皆さんこんにちは!本日も発達障害等に関する学びや情報交換の場所なることを願って投稿させて頂きます。今日のトピックは「発達障害児にパソコン教室(パソコン)との関係」についてです。
「発達障害の子どもをパソコン教室に通わせようかしら?」と悩んでいる保護者の方へ、パソコン教室に通うメリットや、発達障害とパソコンとの関係性をお伝えします。
パソコンとの上手な付き合い方を身につけ、健やかに過ごす手助けになれば幸いです。
目次
パソコンが必須スキルの時代=発達障害の子供に追い風?

2020年から小学校で「プログラミング教育の必修化」がスタートし、オンラインでの授業も一部始まっています。子供たちの学習にパソコン・タブレットなどのデジタル機器が当たり前になりつつありますね。
そして、このパソコンが当たり前の時代は発達障害の子供にとって「大歓迎」かもしれません。
その理由を「ASD(アスペルガー症候群)」と「ADHD(注意欠如多動症)」とを例にして説明します。
発達障害とパソコンとは相性が良い「ASDの場合」
ASDの子供はパソコンの操作を理解しやすい傾向にあります。どういう事かを今から説明しますね。
ASD(アスペルガー症候群)の特徴は「曖昧さが苦手・ルールが明確」です。
- たとえ話やことわざなどの理解が苦手。
- 決められた手順に強くこだわる。
一方、パソコンの特徴は…
- パソコンに何か作業を指示する時、ルールは明確。
- 手順通りに指示すれば、正しく作業が行われる
なんだか、ASDの子供とパソコンとの特徴は似ていると思いませんか?
「それくらい分かってよ…」とこちらが願っても、適切な表現・手順をふまないと「パソコン=子供」には上手く伝わりません。まるで兄弟のようです。
パソコンの操作に慣れやすく、相性が良いのも、うなづけますね!
発達障害とパソコンとは相性が良い「ADHDの場合」
パソコンを活用すると、ADHDの特徴を学習行動に結びつけやすくなります。どういう事かを説明しましょう。
ADHD(注意欠如多動症)の特徴は「落ち着きが無い・不注意」です。
- じっとしていられない、順番を待てない。
- 思いついたらすぐに行動。
- 忘れ物をしやすい。
- 集中力が続かない、気が散りやすい。
このようなADHDの子供の特徴に対して、パソコンが活躍します。
- 特定の文章や絵を強調して表示したり、動画や音楽を流すなどによって、注意力・集中力を持続させる。
- スケジュール管理が簡単。うっかりミスを防ぐ。
- 思いついたことを、メモアプリで文章や音声として記録したり、ネット検索して調べたり、同時並行で素早く行動できる。
いかがでしょうか。パソコン・タブレットなどのデジタル機器は、ADHDの特性を上手く学習につなげているのが分かりますね。
パソコン教室に通うメリット

発達障害とパソコンとは相性が良いことはわかりましたね。
それでは、パソコン教室に通うと発達障害の子供にどのようなメリットがあるのかを紹介しますね。
学習を通して成功体験を得る
パソコン教室に通うことによって「絵が描けた」「文字が書けた」「文章が読めた」「計算が出来た」など、学習の成功体験「私にも〇〇できる!」を得られるかもしれません。
健常者の子供と同じように発達障害の子供にも「なぜ」「どうして」「もっと知りたい」という好奇心や向上心があります。しかし、従来の学習法では十分に応えられませんでした。
ところが、パソコンの登場によって、発達障害児の好奇心や向上心を育み、学ぶ楽しさ(分かる喜び)を体験させることが容易になりました。
それでは、具体的にどのような学習の成功体験が期待できるのかを紹介しますね。
パソコンの機種に関係なく取り組める内容をピックアップしたつもりですが、一部パソコンの機種によっては扱えない内容があるかもしれません。
自信につながる学習体験「読み書き」
読み書きは学習の「基本のキ」です。ここでつまずくと、発達障害の子供の学習意欲に支障が出てきます。
ところが、発達障害の子供は学習障害を併発することが珍しくありません。特に「読み書き」で苦労されている発達障害の子供は多いようです。
パソコンを使えば、かなり楽になる部分があるんです
学習障害(LD)について詳しく知りたい方は、こちらの記事を参考にしてくださいね。
上手く書けない
「漢字を正しく書けない・先生が黒板に書いた文章をノートに上手く書き写せない」など書くことに問題が見られると、学校の勉強が遅れがちになります。
しかし、パソコンでのワープロ打ちを覚えてしまえば問題解決です。ワープロの使い方は、おそらくほとんどのパソコン教室でも教えているはずです。
慣れてくると、文字の大きさ・種類・色などを自分好みに変えられるので、漢字を覚えたり、文章を書くのが楽しくなってしまうかもしれませんよ。
上手く読めない
「文字が逆さまに見える・二重に見える」など、読むことの学習障害もやっかいですよね。周りからは理解されづらく、子供さんやご家族は苦労しているのではないでしょうか。
そんな方に、是非知ってもらいたいパソコンの機能があります。
「読み上げ機能」をご存知でしょうか?
- パソコン等で作成したテキストのファイルであれば読み上げてくれます。
- 今ブラウザを通して見ているこの記事も読み上げてくれます。
これらは、最近のパソコン・タブレット・スマホに標準搭載されている機能です。
「読み上げ機能」の使い方は、パソコンやブラウザの種類によって異なります。詳しい方法はパソコン教室などの先生に聞くと良いでしょう。
また、学校などで配布されるプリントなどはVoice4u TTS (Text-To-Speech) というアプリをオススメします。
スマホでプリントを撮影して読みたい部分を選択するだけです。有料アプリではありますが、非常に助けになるアプリかと思います。
参考元:Voice4u TTS (Text-To-Speech)
▼ダウンロードはコチラ!
これらの機能をしっかりとマスターすれば、読めないことに気後れすることは少なくなるでしょう。
自信につながる学習体験「写真・イラスト」
写真・イラストなどの編集をパソコンで扱えるようになると、発達障害の子供の学習やコミュニケーションの手助けとなるでしょう。
なぜなら、発達障害の子供たちは「聞いて覚える・文章を読んで覚える」よりも「写真・絵などを見て覚える」のが得意と言われているからです。
とはいえ、最初から「画像編集の専門技術」を覚える必要は全く必要ありません。
まずは、デジカメやスマホで撮影した写真をパソコンに取り込んで、簡単な説明の文章を加える程度のスキルを身につければ十分です。
例えば、プレゼンテーション用のソフトとして有名な「Microsoft PowerPoint(パワーポイント)」を使えば「植物日記のスライドショーby 筆者作」なんか簡単に作れちゃいますよ。
私の知り合いの家族は、お弁当の写真を毎日撮って「お弁当日記」を作っています。親子でハマっているみたいです。
パワーポイントを扱っているパソコン教室は比較的多いでしょう。発達障害の子供の好奇心を刺激しながら、写真編集と文章作成の基礎を学べるのでオススメです。
一度、試してみませんか?
参考元:Power PointのWEBブラウザ版
「写真・絵」を使った学習のメリットについて、詳しく知りたい方は「こちらの記事」がオススメです。
パソコン教室以外のオススメ学習「番外編」
条件やタイミングが合わず「パソコン教室に通わせられない」とガッカリする必要はありません。
デジタル機器を使って子供の学習意欲を高める方法はたくさんあるためです。今回は学習意欲を高める方法の中から、オススメのアプリを2つ紹介します。
番外編1「オーディオブック」
読むのが苦手な子供でも、子供が興味・関心のある情報を「耳=音」から吸収し、知識や教養を広げることが期待できるでしょう。
最近はプロのナレーターや声優さんが朗読してくれる電子書籍「オーディオブック」が増えてきました。
日本でもいくつかのオーディオブックが存在していますが、ここではアマゾンが運営している「Audible(オーディブル)」を紹介します。
- 特徴1:月額1500円で毎月1冊のオーディオブックを購入可能
- 特徴2:返品・交換が可能なため、子供が納得できる1冊を選択可能
Audibleには30日間の無料体験がありますので、興味のある方は試してみてはいかがでしょうか。
参考元:Audibleの公式サイト
▼ダウンロードはコチラ!
番外編2「デイジー教科書」
発達障害のような学習に困難を抱えた子供たちのために作られている「デジタル教科書」です。
上手く文章が読めない子供でも読みやすいように、行間を広げたり、文字の色を変えたり、ルビをふったりなどの工夫がなされています。詳しくは以下の紹介動画をご覧ください。
いかがですか。私はこの動画を見て「この教科書を使って勉強したい!」とワクワクしてしまいました。
興味を持たれた方は以下リンクから詳細を確認していただけます。
参考元:デイジー教科書の公式サイト
パソコン教室の選び方のポイント
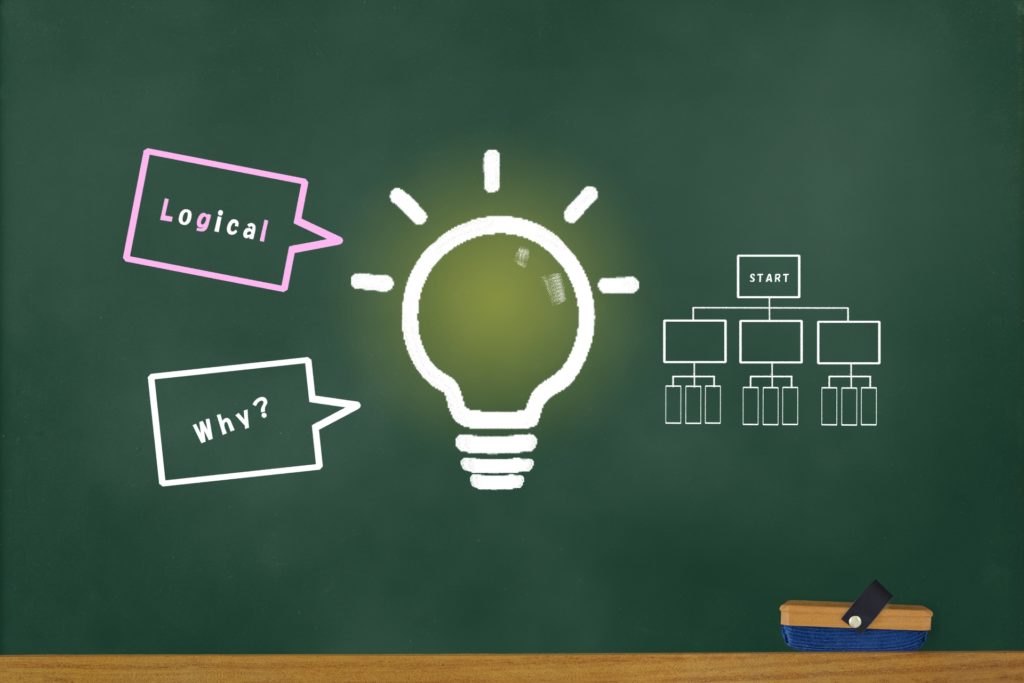
パソコン教室に限らず、子供を習い事に通わせる時、教室選びで悩まれる親御さんは多いと思います。
- 未経験者でも大丈夫?
- 料金設定?
- 個人指導?
教室選びのポイントはいくつかありますので、今回は「発達障害の子供」にポイントを絞ってお伝えしましょう。
発達障害に対する知識と指導経験
「発達障害に対する知識と指導経験の有無」は教室を選ぶ時の重要チェックポイントです。
発達障害は、見た目には分かりにくい障害です。発達障害に対する正しい知識が無いと「不真面目」「ふざけている」と誤解され、子供が傷つくかもしれません。
本の知識通りに子供が振る舞うとは限りません。その時、いろいろな発達障害の子供を指導した経験「体験から学ぶリアルな知識」が不可欠です。
以上の2点「知識と指導経験」については、事前に確認することが大切ですね。一例として、次のように質問してみてはどうでしょうか。
- 私の子供は、〇〇という発達障害ですが、これまでに私の子供と同じ発達障害の子供を受け入れたことはありますか?
- 〇〇という発達障害について知っていますか?
- 学校で落ち着かなくなると、△△みたいに行動するのですが、もし同じようなことが起きたら、どのように対応できますか?
自宅でパソコンを使う時の注意点

パソコンのメリットに気づいて、自宅でもパソコンを活用しようと考えている方もいるでしょう。
ただし、気をつけてほしい点もあります。パソコンのメリットだけでなく、デメリットもしっかりと理解しておくと安心ですね。
「生活リズムの乱れ」と「ネット上でのトラブル」
健全な子供の成長には、規則正しい睡眠時間・バランス良い食生活・楽しい学校などが大切になります。
しかし、発達障害の子供は時間管理が苦手なことが多いようです。パソコンに夢中になり過ぎてしまい、食事も摂らず・睡眠時間を削ってまでパソコンに没頭してしまう子供もいます。
厚生労働省は「デジタルディスプレイ機器を1時間使った場合は15分程度の休憩」を推奨しています。
参考元:情報機器作業における労働衛生管理のためのガイドライン
「ソーシャルゲームに課金」「不用意な書き込み」「有害な情報」など、知らない間にトラブルが大きくなっていることもあります。
とは言え、24時間子供を見守るのも大変ですよね。あまり干渉し過ぎると喧嘩になったり、パソコンが嫌になってしまうかもしれません。
そこで、今回オススメするのがWindows製のパソコンに標準搭載されている「ファミリー機能」です。代表的な機能を3つ紹介します。
- 有害情報のブロック
- 課金制限
- 使用時間の制限
特に、3つ目の機能「使用時間の制限」は便利です。各曜日、子供が使用できる時間を設定できます。
「ファミリー機能」の詳しい設定方法は以下の記事が参考になります。
参考元:子供のインターネットやYoutubeの使用時間を制限する方法 Windows10パソコンに標準搭載「ファミリー機能」がおすすめ!
「スクリーンタイム」という似た機能があります。
参考元:アップルのサポートサイト
子供が安心して使えるパソコン環境を整えましょうね!
ブルーライト対策
ブルーライトとは、パソコンやタブレット、スマホなどのデジタルディスプレイに使用されている青色光です。なくてはならない技術なのですが、人体に対する影響が心配されています。
人体にタイスル影響とは、例えば「ブルーライトによる網膜・眼精疲労・睡眠・精神・肥満」などが挙げられます。
参考元:ブルーライト研究会
ただしブルーライトの調査・研究は始まったばかりなので、ブルーライトによる人体への影響が完全に証明されたわけではありません。
そのため、心配であればブルーライトに対する予防を対策してみてはどうでしょうか。今回はオススメの対策を2つ紹介します。
ディスプレイの「輝度」と「色温度」を調整
パソコンのディスプレイの「輝度」や「色温度」を下げるとブルーライトの影響を軽減することができます。
もちろん、あまり下げ過ぎると画面が見づらくなってしまうので、上手く調整してみてください。
「Night Shift」という機能があり、時間帯に応じて色温度を調整してくれます。
ブルーライトを軽減するフィルムやメガネを利用
2つ目のオススメが、ブルーライトをカットするフィルムをディスプレイに貼る方法とPCメガネを使うやり方です。
ネットで「ブルーライトカットフィルム」「PCメガネ」と検索すれば、いくらでも見つけられます。参考までに商品を紹介しますね。
商品選びのポイントは「カット率」です。例えば「カット率50%」の商品はブルーライトを半分カットします。
下記で紹介しているブルーライトカットはカット率が平均で68.3%でおまけにUVカットもしてくれる優れものです。
こちらはブルーライトカットフィルムです。モニターに貼り、ブルーライトカット効果を狙います。
カット率は平均で48%ですから、ブルーライトカットメガネと組み合わせて利用するのもいいでしょう。
補足として、カット率が高いほど予防効果は高いのですが、カット率によって画面の見え方が変わります。子供と相談しながら決めるのが良いでしょう。
ブルーライトカットフィルムはパソコン以外のタブレットでも同効果を期待できるので、ぜひ検討してくださいね。
タブレット学習については下記の記事も参考にしてください。
困った時の相談先

パソコン教室に限らず、困った時に相談に乗ってくれる場所を確保しておくことは大切です。
子育ての仕方は一人ひとりの子供によって違います。これが正解というのはありません。だからこそ、周囲の人たちの知恵や経験が役立ちます。
特に、発達障害の子供の場合、発達障害に関する知識と経験を持つ人たちの助けは心強いものとなるでしょう。
発達障害者支援センター
発達障害者支援センターとは、発達障害児(者)への支援を総合的に行う専門機関です。
医療・福祉・教育などの機関と連携しながら、発達障害児(者)や家族からの相談に応じてもらえます。
参考元:全国の発達障害者支援センター一覧
放課後等デイサービス
・放課後や夏休み等に子供が通える「家と学校以外の居場所」としての役割
・障害を持つ子供の学習・身辺自立などの支援
・発達障害に対する知識や指導経験を持つスタッフが対応
相談先として放課後等デイサービスを勧める理由は3つあります。
いかがでしょうか。覚えておいて損はしないと思いますよ。
放課後等デイサービス内容について詳しく知りたい方は、以下の記事で詳しく紹介していますので、併せてご覧ください。
まとめ
今回は「発達障害とパソコン教室」についてお話させて頂きました。
個人差はありますが、発達障害とパソコンとの相性は良いようです。
パソコン教室を通して、発達障害の子供がパソコンと出会い「学ぶ楽しさ=成功体験」を経験する…今回の記事がそのきっかけになれば幸いです。
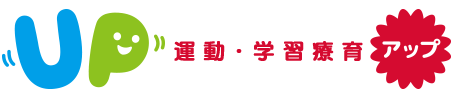
放課後等デイサービス「運動・学習療育アップ」では、発達障害の子供たちに向けたパソコン教室を行なっています。
子供たちの将来(就労)を見据えながらのパソコン教室は、おかげさまで人気です。
もちろん、パソコンが苦手・体を動かすのが大好き!というお子様には、様々な体の使い方を体験できる「運動療育」も用意していますよ。
発達障害の子供の子育てに関する質問を心よりお待ちしております。
▷▷▷メール・電話での相談、無料体験を実施中◁◁◁
最後までお読みいただき、ありがとうございました。



