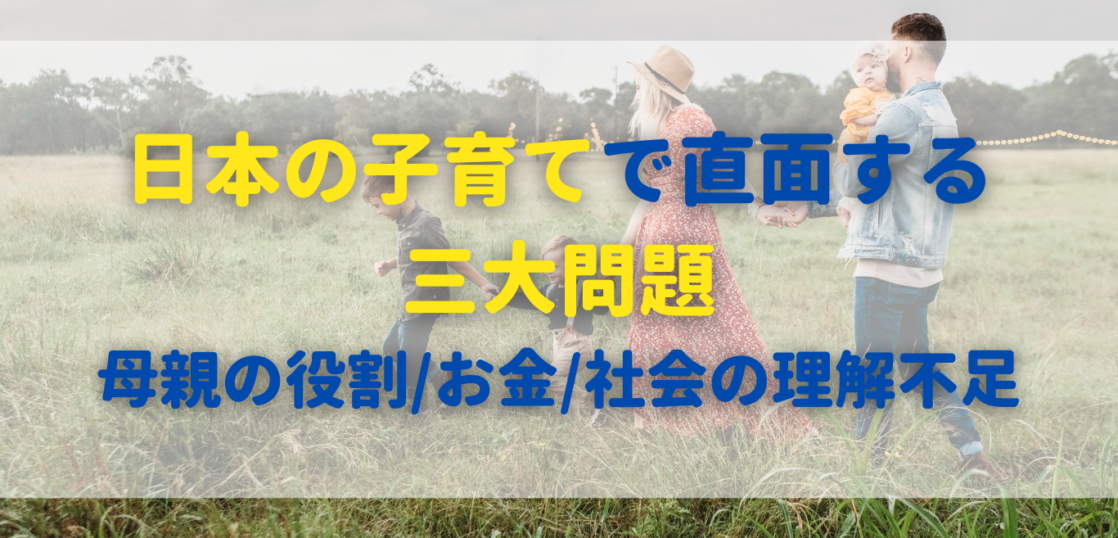皆さんこんにちは!本日も発達障害等に関する学びや情報交換の場になることを願って投稿させて頂きます。今日のトピックは「日本が抱える子育ての問題」についてです。
皆さんは、今の日本が子育てしにくい場所だと思いますか?
この記事では、実際に今の日本は子育てに対してどのような問題を抱えているのか紹介していきます。
ぜひご覧ください。
目次
日本が抱える子育ての問題とは?

実際に日本が抱えている子育ての問題とは何でしょうか?
今回は大きく3つに分けて説明します。
・母親への負担が大きい
・お金の補助が十分ではない
・社会の理解が不足している
母親への負担が大きい

日本では、子育てを辛いと感じる母親が多くいます。
なぜなら、今の日本では、「育児は母親がするもの」という固定観念が根強く残っているからです。
その結果、孤立し、苦しんでいる母親がいるという問題があります。
かつての日本では、「男性は外で仕事、女性は家で家事や育児」という考えが当たり前でした。
そのため、家事育児は男性ができないという固定観念が浸透しています。
実際に、女性の一日における家事育児に費やす時間は454分(7時間34分)なのに対して、男性は83分(1時間23分)となっています。 (男女共同参画局、生活時間の国際比較 平成28年のデータ)
日本では家事や育児の負担が父親に比べて母親に集中していると言えそうです。
共働き、専業主婦、専業主夫など様々な家族の形がありますが、家族で育児や家事の負担を考えてみることも必要ですね。
お金の問題

子育てにかかるお金が負担になっているという人もいます。
お金を理由に子育てを断念してしまうような状況も生まれてしまっています。
補助金
子育てをする上で多くの人が受け取れる補助金として「児童手当」があります。
ですが、こちらも所得の制限があったり、支給額が不十分だという声もあります。
児童手当以外にも、子どもの障害や、1人親世帯や、コロナ禍など状況に合わせた様々な補助金もあります。
そちらを合わせても、まだまだ不十分だと考えている人も少なくありません。
また、子育て支援について、自治体ごとに支援が違うという問題もあります。
子育てしやすい地域としづらい地域の格差があるのも不公平ですね。
教育費、教育格差
教育費がかさむことも大きな問題になっています。
子どもがすべて公立学校に通った場合でも約800万円、すべて私立の場合だと2000万円以上も教育費がかかります。(教育投資参考資料集)
最近では、幼稚園や保育園の無償化、小学生以上への就学援助制度などもあります。
一方で、それらも対象世帯が限られるなど、十分な補助とは言えません。
また、教育にお金がかかることで、教育格差も広がってきているという問題もあります。
社会の理解不足

今の日本社会は、子育てに十分な理解があるとは言えない状況が続いています。
具体的に、どのような場面で子育てへの無理解へ直面するのでしょうか。
仕事との両立が難しい
職場の理解不足で、女性が子育てと仕事を両立させることが難しいという問題があります。
出産する1年前には働いていた女性のうち、約7割が出産後には仕事についていません。また仕事を辞めた女性のうち、約3割が「仕事と育児の両立の難しさ」や「解雇、退職勧奨」という両立環境がなかったことが理由で仕事を辞めたというデータもあります。
子どもが生まれると、体調や行事など、仕事よりも子どもを優先したい状況がたくさんあるでしょう。
今の日本では、どうしてもプライベートよりも仕事優先の考えを持つ人も多く、そこに両立の難しさを感じる人もいるようです。
ベビーカー問題
子育ての無理解は職場だけではありません。町中でも、子育てへの理解不足を実感する機会はあります。
その1つの例が、「ベビーカー問題」です。
2022年11月に元バレーボール選手である大山加奈さんがSNSに投稿した内容に端を発します。
双子用のベビーカーでバスに乗ろうとしたら、乗車拒否された問題です。
大山さんに限らず、電車やバスの中で子どもが迷惑そうな扱いを受けることもあります。
子どもを育てている親自らが助けを求めることが必要という意見もありますが、もっと社会全体が子育てに優しい社会になってほしいものですね。
まとめ
今の日本が抱える子育て分野での問題を見てきました。
・母親へ負担が集中している
・お金の補助が不十分
・社会の子育てへの理解が不足している
今回取り上げた問題はまだまだ氷山の一角だと思います。
もっと気付かれていない、見えていない問題があります。
一方で、ゆっくりとではありますが、改善の方向に向かっているのも事実です。
問題があるのだと悲観的になりすぎず、改善させていきたいですね。