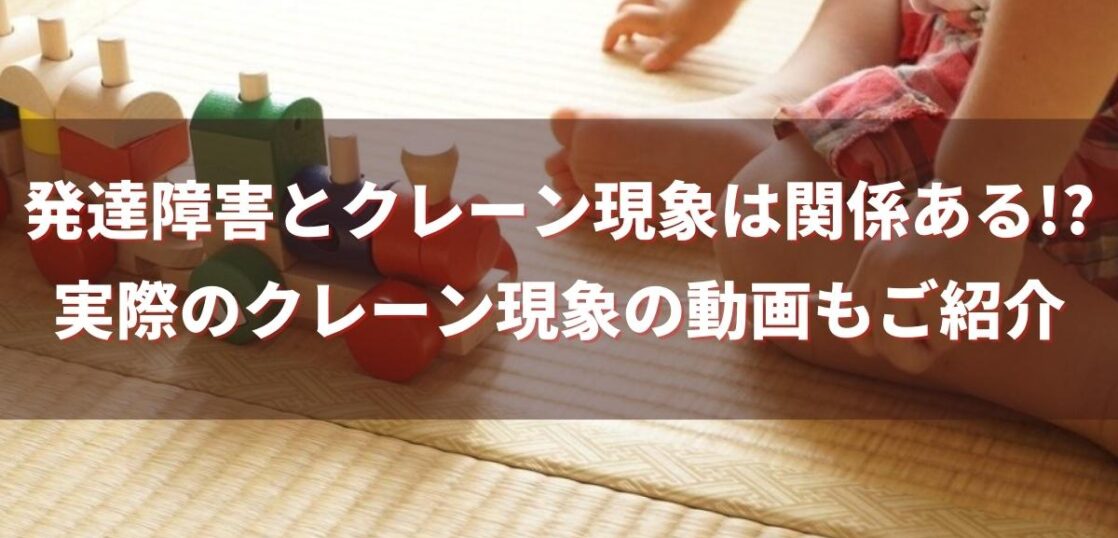皆さんこんにちは!本日も発達障害等に関する学びや情報交換の場所なることを願って投稿させて頂きます。
今日のトピックは「発達障害とクレーン現象の関係」についてです。
クレーン現象は他人の手や腕を代わりに使い、対象に近づける行動がクレーンに似ていることから名づけられました。
発達障害を抱えている子供の中には、クレーン傾向を抱える場合があります。
今回は発達障害とクレーン現象について解説しますので、是非正しい知識を取得して子供と接していただければ幸いです。
目次
クレーン現象=発達障害とは限らない
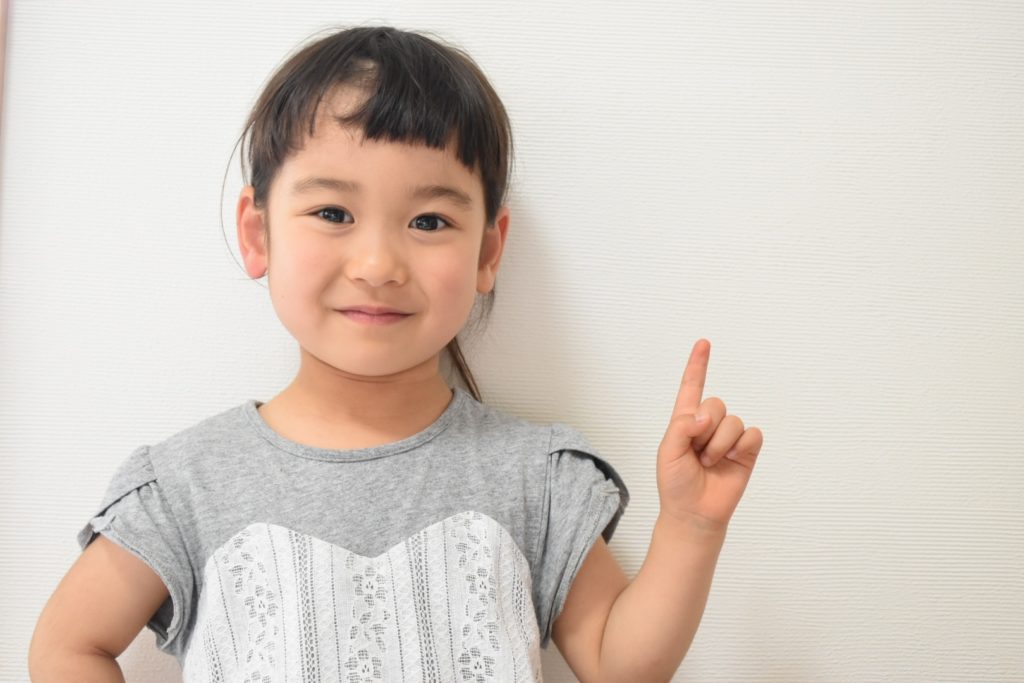
子供にクレーン現象の傾向を見つけたら「うちの子が発達障害!?」「どうしよう!?」と考えが先走ってしまう人もいるかもしれません。
前提として知っておきたいのは、クレーン現象の傾向がある子供が「必ず」発達障害が関わっているわけではありません。
定型発達児童でもクレーン現象は見受けられます。
よって素人目でクレーン現象や発達障害を判断することは困難です。まずは落ち着いて、クレーン現象以外の行動も観察してみましょう。
そもそもクレーン現象とは

クレーン現象とは、「取って欲しいモノ」「して欲しいこと」などを意思表示する際に、保護者の手や腕をクレーンの様に使って欲しい「対象」に近づける行動を言います。
具体的な行動
具体的にどのような行動をいうのでしょうか?クレーン現象について紹介している動画がありましたのでご紹介します。
動画では「飲み物が欲しい」などの欲求があったとしても、対象に指を差すなどの行動を取らず、保護者の手や腕を使いアピールする行動になってしまいます。
SNSでも同現象を体験した方のツイートを確認できました。
ツイートされた方のように、クレーン現象という名前を知らない人は少なくありません。医師に言われて初めて知る人が多くいます。
指で差すことをなかなか覚えない
一般的に、子供は1歳半頃から「指を差す」ことを覚えます。そして対象に向かって「あれは何?」「これが欲しい」などの意思表示をします。
しかし発達障害を抱えた子供は「指を差す」行動をなかなか覚えない傾向が見られます。
成長の偏りにより「出来ること」「出来ないこと」に極端な差が出てしまう為です。
一方で、「興味のあるモノ」を見つけたとしても、
- 何か分からないから怖い
- 安全か確かめたい・安心したい
- どう触ったらいいか分からない
などの理由から、保護者に救いを求めている場合もあります。
以上の通り、クレーン現象なのか発達障害なのか素人で判断するのは難しいのです。
クレーン現象への対処法

クレーン現象の傾向がある子供に、発達障害を抱えている事例は少なくありません。なので、「クレーン現象をやめさせるには…」と悩んでいる保護者も少なからずいるでしょう。
しかし、クレーン現象そのものが悪い行為ではありません。
クレーン現象が見受けられる子供を叱ることは必要ありません。
子供の要求に対し、少しずつゆっくりと教えていくことが大切です。
しつこく何度も教えない
クレーン現象を止めさせたい一心で、何度も説明しがちになってしまうかもしれません。子供自身も驚いてしまいますので、ゆっくり、丁寧に対応することが望まれます。
子供自身が、色々な物や音に興味を持たせてあげることが重要です。
目を合わせる方法
上で紹介したクレーン現象の参考動画の中に、目を合わそうとしない子供の様子が映っています。アイコンタクトはコミュニケーションで大切な行動の1つです。
これに関する記事があります。よければご覧下さい。
クレーン現象以外にも気になる行動
クレーン現象同様、子供の発達に対して「あれっ?」と思う現象は他にもあります。
・つま先歩き
文字通り、つま先立ちの状態で歩いていることが多い現象です。足に触れるモノに極度な不快感を感じる「感覚過敏」を抱えている場合もあり得ます。
・逆さバイバイ
相手に手の甲を向けてバイバイする現象です。バイバイの動作を見て真似する時に、本人からすると相手の「手のひら」が見えている為、自分の「手のひら」を自分に見えるように手を振ってしまいます。
ですので、相手からには「手の甲を見せて手を振っている」「手の向きが逆さ」となるのです。
その他もしっかり観察していきましょう。
クレーン現象と発達障害との関係

発達障害を抱えた子供によるクレーン現象は、自閉症スペクトラム障害(ASD)を抱えている場合が多くあります。
そもそも発達障害とは?
発達障害とは、生まれつき「脳の機能障害」により「出来ること」「出来ないこと」の成長に極端な違いが出てしまうことで「生活に支障をきたす」症状の総称です。大きく3つに分類されます。
ASD:自閉症スペクトラム障害、アスペルガー症候群
- コミュニケーションが苦手
- 相手の目を見ない
- こだわりが強い
▼ASDについて別途記事を用意していますので、興味のある方は参考にしてください。
ADHD:注意欠陥・多動性障害
- 注意散漫で集中できない
- ジッとしているのが苦手
- 気になったモノに意識を向けて行動する為、迷子になりがち
- 忘れ物が多い
▼ADHDについて別途記事を用意していますので、興味のある方は参考にしてください。
LD:学習障害
- 文字の書き取り、読み書きが苦手
- 簡単な計算が苦手
- 単語は読めても、文章になると読めなくなる
などの特徴があります。
▼LD(PDD)について別途記事を用意していますので、興味のある方は参考にしてください。
発達障害の症状は様々
発達障害の症状は抱えている人により様々です。ASDを抱えている人がいれば、ASDとADHDの併存、上で紹介した以外の障害を併存している人もいます。さらに、症状の重さも様々です。
発達障害が見受けられたら?

もしお子さんに発達障害の症状が見受けられた場合、どのように対応すればいいのでしょうか?
例えば今回紹介したクレーン現象は、発達障害が関わっている場合があります。
発達障害の根本的な治療法は現在見つかっておらず、薬の処方による症状の軽減や社会に対する適応力を身につける為の療育が主な治療法です。
そうだとしても早期発見、早期療育により、症状の軽減、改善は見込めます。
保護者の方に置かれましてはどうか1人で悩まないでください。
発達障害の子供を対象に、社会への適応力を身につける為の「治療」「教育」のことです。
1歳半健診・3歳児健診
市区町村で行われる健診で、対象のご家庭には通知が届きます。
○ 根 拠 (母子保健法)
引用先:厚生労働省
第12条 市町村は、次に掲げる者に対し、厚生労働省令の定めるところにより、健康診査を行わなければならない。
1 満1歳6か月を超え満2歳に達しない幼児
2 満3歳を超え満4歳に達しない幼児
第13条 前条の健康診査のほか、市町村は、必要に応じ、妊産婦又は乳児若しくは幼児に対して、健康診査を行い、又は健康診査を受けることを勧奨しなければならない。
発達障害を抱えていると分かる年齢は、幼稚園や保育園などでの集団行動やコミュニケーションが必要になる「3歳頃〜」が多いのです。
SNSの活用
発達障害で悩む保護者は数多く、Twitter、Instagram、FacebookなどのSMSを活用し情報を発信している人も沢山いるのをご存知でしょうか?
例えば、あきさんは娘さんの日常をツイートで綴っていらっしゃいます。
▼発達障害のお子さんを持つ育児ブログを厳選して紹介している記事です。興味のある方は参考にしてください。
支援機関・医療機関の活用
発達障害に関する悩みや相談に関して、全国に展開している支援機関があります。素人では判断が難しい為、専門知識を有した施設を活用し、医療機関の紹介や今後の対応など相談してみましょう。
全国に展開していますが、各施設によって支援内容が異なる場合があります。事前に確認しましょう。
成長の環境作り、保護者の休息も大切
子供の育児は大変です。発達障害を抱える子供は育て方が通常の子と同じようにいかない場合が多く、毎日が格闘になることもあり得ます。
母子共に、負担は計り知れません。

発達障害を抱えた児童を対象に放課後等デイサービスを行っている事業が沢山あります。
下記記事やリンクも併せてご覧下さい。
まとめ
- クレーン現象とは保護者の手や腕をクレーンのように使い、欲しいモノへ近づける意思表示
- 「出来ない」「分からない」または「怖い」などの理由で指を指す場合が多い
- クレーン現象が見られるから、発達障害ではない
クレーン現象が悪い行為であるという認識は間違いです。
理由を探る為に細かな観察して、必要な場合は専門機関などを活用していきましょう。
最後までお読みいただきありがとうございました。