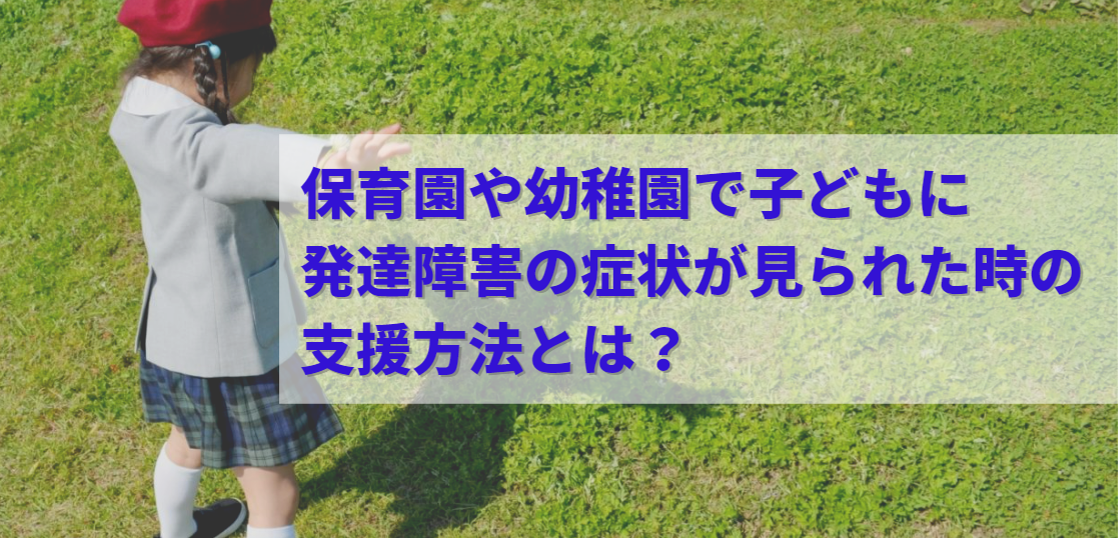皆さんこんにちは!本日も発達障害等に関する学びや情報交換の場所なることを願って投稿させて頂きます。
今日のトピックは「保育園などで発達障害の症状が見られた時の対処法」についてです。
症状にもよりますが、発達障害は保育園に通う年齢で診断されることがあります。
当記事では下記の内容について解説するので、是非参考にしてください。
- 発達障害と気づくのは保育士の場合が多い
- 発達障害の種類とグレーゾーン
- 発達障害の症状が見られた時の支援方法
- 発達障害に対する保育園の対応
目次
発達障害と気づくのは保育士の場合が多い

保育園の現場でお子さんに対し「あれ?」っと気がつくのは、保育士さんです。
それではなぜ保育園などでお子さんが発達障害だと気づくのでしょうか?原因を探っていきましょう。
環境の違いにより行動パターンが異なる
保育の現場は多人数の社会環境を形成しています。
家では家族のみですが保育園では沢山の子供、保育士さんがいますよね?
家で普通に過ごしている子供が、保育園の現場では異なる行動を取る場面もあります。
子供達の見せる何気ない仕草や物事に取り組む姿から「この子は発達障害かもしれない」と気が付く保育士さんもいるでしょう。
「あれ?」っという行動
発達障害を抱えることで、集団行動の面で苦手となる部分が出てきます。下記の特徴は一例です。
- 同じおもちゃをずっと持って離さない
- 他の子供達と集団行動ができない・しない
- 急に叫ぶ・怒りだす・泣きだす
- 一人で遊んでいることが多い
- 他の子供とトラブルになることが多いなど
発達障害の診断を保育士にはできない
発達障害は外傷等の明確な判断基準がありません。例えば、急に大声を上げてしまう子供がいたとします。その行動は
- その子の個性によるもの
- 発達障害の影響によるもの
どちらの影響で起こした行動なのか分かりません。
発達障害であるかどうかを判断するのは小児や児童を受け入れる精神科や神経科で、数か月の検査や問診を経て結論づけます。
発達障害は、外見からでは判断が難しい障害です。保育士さんなら必ず見抜けるとも限りません。
発達障害の種類とグレーゾーン

発達障害とは先天性の脳機能障害により、成長に極端な偏りができてしまうことで「生きづらさ」を抱えてしまう障害の総称といわれています。
ですが具体的な原因や根本的な治療法に関してまだ分かっていないのが現状です。
発達障害の種類別に特性をまとめたので、お子さんに同じ症状があった時の参考にしてください。
ASD(自閉症スペクトラム障害、アスペルガー症候群)
主に対人とのコミュニケーションに関する障害です。
関心事が限定的で興味のないことについては無関心なため、人間関係を築くのが難しく生きづらさを感じる傾向にあります。
例:クラスのみんなはグループになって遊んでいるのに、一人だけ無心で絵を描く
ASDの症状を持つ方は感覚過敏の傾向もあるため、肌触りや音にこだわりを持ちます。
その結果、大人数の場所で作業する際に支障が出るかもしれません。
例:毛布の材質にこだわりをもち、寝つきが悪い
ADHD(注意欠陥・多動性障害)
2パターンの傾向があり、注意欠如と多動性に分かれます。
注意欠如は集中力が足りずにけがをしたり、ミスが多い症状です。
多動性はじっとしていたり待っているのが苦手でやりたい放題動き回るなどがあります。
例(注意欠如):宿題や持ち物を忘れる
例(多動性):先生が話している時に走り回ったり関係ないことをする
LD(学習障害)
文字や言葉の読み書き、簡単な計算など学習面に関する障害です。
正しく文字や数字を認識できないと学習意欲の低下にもつながるため、ツールや道具などの使用が望まれます。
例:読めない文字を適当に読み飛ばす、似た形の文字(「め」や「ぬ」など)を誤認する
上に3つの障害を紹介しましたが、それぞれの障害を併存している子どもは多くいます。
また障害による生活への影響は子どもによって様々です。
よって障害を抱えた子どもそれぞれに合った育児方法が求められます。
グレーゾーン
発達障害と診断されるほどではない「グレーゾーン」のお子さんの存在も忘れてはいけません。
グレーゾーンとは、発達障害の診断基準を満たさないものの、健全児に比べて「成長に偏りがある」「発達障害の症状がある」と診断された状態をいいます。
人口が密集している大都市などでは待機児童の問題があります。
さらには療育施設も足りておらず、大変深刻です。
発達障害の症状が見られた時の支援方法

文部科学省の発表によれば、40人クラスの子供の内、約2人が発達障害を抱えていると言われています。
決して少ない数字ではありませんしグレーゾーンを含めれば、その数は増えていくでしょう。
では「この子は発達障害かな?」と感じた場合、どうすれば良いでしょうか?
頼れる環境を活用する
発達障害は根本的な治療法は見つかっていません。
しかし症状を緩和させるお薬の処方や、社会に適応する為の療育を早期に取り組むことで、抱えた障害をカバーしつつ社会で活躍している人は多くいます。
発達障害を抱えた子供や家族に対し、支援できる環境が整備されてきました。
1人では悩まず、頼れる環境を活用していきましょう。
SNSの活用もお勧めです。
担当保育士との連携
家と保育園では環境が異なる為、想像していなかった行動を取る場合があります。
「家では大人しい」子供が「保育園では暴れ回る」ということもあるでしょう。
普段の行動はどうか、周囲の子と馴染めているか、正しく取り組めているかなど、園での様子を保育士に確認しましょう。
支援機関の活用
発達障害と診断された場合、支援機関を活用しましょう。支援機関は以下の通りです。
- 発達障害相談センター
- 子育て支援センター
- 児童発達支援センター
- 発達障害者支援センター・一覧
上記は発達障害に関する相談、支援を目的とした専門機関です。
- 保育園から診断を勧められたが、どうすればいいのか分からない
- 子供が発達障害か不安
- 障害を持った子供への対応法など
相談は「無料」ですので、身近の専門機関を活用してみましょう。
支援機関は全国に展開していますが、各地域によって支援内容が異なる場合があります。
事前に確認しておきましょう。
デイサービスの利用
発達障害を抱えた子供への成長を促す整った環境、また保護者の休息も併せたサービスを行っている事業があります。

児童発達支援と放課後等デイサービス 運動・学習療育アップでは、障害を抱えた子供を対象に、デイサービス事業を行っています。

また、子育てに向けてのお役立ち情報では、発達障害に関する様々な記事を公開しています。ぜひ参考にご覧下さい。
発達障害に対する保育園の対応

発達障害者支援法とは発達障害の早期発見と発達支援を目的とした法律で、2005年に制定され浸透しつつあります。
しかし地域によって支援レベルや認識度に違いがあり、保育所によっては支援しきれない現状も見受けられます。
例えば発達障害の影響により、周囲の子供達との間で喧嘩へと発展しかねません。
また保育の授業進行に支障が出てしまうなどの理由から、トラブルが続くと退園を迫られる可能性もあります。
まとめ
幼稚園、保育園での環境に「馴染めない」子供には発達障害の可能性があります。
ですがそれが「個性」なのか「障害」なのかを素人は診断できません。
「変わった子」「違った子」と周囲から判断されることもあり、そのたびに保護者の方やお子さんは傷つく可能性があります。
保育園へ通うことが負担にならないよう、普段からお子さんの様子を保育士さんに確認し、相談できる支援機関を把握しておきましょう。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。