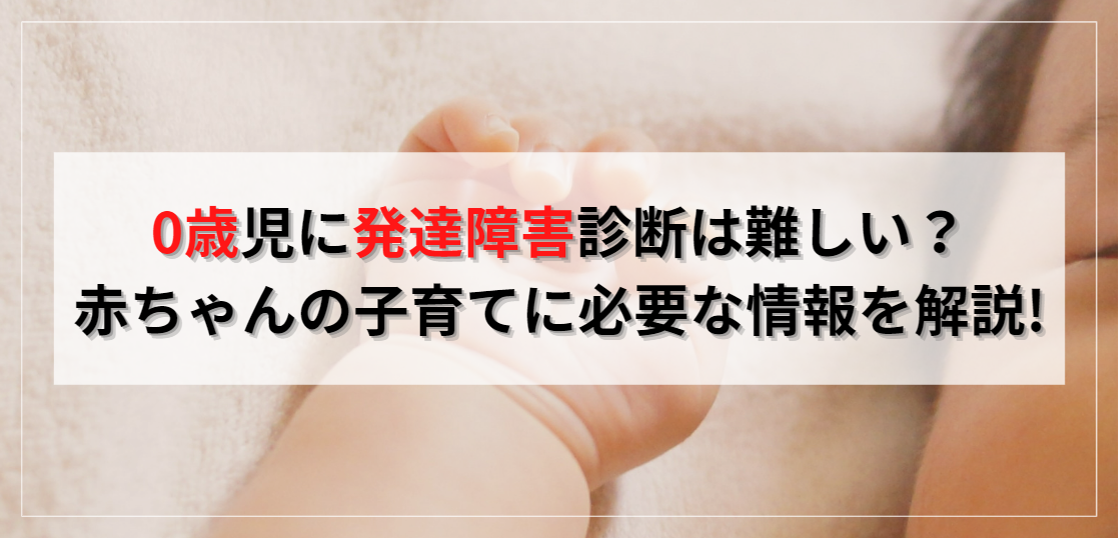皆さんこんにちは!本日も発達障害等に関する学びや情報交換の場所なることを願って投稿させて頂きます。
今日のトピックは「発達障害0歳」についてです。
「私の赤ちゃんは周りの子と明らかに違う……」とお悩みの方はいませんか?
赤ちゃんの様子はひとりずつ違うとはいえ、不安になります。
今回は「0歳児でも発達障害診断はできるのか」のような誤解しやすい情報を解説するので、ぜひ不安を解消してくださいね。
目次
0歳児で発達障害の診断は難しい

結論からいうと、一般的に0歳児へ発達障害の診断を下すことはありえません。
自閉症の症状でもある「視線を合わせない」「素材が気に入らずソワソワするなどの感覚過敏」は、発達障害以外でもよく見られる傾向です。
そして、よく見られる傾向が発達障害だと判断するのは、0歳児の時点で難しいといわれています。
発達障害の診断は、早くて3歳児健診で行います。
よって赤ちゃんが「他の子と違って目線を合わせない、うまく寝てくれない」など疑問に思ったとしても、即発達障害と結びつけるのは無理があるのです。
自閉症に関しては別の記事でまとめています。興味のある方はぜひご一読ください。
発達障害と間違われやすい症状6選

3歳児健診までは発達障害と診断されることは難しいとはいえ、どういった症状が発達障害といわれやすいのでしょうか?
赤ちゃんによく見られる「これをしたら発達障害かも?」といわれやすい症状をまとめました。
視線が定まらない
赤ちゃんは視線が合いやすい傾向にあるのですが、視線を外しやすい子もいます。
名前を呼んだり声をかけても無反応である場合も多々あります。
しかし安易に発達障害だと決めていけません。
視線が定まらないのはおもちゃに集中して、周囲を気にしていないだけという理由も考えられます。
表情が薄い
赤ちゃんは信頼関係の強い人と絆を結ぶために愛着行動を求めます。
例えば赤ちゃんに対して親御さんが笑いかければ赤ちゃんは笑顔を見せる、親御さんが赤ちゃんを放っておくと赤ちゃんが泣くなどの行為です。
しかしまれに笑顔を笑顔で返さず、親御さんが放っておいても気にしない赤ちゃんもいます。
人見知りをしない
人への関心が薄いため、誰に対しても警戒心が薄い子がいます。
関心が薄い分、人を構成するパーツである「耳」や「手」、時には身に付けている「メガネ」や「帽子」に興味を示す子もいるくらいです。
何度もお伝えするように、0歳時点で人よりも物に関心を寄せるからといって、発達障害であると判断するのは困難といえます。
抱っこが嫌い
感覚過敏の傾向が強いと、抱っこ時において圧迫感に耐え切れずイヤイヤしていまうかもしれません。
しかし感覚過敏になる人は発達障害以外の方でもあり得るため、0歳児での判断は難しいといえます。
眠りが浅い
赤ちゃんの睡眠サイクルは歳を重ねるごとにつれ一定になりやすいのですが、まれに眠りが浅く夜中に何度も起きたり、朝の目覚めが早かったりとリズムがなかなか取れない子がいます。
眠りが浅いからといって一概に発達障害とは言い切れません。
泣き止まない
好ましくないにおいや触感、光に耐えられないと泣き続けてしまう可能性があります。
以上のような感覚過敏は、発達障害のうち自閉症の症状の方が持つ特徴の一つです。
赤ちゃんの好みのにおいや肌触りの良い材質を考慮して生活環境を整えると、落ち着く可能性があります。
親御さんにできること

ご自身の赤ちゃんが他の子と様子が違ったとしても心配はいりません。
親御さんにもできることのうち、重要な3点をお伝えします。
相談先を見つけよう
赤ちゃんのことを心配するあまり、親御さん自身の元気が無くなってしまっては本末転倒です。
一人で悩まず思い切って専門家に相談して、いっしょに考えて行きましょう。
【相談先一例】
- 市区町村保健センター
- 児童相談所
- 子育て支援センター
- 発達障害者支援センター・一覧
- 1歳半〜3歳児健診
相談の最大の効果
赤ちゃんについて相談すると、親御さん自身の不安やストレスが減って安心感(元気)を取り戻せます。
もちろん友達や親などに相談するのも良いのですが、悩みの内容が専門的な場合は専門家に話を聞いてもらうのが良いでしょう。
こんな風に書くと「えっ?子供ファーストでしょ。子育てしたことがないのでは?」とお叱りを受けるかもしれません。
ですが赤ちゃんの食事、排せつ、お風呂、睡眠などのように、生きるために必要な全てをお母さんに頼り切っていると、親御さんが元気でないと赤ちゃんだって元気に成長できません。
お母さんの笑顔はすごい
新生児模倣という現象をご存じでしょうか?
赤ちゃんの目の前で、お母さんが下を出したり、口をすぼめたりすると、赤ちゃんがまねをする現象です。
生後2カ月ほどで消失するのですが、何気ない顔まね行為にはものすごい効果があるといわれています。
【新生児模倣手順】
- 赤ちゃんが親御さんの表情をまねする
- 顔まねした赤ちゃんを見て、親御さんはちゃんを大切にする思いが高まる
- 大切にする思いが赤ちゃんの脳の発達に良い影響を与える
以上の結果により、親御さんの表情が赤ちゃん脳の発達にとても大切なんです。
ですから親御さんが暗い気持ちで悩んでいる表情になっていると、赤ちゃんの脳の発達に良くないといえます。
相談前に情報を整理しておく
相談する時は、赤ちゃんの何に困っているのか(言動・コミュニケーション・生活習慣など具体例)を事前にメモ書きして整理しておくのをオススメします。
自分の頭の中が整理され、相談内容を相手に的確に伝えやすくなりますよ。
相談先でのさらなる出会い
相談に出向くと、同じような悩みを抱えている親御さんたちと知り合う機会を得るかもしれません。
親御さんの気持ちをより深く理解できる人は、同じ立場にある親御さんたちです。
同じ悩みを抱える親御さんたちと知り合いになり、感情や思いや情報を交換したり、共有したりしながら、お互いに支え合えるようになると、気持ちが安定して、前向きな気持ちに変わってきます。
以上のように同じ境遇にある人が、対等な関係で支え合うことをピアサポートと呼びます。
まるごと分かり合えるピアサポーターとの出会いは、専門家以上に心強い存在であるともいえます。
発達障害のお子さんと家族の支えとなる福祉サービスを目指している「運動・学習療育アップ」では、発達障害と子育てに役立つ情報を発信中です。

愛情を注ごう
0歳という生後間もない段階で、発達障害かどうかを見極めることは難しいといわれています。
不安な気持ちは分かりますが、はっきりしない段階で悩んでも仕方ありません。
ならば、お母さんの愛情を赤ちゃんに惜しみなく注いであげましょう。愛情が子育ての基本ですよね。
乳幼児期に親御さんができること
親御さんが子育ての基本である愛情を赤ちゃんにしっかりと注いであげましょう。
普通の赤ちゃんでも発達障害の赤ちゃんでも、愛情が子供の成長には不可欠です。
例えば普通の赤ちゃんでも、親御さんからの十分な愛情をもらえずに育てられると、愛着障害などの症状が表れることがあります。
逆に発達障害を持つ赤ちゃんでも、親御さんからの愛情を十分に受けて育つと、自己肯定感の高い大人へと成長できるでしょう。
親御さんのモヤモヤとしたスッキリしない不安感は分かります。
ですが今は親御さんの愛情を、赤ちゃんのこころにたくさん注いであげましょう。
そばにいてあげる
実は興味深い実験があるのでご紹介します。
- 親御さんと赤ちゃんを別々の部屋で5分過ごす
- 赤ちゃんの皮膚温度の変化を調査すると温度が低下
人間の皮膚温度はストレスがあると低下するということが知られています。
つまり赤ちゃんは親御さんとたった5分間離れているだけでストレスを感じたと考えられます。
赤ちゃんが親御さんの代わりに見知らぬ男性と一緒にいても、同様に温度が下がっています。
以上のことから、ストレスが赤ちゃんの成長に良くないことは分かりますね。
親御さんはできる限り赤ちゃんと一緒にいましょう。
スキンシップ
スキンシップには、赤ちゃんの脳を活性化させる働きがあることが知られています。
これにも興味深い実験があるのでご紹介します。
- 生後数日の新生児に視覚・聴覚・触覚の刺激を与え脳活動を計測
- 視覚や聴覚に比べて触覚による刺激では、広範囲に渡る脳活動が見られた
以上のことから赤ちゃんとのスキンシップは、とても大切なだと分かりますね。
またスキンシップという行為自体に相手を安心させる効果もあります。
適切なスキンシップは赤ちゃんの脳の活性化と心の安心感にプラスの効果を与えるといえます。
現在、私は介護士として認知症の人のケアを行なっています。
ケア中において、基本的な技術の一つに「触れる」というのがあります。
この技術を適切に介護に用いることによって、言葉によるコミュニケーションが難しい認知症の人とも良好な関係を築けます。
おそらく、これと同様のことが赤ちゃんと親御さんとの関係にも成り立つでしょう。
発達障害について正しい知識を得よう
発達障害は生まれつきもしくは出産前後に脳機能に障害が起こり、脳機能がアンバランスに発達した状態です。
そして、珍しい障害ではありません。
発達障害の原因
よく「私の育て方に問題があるのでしょうか?」といった質問をお悩みコーナーで見かけます。
しかしながら発達障害の原因は生まれつき、もしくは出産前後に脳機能が損なわれることです。
つまり家庭環境(親の育て方)や本人の性格が直接の原因ではありません。
そして発達障害の最大の特徴は、脳機能の発達に偏りがあることです。
発達障害の例を見てみますと、社会性(対人スキル)・ある特定の能力(読み・書き・計算など)・感情のコントロールなどの一部の機能のみに障害が見られます。
ですが他の機能については正常(もしくはそれ以上)に発達しています。
よって「ある行動は出来るのに、どうして別の行動は出来ないの?」と誤解されやすく「本人が怠けているだけ。努力して頑張ればできるはずだ」と本人を追い詰めてしまいがちです。
発達障害とは脳機能がアンバランスに発達した状態といえるでしょう。
15齢未満で約10%
ADHD(注意欠陥・多動性障害)やLD(学習障害)とされる15歳未満の子供の割合は6~12%、HFPDD(高機能自閉症)やAS(アスペルガー症候群)は1.2~1.5%になるという統計結果があります。
合計すると約10%前後の15歳未満の子供が、なんらかの発達障害であることがわかりました。
ベートーヴェン・モーツァルト・アインシュタイン・ピカソ・レオナルド・ダ・ヴィンチ・織田信長・坂本龍馬などの歴史に名を残す偉人たちは発達障害を抱えていたと言われています。
まとめ
- 0歳児に発達障害診断は難しい
- 発達障害を疑うよりも赤ちゃんへ愛情を注ごう
- 3歳児健診で発達障害診断を受けるのが望ましい
- いつでも相談できるよう赤ちゃんの様子をチェックしよう
0歳児に発達障害の診断は無理がありますので、少なくとも3歳児健診までは気にしすぎずにしましょう。
気にしすぎるよりも赤ちゃんへ愛情を注ぎ、親御さん自身も楽しく過ごしてください。
最後までお読みいただきありがとうございました。