皆さんこんにちは!本日も発達障害等に関する学びや情報交換の場所なることを願って投稿させて頂きます。
今日のトピックは「発達障害を抱える人は優先順位がつけられない?」についてです。
発達障害を抱える人は物事の優先順位を決めて取り組むのが苦手な場合があります。
今回は発達障害を抱える人が優先順位を決められない原因と対処法について解説します。
目次
発達障害者が優先順位をつけられない原因
発達障害の中でも特にASDとADHDの症状が顕著な方に優先順位がつけられない理由は、発達障害に起こる生まれつきの脳の機能障害が原因です。
以下は症状別に解説しています。
こだわるがゆえに優先順位を間違えるASD
ASD(自閉スペクトラム症)は人間関係や関心事が限定的であり、生まれつきの脳の機能障害です。
ASDの症状が顕著になると、自分の関心事以外には興味を示さない傾向にあります。
関心事が優先順位の上位にあればいいのですが、関心事が下位の場合は「空気が読めない」「仕事ができない」などのように、ASDの症状が原因で周囲との関係に亀裂が入るかもしれません。
参考元:ASD(自閉スペクトラム症、アスペルガー症候群)について|厚生労働省
注意不足がゆえに先の見通しが甘いADHD
ADHD(注意欠如・多動症)は集中力の不足や順序立てた行動が苦手な「注意欠如」と待つのが苦手で行動力がゆるぎない「多動性」の2つの側面を持つ、生まれつきの脳の機能障害です。
ADHDの症状が顕著になると、順序を考えず自分のやりたい部分だけ進め、集中力が切れたところで作業がストップし中途半端な状態になる可能性があります。
その結果、先生や上司から「できない子」判定を受けてしまうかもしれません。
参考元:ADHD(注意欠如・多動症)の診断と治療|厚生労働省
優先順位がつけられないへの対処法6選

ASDやADHDの発達障害を抱える人は、脳の機能障害のために優先順位がつけらないことがわかりました。
そこで、発達障害を抱える人でも優先順位をつけやすくなる解決策6選をご紹介します。
ここで取り上げた解決法を一気に行うのではなく、できる範囲から取り組むと継続しやすいでしょう。
- メモを取る
- タスク管理する
- 「報連相」を徹底する
- ルーティン化する
- マネする
- 見直しする
1.メモを取る
メモを取るだけでも十分効果が発揮されます。具体的な効果を4つ、そして注意点を2つをご紹介します。
【メモを取ると得られる効果4選】
- やるべきことが視覚化される
- ヌケ・モレが減る
- 脳の容量(ワーキングメモリ)が空く
- 書くことで気付きを得る
それぞれについて詳しく解説していきましょう。
(1)やるべきことが視覚化される
発達障害に限らずですが、人は言葉では理解しづらい事でも、文字や図にすると理解しやすいと言われています。
例えばやるべきことをリスト化すると、必要なことを忘れずに済み、周囲の人にも迷惑が掛かりません。
メモを取るのが苦手な人は、聞き出したい項目をテンプレート化すると迷わずに済みます。億劫になってしまうと「メモを取る」行為が習慣化しません。
「書いた日付」「やること」「期限」のように項目を区切っておけば、何を書いておくか明確になりますし、万が一分類できない内容があれば、備考欄を追加し書き残しましょう。
メモを取る方法は手書きだけでなく、スマートフォンアプリやパソコンソフト利用もあります。
インターネットにつながっていればどこでも使える「Evernote」「Googleドキュメント」は人気のアプリです。スマートフォンだけでなくパソコンでも使用可能です。
(2)ヌケ・モレが減る
メモを取ったら終わり…ではなく、メモを見返すことで脳は内容を思い出し、思考の整理が行われます。
ADHDの人だけでなく、人間は自分が思っている以上に毎日忘れるものだと分かる結果が、心理学者のエビングハウスが提唱した「忘却曲線」です。
「忘却曲線」は無意味な音節を記憶するというケースで、必ずしもすべてに当てはまりませんが、いかに人は記憶を失うかについて知るのにわかりやすい研究結果ですね。
- 20分後には42%を忘れる
- 1時間後には56%を忘れる
- 9時間後には64%を忘れる
- 1日後には67%を忘れる
- 2日後には72%を忘れる
- 6日後には75%を忘れる
- 31日後には79%を忘れる
以上のことから、ADHDの傾向にあればあるほど、メモを取る重要性はお分かりいただけたのではないでしょうか。
Twitterで、ADHDを抱えている人が実践しているメモ魔の一部シーンを写真入りでツイートしています。
一目で分かると作業効率も上がり、自分以外にも分かりやすくて一石二鳥ですね。
(3)脳の容量が空く
人は作業中に「気になること」があるとそちらに意識が回り、集中力を奪われがちです。
確認ミスやモレの原因になり、周囲の迷惑につながります。
発達障害の人は、定型発達の人に比べて脳のワーキングメモリの働きが弱いと言われ、通常記憶できる量や時間が少ないのです。
「作業記憶」とも呼ばれ、一時的に情報を頭に留めておいて、同時にモノゴトを処理する脳機能のこと。
ワーキングメモリが少ないため、記憶を留めながらの作業継続は向いておらず、記憶しきれていないため作業が非効率になります。
ですがメモを取っていれば、後で見返す際に考えればいいため、今やるべきことに集中でき、結果としてミスを減らせるでしょう。
(4)書くことで気づきを得る
メモを書くと、頭で考えているだけでは気づかなかったことが分かります。
例えば複数の事象を比べてみると関連性が見えたり、先の予測ができたりします。
思考力はADHDでも後天的に身に付けていくことが可能ですので、メモを取りながらその意味や関係について考えるとより効果的と言えます。
効果的なメモの取り方について、当ブログ内で別途記事を設けておりますので、興味のある方はご覧ください。
以上でメモを取ると得られる効果4選は終了です。次にメモを取る際の注意点を2つお伝えします。
【メモを取る際の注意点2選】
- 書いたメモをなくさない
- 周囲に助けを要請する
(1)メモを失くさない対策も行う
ADHDの人は、無意識に何かを置き忘れたり、取り違えたりといった不注意の特徴があるため、メモをどこかへ失くしてしまうことは頻繁に起きてしまいがち。
先にご紹介したような「Evernote」「Googleドキュメント」などのメモアプリならば、かさばらず持ち運びに便利なのですが、スマートフォン自体失くしてしまえば意味がありません。
よってメモを失くさないためには、「失くしもの」を防ぐのしくみづくりが大切です。
「失くしもの」を防ぐしくみづくりは、以下のような方法がありますので、実践できそうであればぜひ試してみてくださいね。
| メモ用紙を大きめにする(A4程度) | 目に留まるサイズであれば、メモを探しやすくなる、周囲の人も反応しやすくなります。 ただし、サイズが大きくなるため荷物がかさばるデメリットあり。 |
| メモを保管する場所は固定 | 自分ルールを策定するといいでしょう。 例えばポケットの中に入れる、バッグの左側に入れるなど。 |
| 指さし呼称 | 本来は製造現場などで安全確認のため用いられている危険予知活動の一つ。 「ヨシ!」と指さしながらの確認を、日常でも取り入れてみましょう。 |
| 紛失防止タグを付ける | スマートフォンと電子タグをBluetoothで接続しておけば、いざという時に位置をおおよそ推測できます。 |
電子タグの一例をご紹介します。家の鍵や財布に電子タグを付けて紛失を防止します。
(2)周囲の人にも配慮をお願いする
発達障害の特性を道具や仕組みですべてカバーするのは難しいので、時には周囲に助けてもらいましょう。
ただし、発達障害であるとオープンにするべきかどうかには注意が必要です。
発達障害をオープンにしているならば、率直に特性について説明します。もし理解してもらうのが難しければ、本やネットの記事、発達障害者支援センターの支援員の方に説明をお願いするなどの方法がありますね。
一方、発達障害をオープンにしていない状態でカミングアウトするのは、雇用契約問題に発展する可能性もあるので、できるだけ避けるべきでしょう。
信頼できる人に、「モノを失くしやすい」ことを伝え、配慮をお願いすることに留める方が良いのではないでしょうか。
2.タスク管理を活用する
メモを取りかつタスク管理すれば、ADHDの特徴をカバーするのに効果的です。
タスクとは「やるべきこと」という意味で、この「やるべきこと」を書き出し、一つずつ実行すれば仕事やプライベートでもモノゴトを前に進めやすくなります。
タスク管理の方法やコツについて解説していきましょう。
(1)やることを書き出す
まずは、先ほどお伝えしたように、やることを全て書き出します。
この時は、順序や書き方などは気にせずに、まずは全て書き出すことに集中しましょう。
この理由は、他のことを考えながら書いていくと、頭に思い浮かんだことを忘れたり、順序はどうしようといった、この時点では重要ではないことを考えてしまうことを防ぐためです。
(2)「やること」「やらないこと」の2つに分ける
ここで言う「やること」とは、「期限が近く重要」なことや「時間に余裕はあるが重要なこと」です。
一方で「期限が近いが重要ではない」「時間に余裕があり重要でもない」といったことは、今やることには入れません。
こうして考える事で、優先順位の考え方が見えやすくなることでしょう。
(3)具体的な行動を考えて実行する
「やること」が決まったら、具体的なやることに細切れにしていきましょう。
夕食をつくるという「やること」でも、献立はどうするか、食材は買いに行く必要はあるか、食材は何を買う必要があるか、などその具体的行動は多岐にわたるものです。
以上のように具体的な小さいやることを挙げていくと「具体的に何からはじめればいいの?」という状態を解決できます。
(4)「マルチタスク」はできるだけ避ける
ここで意識しておきたいのが、ADHDに限らず、人は複数のタスクを同時に進めるのが苦手であるるため、一つずつ取り組む方が良いということ。
複数の作業を同時にこなせる人を「マルチタスク型」と呼び、仕事や処理が早い人と呼ばれます。
実際はマルチタスクの方が非効率であることが多くの研究などでわかっています。
しかしどうしても複数のことをしなければならないという状況も時には発生します。
ですから、できるだけ一つの事に集中することを心掛け、やむを得ない時だけ複数のことをすることも許容するというスタンスで良いのではないでしょうか。
(5)最初は「今日やること」から
タスクの組み方やスケジュールの組み方は一週間や一ヵ月、場合によっては年単位で行う人もいますが、はじめは1日単位で行えば良いでしょう。
見る期間を大きくすると、予測する力やより高度なモノゴトを組み立てる力が必要になってきます。
この辺りは発達障害の特性上、苦手な場合も多いため、まずは目の前の何から取り掛かれば良いかという優先順位付けからトレーニングしていきましょう。
3.報連相を徹底する
「報連相」は社会に出た時によく聞く言葉で、情報を共有したり、問題を複数の人で考えられるなど多くの利点があります。
報告、連絡、相談を略したビジネスの基本とされる略語。
仕事をスムーズに進めるためのコミュニケーションスキルとされ、新入社員研修などではよく用いられる言葉です。
発達障害を抱える人は優先順位や先を読む力、状況に合わせた臨機応変な対応などが難しいといわれています。
しかし「報連相」をしっかり行えばミスやトラブル、方向性の逸脱などを未然に防げる可能性があります。
中には「報連相」が億劫に感じられる人もいるかもしれませんが、毎日仕事の始めと終わりに行うなど、毎日の行動としてルール化してしまえば、続けやすいでしょう。
事例を挙げます。報連相を怠ったために大きなトラブルに発展したというツイート。
報連相がいかに大事かを感じてもらえるのではないでしょうか。
「報連相」がいかに重要かは理解できましたね。
以下は「報連相」を習慣化することで、発達障害の特性をカバーできる点をお伝えします。
(1)進捗を上司が把握できる
常に自分が何をしているのかを知ってもらうことで、上司も他の人との仕事のバランスや仕事の組立て、優先順位を把握できます。
「あの人は何をしているんだろう?」という上司の不安や気がかりの解消にもなるため、お互いに気持ちよく仕事がしやすくなるでしょう。
(2)軌道修正を早期にできる
優先順位や段取りを組み立てるのが苦手なADHDを持つ人は、取り掛かっている仕事が的はずれな場合も多くなりがちです。
「報連相」をすると、その的はずれな進め方を早期に気づいてもらえるメリットがあります。
よって早めに軌道修正すれば仕事を効率的に進められ、かつ「こういう時はこう考えるのか」と自らの学びにもなるため一石二鳥といえるのではないでしょうか。
(3)問題やトラブルを複数人で考えられる
中にはわからないことや、やってしまったミスを1人で抱え込み、いつまでも悩んでしまう人もいます。
ある程度、自分で考えることも大切ですが、考えても何も進まないのであれば、周りに相談すべきです。
場合によっては注意されたり、叱責されたりすることもあるかもしれません。
ですが早期に気づくことで傷が浅くて済みますし、そこから他の人の意見なども取り入れて解決できます。
「軌道修正を早期にできる」の項と同様にその経験から学べることはたくさんあるので、自分を責めずに、次へ活かせるようにしましょう。
(4)自分の性格や傾向を知ってもらえる
発達障害であることをカミングアウトせずとも日々「報連相」をしていれば、周囲は「この人は優先順位を付けるのが苦手だ」とわかってきます。
苦手なことを周囲に知られることに恥ずかしいと感じてしまう人もいるかもしれませんし、場合によっては評価が下がることも考えられます。
しかし隠そうとする方がリスクであり、いつかどこかで破綻するのは目に見えていますよね?
ですから事前に自分の苦手なことを知ってもらえば周囲から危険を知らせて、起こるであろうトラブルを未然に防ぐ可能性が高くなります。
(5)信頼性が上がる
日々「報連相」することで「この人は報連相してくれるから状況がわかって安心できる」と信頼性が上がることもあるでしょう。
意外に報連相ができない人は多く、部下が何の仕事をしているのか把握していないというのは、社会で少なからず問題となっています。
しっかり「報連相」をすれば、効率化のみならず良いコミュニケーションのきっかけになります。
参考元:コミュニケーション不足は「数千万円の損」?米IT企業が取り組む意識改革
4.決まった仕事はルーティン化する
ADHDの人は目についたものからとりあえずやってしまい、やるべきことが疎かになる傾向があります。
ですから何でもかんでもやる前に、やるべきことの中で決まっていることはルーティン化してしまいましょう。
ルーティン化したい作業を確認したら、ふせんやメモへ書き出し、目が届く場所に貼っておきます。
もし作業手順すらすぐ忘れるのであれば、必要最低限の項目を書き出し、その通り実行します。
ルーティン化することで状況に振り回されず、決まった仕事を効率よく終わらせて、他のことに時間を使える余裕が生まれます。
5.人の仕事の方法をマネる
日本には「守破離」という言葉があります。
これは元々、武道や芸道に使われていた言葉ですが、意味としては以下のようなものです。
守:最初は指導者や熟練者の行動や行いを見習い、その通りに行動する
破:基本ができるようになったら、自分なりの工夫や知恵を使って独自の型を試す
離:指導者などの元を離れ、自分なりのスタイルや型を確立させる
まずやるべきは、「守」の部分で、人のやり方をまずはマネることが上達への近道です。
職場では少なからず、仕事が正確で早い人はいるものです。
そういった人を観察していると、その人なりの工夫や心掛けが見えてきます。
自分の仕事に役立ちそうなことがあれば、そこからマネしてみてはいかがでしょう。
自分で考えるのも良いですが、それで上手くいっていないのであれば、上手くいっている人のやり方をまずはマネてみるのが成長の近道と言えるかもしれません。
中には自分に合わない方法もあると思いますが、自分にしっくりきたものはどんどん取り入れていってみてはいかがでしょうか。
6.振り返りをする
結果や起こった出来事に対して、振り返りをする習慣をつけるのもおすすめです。
その時の行動や考えを振り返ると、どこで間違ってしまったのか、どこで上手くいったのかに気づくヒントを見つけられるかもしれません。
そこでわかったことを次に活かすようにすれば、改善のらせん階段を登れるのではないでしょうか。
優先順位をつけたら得られるメリット
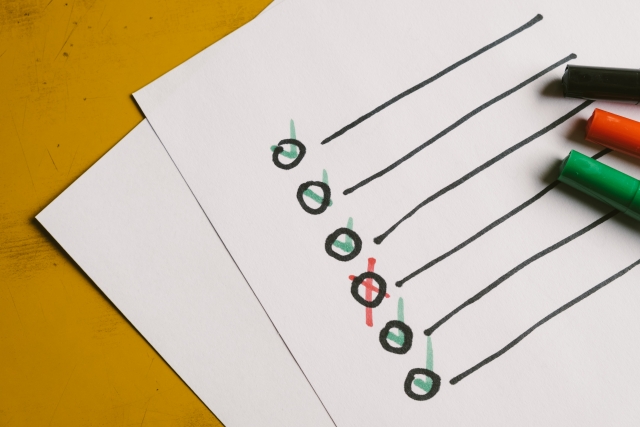
優先順位を付けられるようになればどのようなメリットが得られるのでしょうか?
優先順位をつけて得られるメリットをいくつか取り上げてみましょう。
- 効率よく物事を進められる
- やるべきことを優先できる
- 無駄な時間を使わなくて済む
- 成果を上げられるようになる
- 物事の組立や段取りができるようになる
- 信頼性が高くなる
上記のメリットを見て分かる通り、優先順位をつけることで第三者からの評判が高くなり、スムーズに事が進みます。
また「やるべきことをやっていない」「ちゃんと準備してくれた」など、職場以外でも第三者から感謝してくれる可能性もあります。
まとめ
今回はADHDの人へ向けて、優先順位の付け方をお伝えしました。
いきなり全てをやろうとしても情報が多いためパニックになりがちです。
まずは一つずつ取り組んでいくと良いでしょう。
習慣化すれば優先順位の付け方もわかってきます。ぜひ安心して取り組んでくださいね。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。




