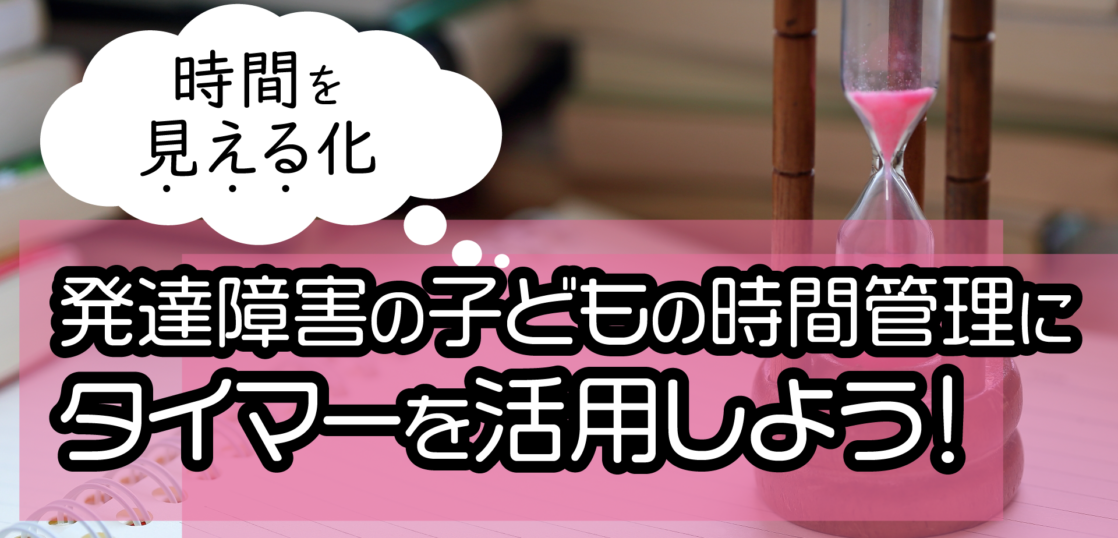皆さんこんにちは!本日も発達障害等に関する学びや情報交換の場所なることを願って投稿させて頂きます。
今日のトピックは「発達障害の子どもがタイマーとどうやって付き合うべきか」についてです。
タイマーがどのように発達障害の子の支援に役立つのか、そして具体的にはどういったタイマーをどうやって使うと良いのかを解説していきます!
目次
発達障害におけるタイマーの効果:時間が見える化できる

タイマーを使うことでどのような効果が期待できるのでしょうか?まず発達障害の特性から考えられるタイマーの効果についてお伝えします。
発達障害の特性
タイマーや使い方の前に、なぜタイマーが良いのかということをご説明します。
お子さんの特性に合わせたメリットを先に把握しておくことで、タイマーに必要な要素が分かるからです。
発達障害とは、脳機能の発達がアンバランスで、その凸凹によって社会生活に困難が生じる障害の総称。行動や認知の特性により、主に自閉症スペクトラム障害(ASD)、注意欠陥多動性障害(ADHD)、学習障害(LD)の3つに分類される。
これら3つの特性を単独ではなく、複数持っている人も少なくない。
発達障害の生活上の困りごとの内、下記のようなことは、タイマーを活用すればサポート可能です。
- 突然の予定変更が苦手
- 先の見通しが立たないと不安
- 曖昧な表現では理解できない
- 集中力に波があり、過集中になると途中で活動をやめられない
次から具体的に説明しますね。
先の見通しが持てる|活動をやめられる・始められる
発達障害のお子さんは時間の切り替えが苦手なことが多く、やめるように言ってもやめられなかったり、時には癇癪を起こすかもしれません。
これは、「先の見通しができない、集中力に波があり過集中になることがある」という発達障害の特性が関係しています。
普段、私たちは楽しいことをしていても「あと30分で終わりの時間だ」など時間を把握しながら活動しています。
苦手なことでも「あと10分で休憩だね。頑張ろう」など考え、作業をやり遂げられるかもしれません。
もしも見通しが持てず、楽しい活動を急に終わるように言われると、大人でも不満が残ります。苦手な作業でも、いつになったら終わるのか分からないと、やる気が持続できないことがあります。
同様に、時間を把握していないお子さんが、遊んでいる最中に急にやめさせられると、その活動をやめられず、うまく切り替えることもできません。不満を感じ、パニックになることもあります。
そのため、あらかじめ「お子さんが分かる方法」で、終わりの時間を伝えることが大事です。
先の見通しが持てることで、「活動を終わらせる」「次の活動を始める」ということがスムーズになります。
「お子さんが分かる方法」で伝えることに対しても、タイマーは有効です。
「タイマーの有効な使い方」や「お子さんへの伝え方」についても後述します。
時間管理ができる
発達障害を持っているお子さんは、時間管理や時間の把握が苦手なことが多いようです。
時計が読めない、時間の把握ができない、やるべきことが分からない、など。様々な要因が考えられますが、タイマーを使うことで解決できるかもしれません。
言葉で伝えただけでは時間の感覚が分からないお子さんもいるので、あとどれくらい時間が残っているのか、視覚的に確認できる工夫が必要です。
特に時計が読めないお子さんにとっては、残り時間が視覚的に分かるタイマーが有効です。最近では発達障害を想定したタイマーも市販されています。(後半でご紹介しますね)
タイマーの有効な使い方やタイマーとして使える道具についても、紹介していきます。
▼今回の記事はタイマーだけ紹介しましたが、支援に便利なアプリは他にもあります。
発達障害向けの便利なアプリの紹介記事もありますので、興味のある方はご覧ください。
様々なタイマーの紹介|メリットとデメリット

タイマーアプリもたくさんありますが、ここではその他の物理的なタイマーを紹介します。物理的なタイマーだと小さなうちから使わせやすいですよ。
それぞれにメリット・デメリットがあるので、お子さんの特性に合わせて選択、または場面によって使い分けましょう。
砂時計・オイル時計
メリット
- 時計が読めない、数字が分からないお子さんでも、視覚的に把握できる。
- 「数分」といった短い時間であれば、普通の時計より残り時間を把握しやすい。
デメリット
- きれいな砂やオイルの動きに気を取られ、作業の手が止まることがある。
- 何度もひっくり返して遊ぶことがある。
- アラームなど音で知らせられないため、作業に集中すると忘れてしまう。
キッチンタイマー
メリット
- 数分から数十分まで設定でき、終了時にアラーム音で知らせられる。
- アナログ式のキッチンタイマーは、砂時計と同様に時計が読めなくても視覚的に確認できる。
デメリット
- デジタル式は、数字が読めない、数の概念が分からないお子さんは使えない。
- 聴覚に過敏性などあると、アラーム音を不快に感じることがある。
タイムタイマー
「タイムタイマー」は、発達障害を想定して作られており、残り時間が一目で分かるよう工夫されています。
赤い円盤は残り時間を表しており、赤い円盤が時間経過とともに減っていき、見えなくなると「終わり」の時間です。終わりの時間には小さな音でアラームが鳴ります。
メリット
- 砂時計と同様に、時計が読めなくても視覚的に確認できる。
デメリット
- 他のキッチンタイマーなどと比べると、少し高価。
(サイズにもよるが数千円~六千円ほど)
タイムタイマーを上手に使えば、お子さんとの会話の種が見つかる例をツイートされている方がいました。お子さんに合わせて上手に使ってみてくださいね。
手作りの工夫
時計が読めたり、時計の針の動きが理解できるお子さんであれば、通常の時計に文字や絵を加え「何をどの時間に行うか」示す工夫もできます。
時計にホワイトボードのシールを貼り付け「4時~6時は勉強の時間」などスケジュールを把握できるように工夫している事例がありました。
それに加え、キッチンタイマーで残り時間を示しているようです。
こちらは貼るタイプのホワイトシートです。
ホワイトボードのように、マーカーで繰り返し書いたり消したりできます。
メリット
- タイマーで測れない長時間にも対応できる。
- 1日の流れやスケジュールを大まかに把握できる。
- 実際の時計を使用することで、時計を読む練習になる。
デメリット
- 短時間の活動には向かない。
- アラームはならないので、元々時間に無関心なお子さんには効果が薄い。
(Twitterのように、タイマーとの併用が必要)
タイマーの効果的な使い方

ここでは、タイマーの効果的な使い方をお伝えしますね。
楽しいことから導入する
タイマーを導入する時、「ゲームをやめさせる」など、楽しい時間を切り上げる目的で使い始めると、お子さんが「好きなことをやめさせる道具」だと認識し、タイマー自体を嫌いになることがあります。
まずはタイマーに興味を持ったり、受け入れることを目標にし、タイマーを導入する時は「楽しいこと」から導入しましょう。
あと10分でおやつの時間、テレビの時間、目的地に着く、など。
お子さんが待ち遠しく思う時間をカウントダウンすることから導入してみましょう。
タイマーは、お子さんの行動を管理するためではなく、お子さんの自己管理能力を育てるツールとして使用する視点が大切です。
苦手なことは小分けにする
苦手なことにタイマーを導入する時、「1時間で宿題3ページ」など一気に長い時間の活動を設定すると、見通しが持てず拒否することがあります。
そのような場合は、小分けにしたり、段階的に作業を終わらせるように設定しましょう。
小分けにすることで作業量の見通しができ、小さな「できた」を重ねることで達成感も持てます。
ツイッターでは、宿題を小分けにし、休憩をはさみながらこなすことで宿題を終わらせた例が見つかりました。
お子さんの特性に合わせて是非実践してみてください。
お子さんに分かる方法で予定を伝える
「8時には出かけるから、あと1時間で準備してね」
伝えたつもりでも、お子さんには伝わっていない可能性があります。
- 「準備して」という指示が曖昧で、何をしたら良いか分からない。
- 「8時」「あと1時間」という時間が把握できない。時計が読めない。
- 「聞く」ことが苦手で、理解できない。
など
時間が把握できない場合は、事項でも紹介するタイマーの使用を検討してみましょう。
「聞く」ことが苦手であれば、文字や絵など視覚情報も与えるように工夫するとなおいいですね。発達障害のお子さんへの伝え方は、こちらの記事も参考にしてください。
アプリの利用|自己管理の練習
「準備して」の指示の中には「着替える、歯磨きをする、トイレを済ませる」など複数の活動が含まれています。
そのような場合に効果的なのは「時間毎にやるべきことを声掛けしてもらう」です。
しかし、朝の忙しい時間は難しく、また本人もできるだけ自立に向けて練習していく必要があります。
こちらの「ルーチンタイマー」というアプリは、作業する順番と各作業時間を登録することで、完了まで音声でアナウンスしてくれます。

時間感覚を把握しにくいお子さんに、ルーチンタイマーを利用している方いました。うまく活用すれば生活習慣がうまく変えられるかもしれませんね。
できたことは褒める
発達障害のお子さんは「苦手」も多く、失敗して注意されてばかりだと自己肯定感が低くなり、うつ病や不登校など二次障害へつながる恐れもあります。
生活の中の当たり前のようなことでも、通常よりも努力している場合があります。
時間内に上手に準備ができたね、間に合ったね。
ルールを守ってゲームをやめられたね、宿題を始められたね。
できたことはできるだけ具体的に、その場で褒めましょう。
まとめ
今回は、発達障害の「先の見通し持てない、活動の切り替えができない」という特性に対し、タイマーを使った対処法を紹介しました。
視覚的に残り時間が分かるタイマーを使うことで、残り時間を意識して活動でき、活動の切り替えもスムーズになります。
タイマーは、お子さんを管理するためではなく、「お子さんの自己管理能力を育てるツール」だという視点で用いることが大切です。

児童発達支援と放課後デイサービス 運動・学習療育アップでは発達障害のある児童を対象に、デイサービス事業を提供しています。
お子さんの成長や個性に合わせて様々なプログラムを実施しており、生活の中の苦手や困りごとについても、皆様の相談をお待ちしております。
最後までお読みいただきありがとうございました。