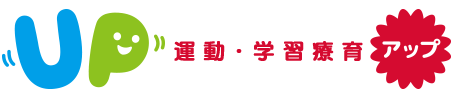皆さんこんにちは!本日も発達障害等に関する学びや情報交換の場所なることを願って投稿させて頂きます。
今日のトピックは「発達障害を抱えた子供のクールダウン方法」についてです。
この記事では、発達障害とパニックの関係。そして、パニックに陥った際のクールダウンについて解説していきます。
目次
パニックとは

急に子供が叫び出したり、泣き叫んだりと、保護者が驚いてしまう行動を取る場面はあるものです。それが外出中や電車の中だとしたら…。
「どうしてこうなるの?」
と悩んでしまう場面もあるでしょう。
パニックとは、不安や恐怖から受けるストレスによって混乱してしまい、人や物に当たる、大声や奇声をあげるなどの行動を意味します。
パニック状態に陥ると、外部から入る様々な情報を正常に処理することが難しくなります。この状態になると声をかけたり、身体を揺さぶってみたりしても応じることができません。
逆に、パニック中に新しい情報を上乗せする結果となってしまいます。つまり、さらにパニック状態を悪化させかねないのです。
具体的に
- 大声、奇声をあげる・泣き叫ぶ
- 人や物に当たる・壁などに頭をぶつけたり、体を叩いたりする
- ボーっとして動かなくなる・呼びかけに応じない
の様な行動をとりがちです。
参考:発達障害-自閉症.net
パニック状態になってしまった。またパニックにならない為に、クールダウンすることが有効と言えます。
クールダウンの有効性

パニックを起こすと、自分自身でも感情をコントロールできません。クールダウン(心身の機能を落ち着かせる)ことで、パニック状態から戻る。またはパニックにならない様に取り組むことが必要です。
誰もがパニックになる可能性がある
パニックを起こす理由は様々です。
- 不快な物を触った・触れられた・食べた
- 不快な音を聞いた
- 嫌なことを思い出した
- 怒られた・注意を受けた
ご覧の様に、誰にでもパニックを起こす可能性はあります。下記の引用にもある通り、年間で11%もの成人がパニックを経験しています。これは発達障害に限ったことではありません。
パニック発作はよくみられる症状で、1年間で少なくとも成人の11%が経験します。ほとんどの人は治療なしでパニック発作から回復しますが、少数の人ではパニック症に進行します。
引用元:MSDマニュアル家庭版/パニック発作とパニック症
私自身も、昔のトラウマを抉られるような音に遭遇したとき、実際にパニックを起こしたことがあります。体が勝手に震え、それまでしていた仕事が全くできなくなり、その後数十分しばらく休みました。
発達障害とパニックの関係
発達障害を抱えている人はパニックに陥りやすいと言われています。
なぜなら混乱したとき、受けているストレスや不快な感情をことばで表現するのが苦手なため、パニックという形になって発露してしまいやすいのです。
下記でパニックについてのツイートを数点ご紹介します。
ご覧の様に、発達障害からの影響でパニックを起こし、悩みを抱えている人は多くいます。
また、発達障害とパニック障害に関する動画がありましたのでご紹介します。良かったら併せてご覧下さい。
クールダウンが必要なケース
普段からパニックに陥らない様に余裕を持って行動することは大切ですが、ここではパニックに陥りやすいパターンをケース毎に紹介していきます。
1.状況が整理できない
発達障害を抱えている子供は、「こだわりが強い」と言う特徴を持っている場合があります。例えば、いつも同じ席や場所じゃ無いと嫌だったり、普段通りの手順で物事が進まないと嫌だったりです。
普段のルーティン以外のことが起きると、状況を整理することが苦手の為、新しい情報が一度に沢山入ってくるので対応しきれなくなってしまいます。これがパニックの素となってしまうのです。
不快さ
パニックを起こす原因の一つに「感覚過敏」の可能性が考えられます。感覚過敏とは、視覚や聴覚、味覚などの五感に、「極端に苦手な感覚があり、生活に支障が生じるほどの症状」のことです。
- 部屋や教室が眩しい(視覚過敏)
- 物音や話し声が煩く感じる(聴覚過敏)
- 特定の味が極端に苦手(味覚過敏)
- 特定の感触、触られるのが苦手・怖い(触覚過敏)
- 特定の匂いが極端に苦手(臭覚過敏)
全てに言えるわけではありませんが、発達障害を抱えている場合、この感覚過敏も併存していることがあります。
過剰すぎる感覚が影響してパニックを起こす場面は決して少なくありません。
要求が満たされない
発達障害は「外見からでは判断が難しい」特徴があります。さらに上で触れた感覚過敏も同様に判断が難しく、周囲からは「変な人」と思われがちです。
自分の要求が通らないと「相手に分かってもらえない」という気持ちから、パニックを起こすことがあります。小さな子供の癇癪のようなパニックです。
このように発達障害によって、パニックになりやすいという一面があります。
発達障害とは
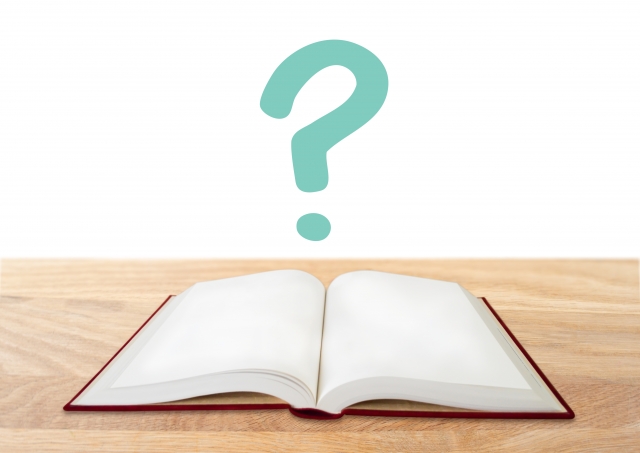
発達障害とは、先天性の脳機能障害が原因と言われています。この影響により成長に極端な差が生まれてしまい、生活に支障が生じてしまう障害の総称です。
発達障害には様々な障害があり、今現在でも発達障害の研究が世界的に行われています。ですが、根本的な治療法についてはまだ解明できていないのが現状です。
主な障害
ここでは発達障害の主な障害3つを解説していきます。
ASD:自閉症スペクトラム障害
アスペルガー症候群なども含まれ、主に「コミュニケーション」に関する障害です。
- 相手の感情を読み解くことが苦手の為、トラブルになりやすい
- 相手の目を見て会話することが苦手
- 強いこだわりがある
ADHD:注意欠陥・多動性障害
注意散漫な為、物事に対して落ち着いて対処できない。ジッとしていられない特徴があります。
- 順番の列に並ぼうとせず、先頭へ割り込む
- 物を無くしたり、忘れ物をしたりの様なミスが多い
- 迷子になりやすい
目に入る様々な情報が気になってしまい、団体行動から逸れてしまう場合もあります。この結果、迷子になりやすく、本人も何故ここに歩いてきたのか分かっていない場合も。
LD:学習障害
言葉の読み書き、簡単な計算や暗算が極端に苦手な障害です。
- 単語は読めても、文章になると急に読めなくなる
- 朗読ができない・苦手
- 字がまっすぐ書けない
定形発達児とは異なり、見えている物、聞こえてくる音などの情報処理が極端に苦手な為、文字が読めないのではなく、正しく見えていない場合があります。
文字が正しく見えていないので読むことも難しいのです。
学校では授業で様々なことを学びますが、障害が影響して学習意欲が低下してしまいがちです。
この学力低下が発端で発達障害を抱えていると分かるケースもあります。
発達障害の症状は、抱えている人によって様々です。ASDのみを抱えている人もいれば、ADHDとLDを併存している人もいます。また、症状の重さによっても変わってきます。
クールダウンの方法・パニックを起こしたら

パニックを起こさない為には、感情のコントロールやパニックにならない為の対策を取ることが重要です。ここでは、クールダウンの方法について解説していきます。
パニックが収まるまで見守る
混乱している状態に対して、「落ち着いて」などの声かけや指示は、さらなる刺激になってしまう場合があります。そのため無理に止めようとするのではなく、安全に見守ることが大切です。
状況や症状の重さによって異なりますが、20分程度でおさまります。刺激の無い時間を確保しましょう。
この「落ち着くための時間」こそが、クールダウンのことなのです。何か特別なことはいりません。必要なのは本人の混乱が収まるまで、待ってあげることです。
クールダウン用の場所を確保
上でも触れている通り、落ち着く為の時間が必要です。この間にさらなる刺激や情報、指示が入るとパニック症状が悪化してしまう場合があります。
自宅などでは「クールダウン部屋」として、パニックを起こした時にクールダウンさせる専用の部屋(スペース)を用意し、その場所でクールダウンさせる方法です。
専用のスペースがあれば問題ありませんが、ご家庭によっては兄弟や姉妹と兼用というご家庭もあります。
下記のツイートをご覧下さい。
「専用の場所が無いなら作ってしまおう」という取り組みで、パニックを起こしやすい子供に一定の効果が期待できます。
また、小学館のサイトHugKumが発信している記事では、ANAグループと成田国際空港株式会社(NAA)が共同で開催した、発達障害を抱えた児童と家族を対象に旅客機の「搭乗体験プログラム」が注目されています。
発達障害を抱えた児童に「飛行機に慣れてもらう取り組み」で、仮にパニックを起こしてしまう状況に陥った際はクールダウン専用スペースも確保してあります。ぜひ参考にご覧下さい。
参考:日本初!ANAグループの「発達障害のある子と家族」の搭乗体験プログラムが素晴らしい理由
クールダウンに対する対策として、「専用のスペースで落ち着く」という方法が有効と言えるでしょう。
下記に、この記事に関するツイートがありましたのでご紹介します。
クールダウンの方法:パニックを起こさない対策

クールダウンと共に、「何故パニックを起こしたのか」を知ることが重要です。状況を確認し、それに対する対策を取ることでパニックの回避に繋がります。
パニックの振り返り
パニックは一見原因が分からないこともありますが、その人が混乱してしまうほどの強いストレスを受けて起きたことは確かです。
落ち着いてから、何が嫌だったのか、不安だったのか聞き取ってあげましょう。そうすることで、パニックの原因を除外し、予防することができます。
パニックを起こす子供は、自分の感情を言葉で表現するのが困難である場合が多いです。この振り返りを行うことで、自分の気持ちを言語化する練習もでき、パニックを減らすことに繋がっていきます。
感覚過敏の対策
感覚過敏が原因でパニックを起こしてしまう場合、この過敏に反応してしまうモノの対策が必要です。
例えば聴覚過敏の場合、イヤーマフなど「音声を遮断するアイテム」があることで一定の効果が期待できます。
聞こえてくる音に過剰に反応してしまう症状です。
・周囲の話し声
・周囲の物音
・自動車や電車、踏切の音
私達が普段から耳にしている何気ない音に不快感を感じてしまうのです。
そこで、外部からの音声を軽減するイヤーマフが注目を集めています。ヘッドホンではありませんので音楽が聴けるわけではありません。ヘッドホンの様な耳栓というイメージです。

3M イヤーマフ JIS適合品 PELTOR ネックバンド式 H6B/V(1コ入)posted with カエレバ楽天市場AmazonYahooショッピング
100%外部の音を遮断することはできません。しかし、不快となる音を軽減することは可能です。上にイヤーマフを紹介していますが、種類は沢山あります。
下記にイヤーマフを取り扱うサイトをご紹介します。参考にご覧下さい。
聴覚過敏保護シンボルマーク
感覚過敏は周囲からでは判断が難しく、当事者本人にしか分からない悩みがあります。
聴覚過敏の対策としてイヤーマフをご紹介しましたが、イヤーマフをヘッドホンと勘違いされてしまう場合も少なくありません。
そこで、周囲に「聴覚過敏の対策をしている」ことを伝えるマークがあります。

上記サイトで無償でダウンロードが可能です。聴覚過敏でお悩みの場合、参考にご覧下さい。
ヘルプマーク

ヘルプマークとは、周囲からでは判断が難しい障害、病気などを抱える人の支援を目的としたマークです。パニックを起こす前に周囲に救いを求めやすく、周囲も気がつきやすくなります。
佐賀県の広報が公開しているヘルプマークの動画がありましたのでご紹介します。
また、ヘルプマークをトピックにした記事を公開しています。よければ併せてご覧下さい。
相談窓口
パニックの対策について相談できる環境も必要です。発達障害やパニックについて、相談できる専門機関があります。
- 子育て支援センター
- 児童発達支援事業所
- 発達障害者支援センター
支援機関は全国に展開していますが、各機関によって支援内容が異なる場合があります。相談前に確認しておきましょう。
子供のパニックについて、保護者の方も不安に思うところが多いでしょう。障害の診断を受けていなくても、少しでも「おや?」と不安に思うことがあれば、気軽に相談してみてください。
SNSの利用
TwitterやInstagramなど、SNSで発達障害に関する情報を発信している人は数多くいます。SNSから情報や、同じ境遇の仲間と知り合えることで「救われた」と感じる人は多く、有効な対策のひとつです。
この記事にも複数のツイートが添付されています。悩みを抱えている人は沢山いるのです。
デイサービスという環境
また、発達障害を抱えた子供を対象に放課後等デイサービスを行なっている事業が複数あります。
専門的な知識を有した職員による療育と同時に、保護者の休息も必要です。
放課後等デイサービス「UP(アップ)ではこのデイサービスを行なっています。デイサービスと言われてもピンとこない人はいるかもしれません。デイサービスに関する記事を用意してありますので、よければご覧下さい。
まとめ
パニックは周囲から「わがまま」「自分勝手」などと思われがちですが、一番苦しんでいるのは本人です。本人はパニックを起こしたことに自己嫌悪に陥りますが、周りの視線が厳しいと、それがもっと酷くなっていきます。
そのためパニックが生じても慌ててどうにかしようとせず、クールダウンを経て本人が落ち着いてから、今回のストレスの要因についてゆっくり話し合うことが大切になってきます。また専門機関にも頼っていきましょう。