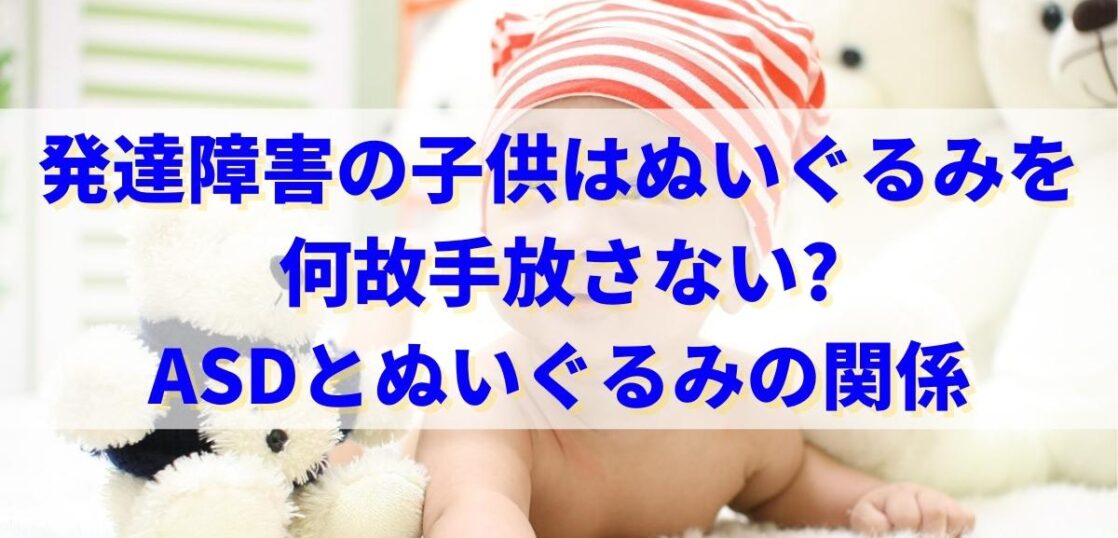皆さんこんにちは!本日も発達障害等に関する学びや情報交換の場所なることを願って投稿させて頂きます。
今日のトピックは「発達障害とぬいぐるみの関係性」についてです。
「ぬいぐるみといると癒される」「ぬいぐるみが好き」という理由で、年齢や性別、病気関係なく肌身離さず持ち歩く人はいます。
一方でぬいぐるみを肌身離さず持ち歩く行為が理解できず不安になる方もいるのです。
今回は発達障害とぬいぐるみの関係性に注目し、ぬいぐるみへ依存する理由をメインに取り上げています。
ぬいぐるみとの適切な関係を作り、子供たちの笑顔を増やすきっかけになれば幸いです。
目次
発達障害とぬいぐるみの関係

定型発達の子供に比べ発達障害を抱える子供は、さまざまな不安や悩みを抱えています。
ぬいぐるみは不安や悩みを和らげ安心させてくれる存在なので、発達障害の子供は肌身離さず持ち歩く場合があります。
定型発達児童:概ね発達障害ではない児童を示します。
ぬいぐるみの役割は期間限定の処方箋
赤ん坊からハイハイの時期に移行すると、不安な時は泣いてわめくだけではなく、ぬいぐるみを使い始める傾向にあります。
ぬいぐるみに依存することで不安を解消しようと試みるのです。
1歳、3歳と歳を重ねるごとに次第に対人対処法を身に付けていくので、ぬいぐるみへの関心度は減っていくのが一般的と言われています。
発達障害の子供から見たぬいぐるみの役割
対する発達障害の子たちが抱く、ぬいぐるみの役割とはいったい何なのでしょうか?
感情を表に出す、問いかけに答える、言葉を交わすなどといった、対人コミュニケーションを、ぬいぐるみは取りません。
発達障害の子供がぬいぐるみに話しかけることにより、ぬいぐるみは悩みを打ち明けたり、嬉しかったことを報告できる「話し相手」に変わるのです。
「話し相手」であるぬいぐるみは、発達障害を抱える子供に反論も叱る行動もせず、全てを受け入れてくれます。
ぬいぐるみが必要になる理由

発達障害を抱えた子供にとって、ぬいぐるみが必要になる理由はさまざまです。
本項では、症状ごとに理由を探っていきます。
自閉症スペクトラム障害(ASD)の場合
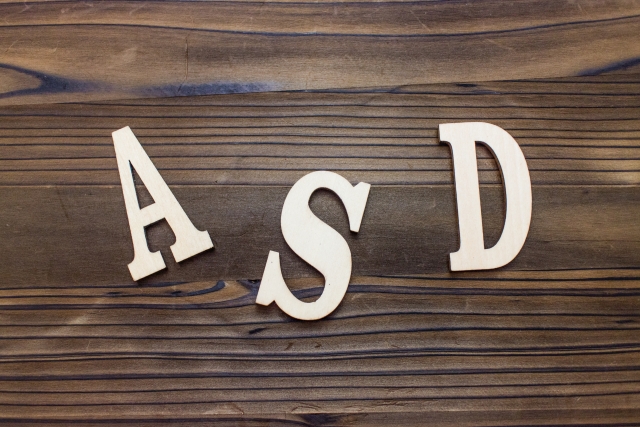
ASD(Autism Spectrum Disorde)とは、自閉症スペクトラム障害やアスペルガー症候群など、「コミュニケーションに関する障害」が多く、発達障害の一つです。
ASDの主な特徴は以下の通りです。
- 空気を読んだ発言が苦手
- 相手の感情を読み解くことが苦手
- 相手の目を見ることが苦手
- 好みの事以外に関心を持たない
- 強いこだわりがあるなど
ASDの影響により、コミュニケーション面において、様々な問題が現れます。
ASDの子供は、本人にその気は無くても、話し相手を傷つけてしまったり、喧嘩の原因になったりしかねません。
結果的に周囲とのコミュニケーションが取れず、ASDの子供は一人で遊ぶ傾向にあります。
一度「変わった子」「話すのが難しい子」というイメージを持たれてしまうと、周囲との溝は深まり、人は近寄らなくなります。
本人が「あれ?」と思った時には遅い場合もあり、「どうしてこうなってしまうんだろう…」と悩み続ける人は少なくありません。
その悩みの相談相手こそ、ぬいぐるみとなります。
答えが返ってくるわけではありませんが、話を聞いてくれる「相手が居る」という安心感が得られるのです。
ASDはぬいぐるみ好き?【自閉症スペクトラム障害・アスペルガー症候群】
発達障害系YouTuberである光武オーナーさんによるASD視点から見たぬいぐるみについての持論を発信されています。
動画内では彼自身もぬいぐるみが好きと発言しており、夏でも素材が気持ちいい毛布を好んで使用しているので、こだわりをもっている様子が分かります。
自閉症スペクトラム障害やアスペルガー症候群など、「コミュニケーションに関する障害」が多い特徴があり、発達障害のひとつです。
発達障害とは、先天性の脳機能障害が原因と言われており、生活に支障が生じてしまう障害の総称を言います。
触覚過敏の場合

発達障害を抱えている人は、感覚過敏を併存している場合が多くあります。
感覚過敏とは、視覚、聴覚、味覚など人間にある五感のうち、生活に支障が生じるほど過剰に反応してしまう感覚がある症状を言います。
感覚過敏の主な特徴は以下の通りです。
- 部屋の照明が眩しい
- 特定の音に刺された様な痛みを伴う
- 特定の物に触れた感触が苦手など
感覚過敏の一つである触覚過敏は「触れた物に対して過剰に反応する感覚」です。
特徴は好きな感触の物にこだわりを持っていることです。
例えばタオル生地の感触が好きな子供は、タオルを手放そうとしません。
ぬいぐるみは、ふわふわと柔らかく、触り心地の良い生地で出来ている商品が多くあります。
ぬいぐるみに触れられている感覚が心地良い為、手放そうとしない可能性もあるでしょう。
発達障害と感覚過敏
発達障害と感覚過敏を併存している場合、両方の影響からぬいぐるみに依存している可能性が高いでしょう。
- 普段着る洋服の素材
- ぬいぐるみの素材
- 布団やベッドの素材
以上のように素材に対するこだわりがあるため、保護者にとっては様々な場面で「強いこだわり」と「苦手な感触」に悩まされることになります。
コミュニケーションという場面だけで無く、生活面でも不安材料が増えていきます。
周囲の向き合い方

ぬいぐるみから離れようとしない子供や、中学へ進級してもぬいぐるみと一緒に寝る人、さらには成人でも「ぬいぐるみがないと落ち着かない!」と主張する人はいます。
ぬいぐるみに対して確固たるこだわりを持つ人に対し、保護者の中には本人の年齢や生活面の影響を考慮し「ぬいぐるみの持ち歩きをやめさせたい」と望む人もいます。
保護者とぬいぐるみを手放したくない当事者の意見がかみ合わない場合、保護者が取るべき行動はなんでしょうか?
結論から言うと、本人や周囲の環境に危険が伴わないのであれば、ぬいぐるみをとりあげる必要はありません。
ぬいぐるみは本音を引き出すために必要不可欠
発達障害を抱えている子供にとって、ぬいぐるみは良き理解者になり得ます。
保護者の方が、ぬいぐるみを抱きかかえている状態で子供の言葉に耳を傾けてみると、本音を語ってくれる場合があります。
また、子供からぬいぐるみを使って遊んで欲しいと要求される場合もあるでしょう。
子供の本音を知ることで、解決に結び付く結果になる場合は十分あります。
子供の素直な意見が聞ける時間とも言えますので、保護者側は、要求に応えられる「環境作り」を目指しましょう。
ぬいぐるみに関するルールを設ける
自宅以外でぬいぐるみを持ち歩けない場合、発達障害を抱える子供はどうしたらいいでしょうか?
例えば学校のように自宅と同じ環境ではないのなら、「授業中だけ別の場所に保管」もしくは「先生に預かってもらう」など、独自のルールを設けてみるといいでしょう。
独自のルールを設けることにより、ぬいぐるみと一定期間距離を離す環境を作り、慣れさせるのです。
勿論、不安になって泣き出してしまうかもしれません。
強引に取り上げることはトラウマにもなりかねず、外出や通園、通学を拒否してしまう場合も考えられるため、先生や周囲の人との協力は必要不可欠です。
ぬいぐるみと一定期間距離を離す環境作りが難しい場合、ぬいぐるみと同じ素材でできているアイテム(ハンドタオルやハンカチなど)を代用すると落ち着く場合があります。
それでも子供にとって不安な状態であることには変わらないため、ぬいぐるみから卒業できたと確信できるまでは、緊急用としてぬいぐるみを準備しておくのが無難です。
持ち歩き可能なぬいぐるみを用意する
外出時専用の小さなぬいぐるみを用意し、キーホルダーの様に鞄へ取り付けておきしょう。
別室で預かるよりも身近に置いておけるので「いつでもそばにいる」と安心感が持てます。
可能であれば普段から持ち歩いているぬいぐるみと同じ素材のものを選択したいところです。
ただし持ち歩く場合は2点注意点があります。
1つ目は普段から持ち歩いているぬいぐるみの素材と同じ素材にした方がいい点です。
いくらキーホルダーのように手軽に持ち歩けたとしても、本人が好きではないと効果は期待できないからです。
2点目はチェックを怠らない点です。
持ち歩いていると何らかの拍子に落とす場合があるので、留め具の状態を確認し壊れていないかチェックしましょう。
キーホルダーぬいぐるみ
キーホルダーになっているぬいぐるみの一例をご紹介します。
たとえば「となりのトトロ ふんわりキーホルダー」は、ご存じの方も多いジブリ作品のマスコットキャラです。
「シュタイフ Steiff フィン テディベア」は少しお値段はいきますが、くまのぬいぐるみは定番ですね。
どちらもふんわり感があるので、ふんわり感が好きなお子様におすすめです。
ささいな行為でも達成できたことを褒める
環境を整えたとしても、ぬいぐるみを手放さなければいけない場面は出てきます。
不安になって泣いてしまう子供はいるかもしれません。
そんな時、保護者は「泣くんじゃないの!」と責め立てず褒めることが大切です。
「別のアイテムで代用できた」「少しの間でもぬいぐるみと離れた」など、些細なことでも構いませんので、出来たことを褒めましょう。
褒めると自身が湧き、未来に対して自信を持てるのです。
まとめ
ぬいぐるみを持ち歩く行為は、発達障害を抱える子供だけではなく成人にもいます。
変わらぬ味方であるぬいぐるみは、不安解消のために必要不可欠です。
「周囲の視線が恥ずかしい」などの理由で強引に取り上げてしまうと、トラウマなどになりかねません。
保護者や周囲の方は、ぬいぐるみの存在を理解し、不安を解消するために環境作りに力を入れてみてはいかがでしょうか。
そうすれば、子供の不安が解消するきっかけにつながることでしょう。