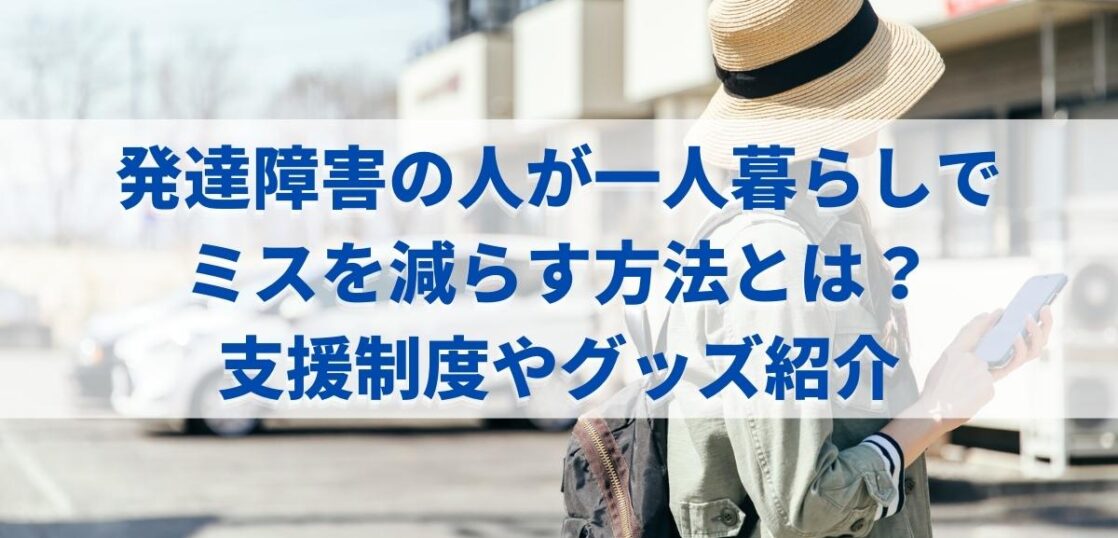皆さんこんにちは!本日も発達障害等に関する学びや情報交換の場所なることを願って投稿させて頂きます。
今日のトピックは「発達障害の一人暮らし」についてです。
発達障害の人でも自立を目指したり、家庭の事情で実家を離れたりしたい人はいます。
そこで今回は、発達障害の人が一人暮らしにおいてミスを減らす方法をお伝えするだけではなく、支援制度や便利なグッズも紹介するので、是非参考にしてみてください。
目次
発達障害の人が一人暮らしでミスを減らす方法
発達障害の人が一人暮らしでミスを減らす方法としてあらゆる面で前倒しの準備が必要です。本項では生活面、健康面、金銭面の3点をピックアップしました。
生活面でミスを減らす
発達障害の人は、特性の影響でさまざまな面において忘れ物をしやすい傾向があります。例えば鍵をどこに置いたのか忘れたり、ゴミを出し忘れたりなどはよく聞きますね。
大切なものを失くさないためには、あらかじめ保管する場所を確定します。特に鍵など大切なものはスマートタグをつけて見つけやすくしておく工夫をしましょう。

ゴミ出しの日を忘れないためにはカレンダーやホワイトボードに予定を書き込むなど視覚的に分かりやすくするといいでしょう。
部屋のスペースが足りない場合は、アプリでゴミ出しの日を管理するのも手です。下記画像は、投稿者が試しに「ごみの日アプリ」を利用してみました。

ごみの日アプリを使用することで、指定した時間に通知をしてくれるので忘れにくくなりました。
健康面でミスを減らす
発達障害の人は興味のあることに過集中しやすいため、気づかぬうちに体調を崩しがちです。よって少ない集中力でしなければならないことをやり切れるよう、過集中できる時に一気に前準備をしてしまいましょう。
例えばゲーム機やスマートフォンで長時間遊ぶ場合は、アラームを使って制限時間を設けます。リラックスできる定位置からいつでも時間が確認できるよう、掛け時計を置けばより効果が出るかもしれません。
薬を処方されている場合は毎日同じタイミングで飲むのは分かり切っているので、処方された薬を小分けにして見ただけで飲む量が分かるようにしていると、飲み忘れを防げます。

金銭面でミスを減らす
衝動買いをする人は健常者にもいますが、発達障害の人は生活費まで削る人が少なくありません。
「生活費にいくら必要なのか」「優先順位はなにか」など、お金の入出状況を把握していないことが原因なので、お金の流れを可視化するといいでしょう。
例えば壁掛けのクリアポケットへジャンルごとにレシートを分けたり、銀行のカードやクレジットカードを一元管理できる家計簿アプリを利用すると、何を無駄に使ったのかが判明します。

支援制度や便利グッズ、サービスの紹介

発達障害の方の一人暮らしを支援する制度や工夫、便利なグッズはたくさんあるので、一部を紹介します。
- 困難を少しでも軽減するための工夫
- 便利グッズ
- アプリの活用
- 公的機関の支援制度や支援施設の活用
1.困難を少しでも軽減するための工夫
ルール(決まりごと)を作る
一人暮らしにおける困難を少しでも軽減、回避できるための工夫として自分だけのオリジナルのルールを作りましょう。
ご自分の性格や特性を把握した上で、自分にあったルールを作ることが大切です。
【ルール一例】
- 財布や鍵など大切なものは、置く場所を決めておく。
- ゲームやスマホなどに集中しすぎる時は、時間を決めておく。時間になったら電源が切れる設定にしておくことやそのように促す環境にする。
- ゲームの課金は絶対にしない。もしくは1ヶ月に3,000円まで。
- 1週間のうち、月曜日と水曜日は21時に必ず寝る。
- 外出時には、火の元確認、戸締り、持ち物チェックする。
2.便利グッズ
キーファインダー
どこに置いたかわからなくなっても、あらかじめ大事なものにつけておけば親機のボタンを押すだけでその番号の子機が鳴って置き場所を教えてくれます。
外出前になって、「鍵がない」「財布どこ置いたっけ?」となる方はきっと、よき相棒になってくれるはずです!
| 商品名 | キーファインダー |
| 価格(楽天市場最安値) | 2,480円(税込、投稿時の価格) |
| 素材 | ABS |
| 寸法 | コントローラ:約105×46×13mm 受信機:約50×36×9mm |
| 色 | ブラック |
壁掛けポケット
レシートをジャンルごとに区分けするの便利です。レシート以外にも使い道はありますので、いろいろ試してみましょう。
| 商品名 | ウォールポケット マチ付 |
| 価格(楽天市場最安値) | 1,605円(税込、投稿時の価格) |
| 素材 | 透明PVC |
| 寸法 | 1ポケット:14cm×14cm 全体:30cm×57.5cm |
| 色 | クリアー |
3.アプリの活用
睡眠サイクルアラームLite
無料で使える睡眠時間の記録管理アプリです。睡眠時間と起床時間の入力で毎日の睡眠時間を見直しましょう。
記録したデータは自動でグラフ化してくれるので、自身の睡眠傾向を簡単に確認できます。
なお「睡眠サイクルアラーム」は有料アプリです。睡眠時間の傾向を確認するだけならLiteで十分です。
ごみの日アラーム
ごみの日を忘れないように通知してくれるシンプルなアプリで、電気や電池など隔週や2ヶ月に1度などの変則的な設定が可能です。
通知設定で前日と当日の2回通知してくれるのでうっかり出し忘れが激減します。
MoneyForward(家計簿アプリ)
手持ちのカードや携帯料金を登録すれば、お金の流れを確認できるアプリです。すべての機能を使うには有料会員になる必要がありますが、お金を一元管理をするには手っ取り早いアプリです。
紙で管理したくない人におすすめします。
あさとけい
心地よい12種類のサウンドで起こしてくれる目覚ましアプリで、スマホに入っているお好きな曲に設定も可能です。
お出かけ時刻を設定すれば、残り時間を音声で通知するほか、登録地域の天気予報を閲覧できます。
多機能な分、使いこなすまでは時間がかかりますが便利なアプリです。
4.公的機関の支援制度や支援施設の活用
高校や大学の進学、就職を機に一人暮らしを検討されている方へ朗報です。
発達障害の方への支援が手厚い学校がありますので、是非検討してみてください。
発達障害を抱える大学生でも安心して大学生活が送れるよう、大切な事項をまとめている記事があるので参考にしてみてください。
発達障害を抱える人でも安心できる高校の種類や、サポート内容についてまとめている記事もあります。
支援施設の活用
発達障害者支援センター
発達障害者支援センターは、発達障害児(者)への支援を総合的に行うことを目的とした専門的機関です。
都道府県・指定都市自ら、または、都道府県知事等が指定した社会福祉法人、特定非営利活動法人等が運営しています。
障害者就業・生活支援センター
障害者就業・生活支援センターは、障害者の職業生活における自立を目的として設置されているセンターです。
雇用、保健、福祉、教育等の関係機関との連携の下、障害者の身近な地域において就業面及び生活面における一体的な支援を行い、障害者の雇用の促進及び安定を図る
引用:厚生労働省
障害者就業・生活支援センターは全国各地に設置されているので、包括的な支援が期待できます。
お近くのセンターをチェックしてみてくださいね。
参考元:厚生労働省|令和3年度障害者就業・生活支援センター一覧
公的機関の支援制度・補助制度
日常生活自立支援事業
成年後見制度の一環で福祉サービスの利用や金銭管理の援助を行う、日常生活自立支援事業というものもあります。
窓口は市区町村の社会福祉協議会、対象者は「障害(発達障害を含む)のために判断能力が不十分である者」です。
実施主体が定める利用料を利用者が負担しますが、生活保護受給世帯の利用は無料です。
参考元:厚生労働省|日常生活自立支援事業
障害年金
障害年金とは、病気やけがによって生活や仕事などが制限されるようになった場合に、現役世代の方も含めて受け取れる年金です。
「障害基礎年金」「障害厚生年金」があり、病気やけがで初めて医師または歯科医師の診療を受けたときに「国民年金」に加入していた場合は「障害基礎年金」、厚生年金に加入していた場合は「障害厚生年金」が請求できます。
【病気やけがで診察を受けた際、請求できる年金】
- 国民年金に加入している場合:「障害基礎年金」
- 厚生年金に加入している場合:「障害厚生年金」
また、請求する年金がどちらかにより窓口や認定条件も変わります。下記Tweetも参考にしてくださいね。
参考元:日本年金機構
生活保護
生活保護は、収入や資産、能力などの活用をしても生活に困窮する人が対象となる国の補助制度です。
障害者手帳を持っている人は、生活保護制度に合わせて障害者加算が受けられる場合もあります。
申請方法などの不明点は、ソーシャルワーカーに相談に乗ってもらうケースが多く、場合によってはかかりつけの病院の医師も相談に乗ってくれるケースもあります。
申請場所は、居住エリアの福祉事務所もしくは市区町村の担当窓口です。
参考元:厚生労働省|全国の福祉事務所一覧
社会福祉の立場から患者さんやその家族の方々の抱える経済的・心理的・社会的問題の解決、調整を援助し、社会復帰の促進を図ります。
居宅介護(ホームヘルパー)の利用
食事のための買い物、調理や掃除などの生活困難がある場合は、障害福祉サービスの居宅介護を受けられる可能性があります。
サービス内容としては、入浴・排せつ・食事等の身体介護、調理・洗濯・掃除生活必需品の買い物など家事援助のほか、生活等に関する相談や助言、その他生活全般にわたる援助があります。
ホームヘルパーが、自宅を訪問して、入浴、排せつ、食事等の介護、調理、洗濯、掃除等の家事、生活等に関する相談や助言など、生活全般にわたる援助を行います。
対象者は、障害支援区分が区分1以上(児童の場合はこれに相当する心身の状態)である方
利用料:18歳以上の場合は利用者とその配偶者の所得、18歳未満の場合は児童を監護する保護者の属する世帯(住民基本台帳上の世帯)の所得に応じた自己負担の上限月額があります。
ただし、上限月額よりもサービスに係る費用の1割の金額の方が低い場合には、その金額を支払います。
引用元:WAM独立行政法人福祉医療機構
発達障害を抱える人でも一人暮らしをした方がいい理由

発達障害を抱える人でも望むのであれば、一人暮らしはしたほうがいいでしょう。
発達障害を抱えていたとしても、一人暮らしを継続していけば、デメリットよりもメリットが増えるからです。
一人暮らしのメリット
- 自分の自由な時間が増える
- 同居人との衝突が減る
- 自分を見つめ直し自己投資できる
メリットの一つとして、一人暮らしをすれば自分の時間が増えます。
不要な人間関係から解放され、自分へ向ける時間が増えることで、時間を自分への投資に使えるのです。
自分への投資は自信がつくだけでなく未来につながりますので、他人を比べて精神を病む暇がありません。
以上のように、一人暮らしはメンタルの面でプラスになります。
一人暮らしのデメリット
- 段取りや準備が必要な作業が必須
- 金銭感覚が鈍いと浪費しがち
- 清潔感を保つために清掃が必要
一人暮らしのデメリットは「身の回りのすることが増えてしまう」です。
炊事洗濯は勿論、部屋の掃除、生活費や公共料金の管理など、自分自身で行う必要があるからです。
発達障害を抱える人が苦労する部分は現実的な部分が多い傾向ですが、自己解決できれば自信につながります。
身の回りのことをできるようになれば、デメリットがメリットに転ずるのです。
一人暮らしをする場所選びのポイント
勤務先や学校の近くに引越しすれば、通勤・通学時による不快さを軽減できる可能性があります。
発達障害を抱えている人は、感覚過敏を併存しているため、外の明るさや周囲の音などに不快を感じやすく、通勤・通学するだけで疲れてしまいがちです。
お部屋を選ぶ際は確認を怠らなければ、ハズレ物件に住む確率が減ります。
- 平日だけではなく休日、時間帯は日中と夜間に物件を確認
- お気に入りの物件へたどり着くまでの間に避けたいポイントを確認
例えば平日の昼間は静かでも、休日の夜間に近隣がうるさい場合は回避できますし、お目当ての物件へ行くまでに回避したいポイントがあるなら、回避できる道がないか事前にチェックしましょう。
分からない点を一つずつ確認をすることで安心感が生まれ、いっときの感情で物件選びをしなくて済みます。
視覚や聴覚など人間にある五巻に「生活に支障が生じるほど不快に感じる感覚」がある状態を言います。
・照明が眩しすぎて目を開けられない
・周囲の会話が煩く聞こえてしまう・苦手な音があるなど
発達障害を抱えた子供に焦点を当て、片付けを改善するメカニズムを記事にしています。参考にしてみてくださいね。
一人暮らしができないと陥る罠とは?

一人暮らしをすることにより苦労は増えるものの、メリットもあることは分かりました。
しかし「一人暮らしは必要ないなあ」と感じる方はいらっしゃるかもしれません。
そこで本章では、一人暮らしをしないといずれ襲い掛かってくる隠れた罠についてお伝えします。
親や家族はいつまでも一緒ではない
寿命や体の不調により、親や家族は永遠に支え続けることはできません。
いざ親や家族の死をきっかけに一人暮らしをせざる得ない状況になると、今まで自分でやらずに頼って生活していた分だけ負担が大きくかかってしまいます。
慣れないことや知らないこと、覚えないといけないことなど、一気に降りかかってしまうのですから。
障害を抱えている人の受け入れ施設が少ない
発達障害を抱える未成年者の場合や養ってくれている親や家族が元気なうちはあまり問題になりません。
しかし、いざ養ってくれる人がいなくなってしまうと、業者や施設を頼ることになります。
現在の日本の障害者福祉入所施設は、数が少ないために入所したくても入所できない(飽和状態)現状がある他、入所するための条件を把握するのに手間がかかることもあります。
自分のことを支援者に任せっきりで、どうすればいいのかわからない場合、障害を抱えた本人は路頭に迷う可能性があります。
成人の発達障害者やその家族に支援を提供する全国の専門機関では、生活面に関する相談の頻度が多いものの、生活スキルに関する支援・指導を行っている施設は少なく、十分な人材・スタッフ育成もなされていないのが現状であることが分かりました。
引用元:発達障害情報・支援センター
●障害を持つ18歳未満の入所条件
対象者は、福祉型障害児入所施設については、知的障害児(自閉症を含む)、盲ろうあ児、肢体不自由のある児童、医療型障害児入所施設については、自閉症児、肢体不自由のある児童、重症心身障害児、情緒障害児短期治療施設については、心理(情緒)的、環境的に不適応を示している等の児童であって、施設への入所(宿泊)・通所を適当と児童相談所が認めた者です。
引用元:発達障害情報・支援センター
●障害を持つ18歳以上の入所条件
対象者は、発達障害を含む障害者で、市町村が障害者の福祉サービスの必要性等の調査を行った上で支給決定した者です。
引用元:発達障害情報・支援センター
よって頼れる人がいるうちに、一人暮らしを早くからスタートさせ、1人でも生活できるスキルを身につけることが大切なのです。
まとめ
今回は発達障害の方でも一人暮らしができるためのポイントを解説しました。おさらいをしましょう。
- 一人暮らしは自分自身のための時間や人間関係をコントロールできる
- 家事や申請処理など現実的な問題を自力で解決しなければならない
- 快適な生活を送るためにグッズやアプリを利用する
- 自助でどうにもならない場合は公助利用を検討する
残念ながら、支援者はいつまでもそばにいるわけではありません。
切羽詰まってから一人暮らしにならないように、周囲や公的サービスを併用しながら、事前に準備を進めておきたいですね。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。