皆さんこんにちは!本日も発達障害等に関する学びや情報交換の場になることを願って投稿させて頂きます。今日のトピックは「子育て共働き」についてです。
家事や育児をしながら働く女性には、保育園の問題や復職のことなど、さまざまな悩みがつきものです。病気や障害を持つ子どもの親の就労にはまだ様々な壁があるような気がします。
目次
発達障害の子育て共働きは健常児を持つ親の7分の1

専業主婦世帯と共働き世帯の割合を調べてみると、7割近くの夫婦が共働きしていることが分かります。
独立行政法人労働政策研究・研修機構の統計情報から過去20年間の数字を抜粋いたしました。
| 調査年 | 専業主婦世帯 | 共働き世帯 | 共働き世帯比率 |
|---|---|---|---|
| 2001 | 890 万世帯 | 951 万世帯 | 52% |
| 2006 | 854 万世帯 | 977 万世帯 | 53% |
| 2011 | 773 万世帯 | 987 万世帯 | 56% |
| 2016 | 668 万世帯 | 1,136 万世帯 | 63% |
| 2021 | 566 万世帯 | 1,247 万世帯 | 69% |
図12 専業主婦世帯と共働き世帯
参考:行政法人労働政策研究・研修機構
発達障害児の子がいる家庭の共働き世帯は少ない
障害児を持つ母親のフルタイム勤務は、なんと! わずか5%。健常児を持つ親の7分の1という結果をみつけました。
障害児の母の95%は安定した就労ができていない
引用:日経xwoman
共働きの悩みは子供との時間が足りない

共働きをするうえで、一番のデメリットは子供にかける時間がすくないというところにあるようです。
- 子供と会話時間が少ない
- 平日の学校行事の参加が難しい
- 送迎の関係で習い事を制限している
- 宿題チェックができない
- 子供の交友関係を知る機会が少ない
通勤時間を含めると一日7~9時間は会社に拘束されますので必然的に、子供と過ごす時間が少なくなってしまうのは仕方がありませんね。
ほかにもこのような悩みがあげられあるでしょう。
- 病気時の預け先がない
学校行事や、こどもが病気になった時いつでも簡単に休暇を取得できるように、働くお父さん・お母さんたちは常に業務を調整したり、上司や同僚との関係も良好にしたりと日々の頑張りが想像できます。
共働きはお金に余裕ができ子育てのメリットが多くなる

共働きの最大のメリットはお金に余裕ができることです。
- 世帯収入増える
- 年金が増える
- 子どもの自立
- 子どもの教育費貯金ができる
お金に余裕ができることによりケチらずお出かけできます。
育児にはお金がかかります。そして発達障害児の育児には、もっともっとお金がかかります。共働きを維持できればお金による将来の心配、ストレスはありませんね。
障害児の教育現場は多様な学び場が確立されてる
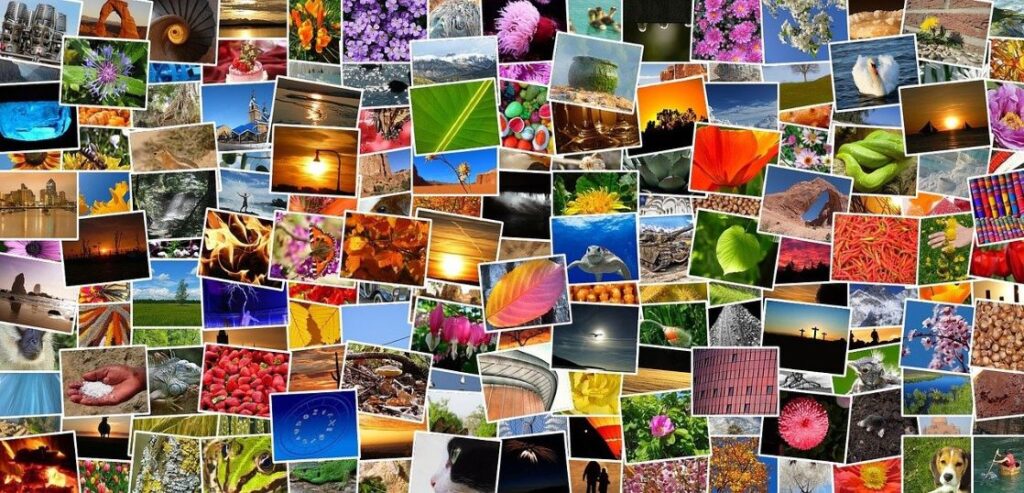
それでは出社している間の子供たちが過ごす環境を見てみましょう。保育園・幼稚園、小学校の取り組みについて調べてみました。
幼稚園は工夫して対応してくれます
発達障害は、人から見えにくく、わかりにくいために、気づいてもらうことが難しいと言われています。入園前の面談で断られた、入園後退園をすすめられたなどネガなお話も聞きます。
しかし!!工夫する幼稚園や保育園が増えています。
発達障害のある子のために、さまざまな工夫を行う幼稚園や保育園が増えています。
引用:NHK福祉情報サイト ハートネット
耳で聞かせるより目から情報を与えるなど、なるほどです。
幼児期の場合は、障害の特性がどのように表れてくるのか、を観察しながら、両親と先生でタックを組んで対応法を探っていこう、という形ができるのが理想ですね。
小学校には特性に応じて学習する仕組みができてました
- 特別支援学校に通う
- 小学校に通い、特別支援学級に在籍するか、通級による指導をうける
特別支援学級と通級の違い
特別支援学級とは、1クラスの児童生徒は8人という基準で編成され、少人数で活動する学級です。
それに対して通級とは、通常のクラスに在籍し、学習のほとんどはみんなと参加。障害に応じて特別な指導を受けます。1人に1人の支援員が隣に付いてサポートしながらクラスのみんなと学習しているようです。
2.特別支援教育の現状
障害のある子供の自立と社会参加を見据え、一人一人の教育的ニーズに最も的確に応える指導を提供できるよう、通常の学級、通級による指導、特別支援学級、特別支援学校といった、連続性のある多様な学びの場の整備を行っています。
引用:文部科学省
国も障害のある子どもの教育の充実を図ろうとしてます。
共働きを成功させるカギは周りの協力

このように幼稚園も小学校も特別支援教育という多様な学びの場が確立されつつあります。それでも発達障害児のいる家庭のお母さんは、働きづらいのでしょうか。
明るい共働き家庭をつくる為のポイントを考えてみました。
- パートナーの帰りがある程度きまっている
- 職場の理解が得られている
- 両親や友達など近くに頼れる人がいる、またはサポートセンターなど利用できる
周囲の協力を得れば、お仕事も子育てにも目標を持って輝いている方もいます。
なんといっても周りの協力を仰ぎましょう。地域のサポートもできるものは利用しましょう。
行政のサービスを受けるには「障害児通所支援受給者証」が必要
児童発達支援事業所や放課後等デイサービスに通うためには、基本的には、「障害児通所支援受給者証」が必要です。障害と言い切れるか微妙な(「グレーゾーン」や「ボーダーライン」)子も、早期に適切な療育を開始することによって、将来が大きく変わる可能性がありますので、受給者証の交付を受けることをお勧めします。
こちらの記事にあるように、放課後等デイサービスでは、障がいを持つ子どもたちへの療育行っています。
またアップでは放課後等デイサービスを行っております。放課後等デイサービスでは他であまり例を見ない取り組みプログラミング教室も開設しております。

地域で利用できる行政サービスや、児童福祉施設の情報はお住いの地区のHPに載ってますが、LITALICOりたりこ発達ナビからも発達支援施設を探すこともできます。
子育てと仕事に迷ったら親がイキイキできる方法を探す
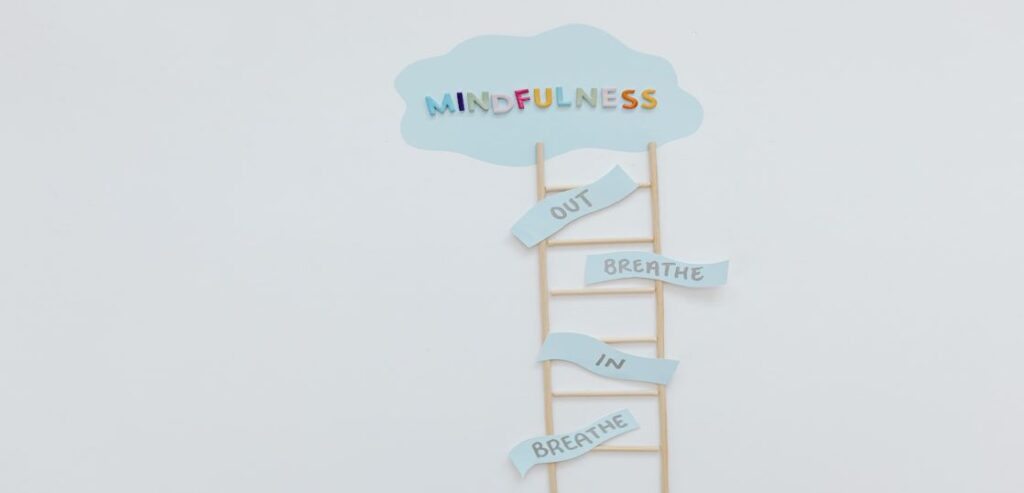
療育先と周りの協力を確保できても、お仕事を辞めてしまうこともあります。
お仕事を辞めて後悔
金銭面への不安はもちろんですが、こんな意見が気になりました。
- 充実感が感じられなくなった
- こどものマイナス面が特に目に入るようになった
- 家庭療育で頭の中がいっぱいになってしまった
お仕事を辞めてよかった
- 時間と心に余裕が持てた。
- 療育センターに通う時間が増えた。
時間と心に余裕が持てて理想していた家庭療育ができるのかもしれませんね。
「療育センター」は臨床心理士など専門家がいて相談に乗ってくれます。お父さんお母さんが安心して、自分たちの考えを確信しながら、家庭療育に取り組んでいけるように支援してくれます。親同士の交流の場もあります。
まとめ
教育と福祉との連携を推進が図られ、保護の支援を推進するための方策も取れていることわかりました。発達障害児の家庭も安心して共働きできるような社会になると期待できそうです。
- 工夫する幼稚園や保育園が増えている
- 小学校には特別支援教育という学びの場が確立されている
- 放課後等デイサービスに通い早期に適切な療育を開始できる
共働きを続けるうえでデメリットがいくつもある一方で、共働きを辞めて後悔されるパターンもあることが分かりました。
共働きをする家庭もそうでない家庭も、ストレスを少なくする工夫がみつかると良いですね。ノンストレスで子供の心を成長させてあげたいものです。
最後まで読んでいただきありがとうございました。

