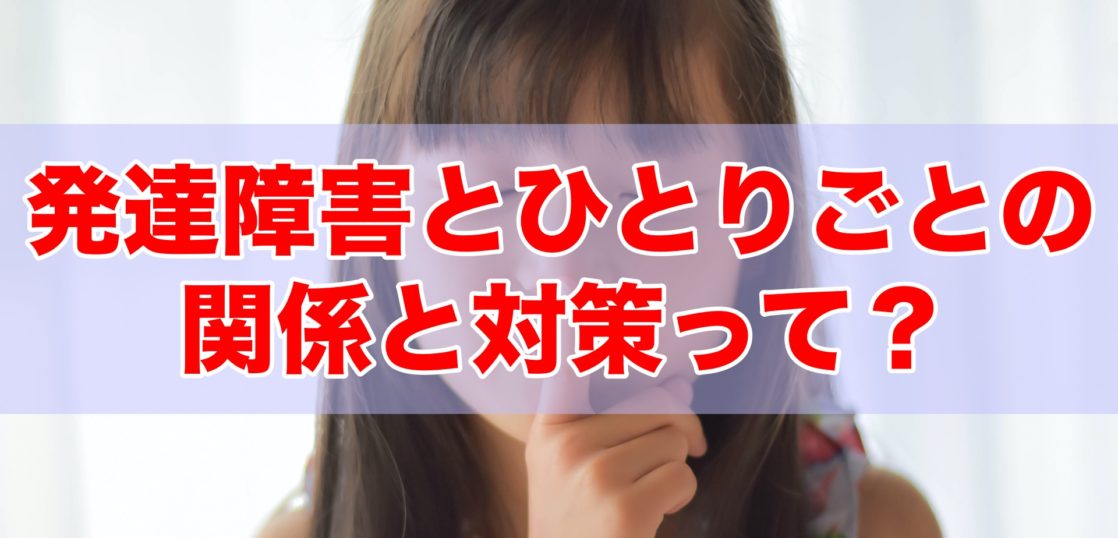皆さんこんにちは!本日も発達障害等に関する学びや情報交換の場所なることを願って投稿させて頂きます。今日のトピックは「発達障害とひとりごと」についてです。
ひとりごとは誰でも言った経験があると思いますが、発達障害の影響でひとりごとが強まる場合があります。
「うちの子、ひとりごとが多い気がする…」「もしかして、何かの障害?」と不安に感じてしまう保護者は少なくありません。
この記事では、発達障害とひとりごとの関係性、その特徴や違いについて解説していきます。
目次
ひとりごとが多い=発達障害とは限らない

私達は、日常生活から何気なくひとりごとを言っています。
「これを…こうして…」と言いながら作業したり
「あ〜、またやっちゃった…」と反省したり
無意識にひとりごとを言ってしまう時は誰にでもあるでしょう。ですが、ひとりごとを言ってはダメなシチュエーションの際には、ひとりごとを言わない様に意識していますよね。
この一方で、発達障害を抱えている人はひとりごとが多いと言われています。これは、「周囲に合わせる意識」と「ひとりごとを言っても良いシチュエーション」を理解できていない場合が考えられます。
しかし、ひとりごとが多いからと言って、その人が発達障害を抱えているとは限りません。
発達障害の診断は難しく、長期間の診断や検査が必要になります。
「あの子、ひとりごとが多いから発達障害だ」と決めつけるは誤りです。
発達障害によるひとりごとの特徴

一般的なひとりごとと、発達障害によるひとりごとにはどのような違いがあるのでしょうか。
ただ、ひとりごと自体は決して悪いことではありません。むしろプラスに働くことすらありますので、まずは一般的にひとりごとを呟く理由や効果をご説明いたします。
ひとりごとを言う心理と効果
ひとりごとで自分の考えを整理
気持ちや考えを声に出すことで、物事を整理しやすくしている場合があります。無意識的に自分自身で確認をして、ミスを減らそうとしているといえるでしょう。
声に出さなければいけないほど、考えていることが多く余裕があまりない状態でもひとりごとは増えることがあります。
ひとりごとでストレスを発散させて心を保つ
多くのストレスを抱えていると、気持ちが自然と口から出てしまう場合があります。これは、言葉に出すことでストレスを発散させようとしている状態です。
不安感が強いときにもひとりごとが増える傾向にありますが、この場合は気持ちを声に出し自分の声を聴くことによって安心感を得ようとする働きだといえます。
ストレスや不安感を少しでも和らげるために、自分の声で気持ちを整えようとしているのです。
自分の世界に入り込む
周りを気にせず自分の世界に入り込んでいる状態でもひとりごとは増えます。マイペースな性格の方に多い傾向があるようです。
幻覚幻聴などで、誰もいないのに人と話しているような場合は精神疾患の可能性がありますので注意しましょう。
アスリートは自分の世界に入り込むことで精神を集中し本番に臨むことができるなどプラスに働く面もあります。
愚痴や自責の癖がある
他人や自分を非難しやすい人は、それを声に出しやすい場合があります。
「どうせ自分なんて…」「できるわけない」などのように否定的な考えは不満やストレスが多くなるため、よりひとりごとを増やすことになるでしょう。
基本的にネガティブな思考の方に多いといえます。
発達障害でひとりごとが増える理由
発達障害の方がひとりごとを言う心理は、一般的な状態と大きくは変わらないでしょう。しかし、発達障害の特性を考えると、ひとりごとを言いやすくなることが分かります。
- 行動するときに余裕がない
- ストレスを受けやすく耐性が低い
- 他人に関心が少なく自分の世界に入りやすい
- 不安感が強い など
定型発達児なら普通にできることが、発達障害の影響によってできない場面は少なくありません。これにより「変わった子」「怠けている」と周囲からは感じ取られてしまいます。
下記のツイートをご覧下さい。
このように、ひとりごとにつながる要因が多く、ストレスや不安を解消するためにひとりごとが増えているといえます。
さらに自閉症スペクトラム障害の行動特性が合わさることで、特徴的なひとりごとになるのです。
同じ言葉を繰り返す
行動とは特に関係のない言葉でも、繰り返して言い続けることがあります。自分の好きな言葉やセリフであることが多いようです。
自分の声で好きな言葉を聴くことにより安心感を得ようとしている可能性があります。
自分の好きな妄想の世界
自分の世界に入り込みやすい傾向にあるため、行動とは無関係でも妄想のような言葉が自然と口から出てくる方もいます。
自閉症のある子どものひとりごとを収めた動画を見つけましたのでご覧ください。
見聞きした言葉を繰り返す
特徴的な行動としてオウム返しを自然としてしまうことがあります。その影響を受け、見たものや聞いたものをそのまま声に出してしまう場合があるようです。
棒読みで抑揚のないひとりごと
人との会話でも棒読みのような話し方になってしまうことがあり、そのままひとりごとにも反映される場合があります。
ひとりごとを言いやすい発達障害とは
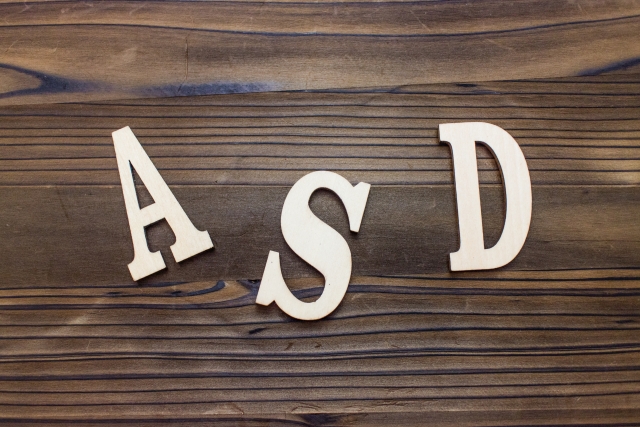
発達障害といっても症状によってさまざまな分類に分けられ、大きくは次の3つがあります。
- 自閉症スペクトラム障害(ASD)
- 注意欠陥・多動性障害(ADHD)
- 学習障害(LD)
この中でも特にひとりごとに関係しやすいものが自閉症スペクトラム障害です。
自閉症スペクトラム障害とは
自閉症スペクトラム障害は、以前使われていた広汎性発達障害という診断名とほぼ同じ意味合いで、コミュニケーション能力を中心に発達や能力に偏りのあるの状態です。
原因は、先天的に脳の一部に異常があることだとされていますが、はっきりとしたメカニズムはまだ解明されていません。子どもの約20~50人に1人の割合で、男性が女性の2~4倍多いといわれています。
かつては似た症状であっても特性が違うため別々の診断名が付けられていました。
- 自閉性障害
- アスペルガー障害
- 小児期崩壊性障害
- レット障害
- 特定不能の広汎性発達障害
これらの診断名を2013年に公開された『DSM-5』では、レット障害以外のすべてを自閉症スペクトラム障害だとしてまとめられたのです。
アメリカの精神医学会が出版している精神疾患の診断基準や診断分類のことです。日本の発達障害の診断基準としても使われています。
他にICDというものがありますが、こちらは世界保健機関(WHO)が作成している国際的な診断基準です。病院や医師によって使う診断基準は変わります。
現在でも病院や医師の方針などによっては、特性に応じた診断名をつける場合もあり、どれが間違いや正解というわけではありません。
3歳ごろから発達障害は見つかることが増える傾向にあります。自閉症スペクトラム障害以外の症状も合わせて詳しくお知りになりたい方は、こちらの記事もご参考ください。
自閉症スペクトラム障害の症状としては、軽症から重症の状態やさまざまな特性のすべてを総称した診断名であるため多様性があります。次にあげるのはその中でも代表的な症状です。
対人関係やコミュニケーションが苦手
基本的に、人に対する関心が少なく相手の気持ちや状況を把握することが苦手です。
保育園や幼稚園に行き始め、集団生活の機会が増えると独特な人との関わり方が目立つようになります。また、言葉の発達自体も遅れが見られることがあるため、さらに話す機会が減る傾向にあるようです。
特徴的な行動や例としては次のようなことが見られるでしょう。
- 人と目を合わせない
- 話し方が棒読みで不自然
- 表情や感情を読むことができない
- 空気が読めず孤立しやすい
- 集団でいても自分の世界に入りやすい
- ひとりごとやオウム返しが多い など
特徴的な行動のひとつとして『ひとりごと』があげられます。
単調で決まった行動はできる場合がありますが、その場に応じた行動が難しいため、臨機応変な対応を必要とする対人関係の構築には難しさがあるようです。
こだわりの強さや興味の偏り
子どもの頃から物事に対する好き嫌いが極端に表れ、決まりごとやルールなどに対して非常に強いこだわりが見られます。
自分の関心のあるものや自分のやり方を変えられることを嫌い、できることとできない事の差が大きくでるでしょう。
- 同じ行動を繰り返し続ける
- 物の置き方にこだわりがあり、毎回同じ位置や向きにする
- やり方や手順が同じでなければ気が済まない
- 興味のあることはとても詳しくなるが、興味の範囲がとても狭い など
こちらの方のように、分かっていても変更することが難しい場合があるようです。
気分や感情のコントロールが難しい
自分の考えや思いを言葉にすることが難しく、不満やストレスを感じやすい傾向にあります。さらにストレスの耐性も低く、上手にストレスと付き合うことができません。
そういう特性から、ささいなことでかんしゃくを起こしたり、乱暴したり、自傷行為がみられる場合もあります。
また、うまくできないことも理解しているため、普段から自信がなく不安感が強い傾向があり、常にストレスがかかっている場合が多いようです。
感覚の異常
通常は刺激を適切に感じ取ることで上手に対応してきますが、自閉症スペクトラム障害があると適切に感じ取ることができない場合があるようです。
- 季節、気温に合わない服装をする
- うまく身体を動かせない
- 物音に対して過敏に反応する など
感覚が過敏になったり逆に鈍感になったりと人によって様々な偏りがあります。体温調節について詳しい記事がありますのでこちらもご覧ください。
発達障害のひとりごとへの対策

基本的にはストレスや不安の軽減、考えの整理のために増えるひとりごとですので、無理に止めるのはオススメしません。
しかし、大声でのひとりごとなどにより、生活や社会性に影響が出てくる場合があります。
こちらの方のように、止めるのではなく上手く対応することで学校・社会生活などを円滑にできる場合があるのです。
- 不安やストレスの原因を取り除く
- 声を大きくしても良い場所の指導
- 抗不安薬などの服薬調整 など
つまり、ひとりごとを言っても良いシチュエーションを理解させることが必要になります。
ひとりごとが多いと自覚すること
無意識のうちにひとりごとを言っている場面は少なくありません。過度なストレスや頭がごちゃごちゃしている時などでは、ついつい声に出てしまいます。
まずは、ひとりごとを言っていることを自覚することです。
そして、周囲からひとりごとを言ってると指摘できる環境をおすすめします。ご家庭は勿論、学校のクラス、さらには職場などの協力があると良いでしょう。
さらに、ひとりごとの原因となっている事柄を整理し、不安の払拭や解決に繋げられれば、ひとりごとへの解消となり得ます。
ひとりごとに不安がある場合は専門機関へ相談
ひとりごとを意識して止めようとしても、常に意識をしていなければいけません。意識し続けることで疲れてしまいますし、なかなか簡単にはいかないものです。
まだ診断を受けておらず、お子さまやご自身のひとりごとに対して「発達障害かも…」と不安がある場合は、ひとりで悩まず専門機関に相談しましょう。
- 発達障害者支援センター
- 子育て支援センター
- 児童発達支援センター
発達障害者支援センターをクリックすると、相談窓口の検索ページに移行しますのでぜひ利用してみてください。
子育て支援センターと児童発達支援センターは、お住まいの地域と合わせて検索すると問い合わせ先が見つかります。
デイサービスという選択肢
家庭や医療だけでなく福祉サービスとも協力することでより改善しやすくなります。
放課後等デイサービス・アップでは、発達障害を抱えた児童を対象にデイサービス事業を行っています。

また、発達障害に関する情報を子育てに向けてのお役立ち情報記事を公開しています。ぜひ参考にご覧下さい。
まとめ
今回は発達障害のひとりごとについてお伝えしてきました。
誰でもひとりごとを言うことはありますし、ストレス発散や不安軽減など良い効果もあることが分かりましたね。
発達障害の特性で、特徴的なひとりごとが普段の生活の妨げになる場合は、本人も苦しんでいるのかもしれません。
ひとりごとに不安があってもまだ相談されていない方は、一度電話だけでもしてみてはいかがでしょうか。よい解決策が見つかるかもしれませんよ。