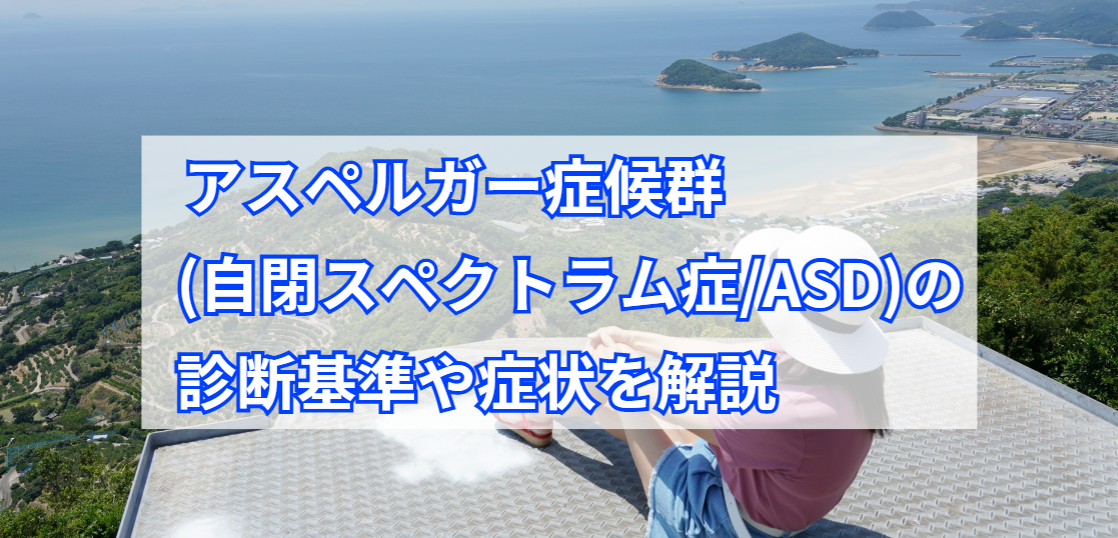皆さんこんにちは!本日も発達障害等に関する学びや情報交換の場になることを願って投稿させて頂きます。
今日のトピックは「アスペルガー症候群の診断基準」についてです。
「私の子どもはアスペルガー症候群なのではないか?」「社会に出てから失敗が増えたのは発達障害だから?」とお困りの方はいませんか?
今回は、発達障害の一つであるアスペルガー症候群の診断基準について解説します。
どのように判断されるのか、どうすれば診断できるのか気になる方はぜひご覧ください。
目次
アスペルガー症候群の主な症状

アスペルガー症候群は過去の名称で、現在は自閉スペクトラム症(ASD)と呼ばれることが多いです。
しかしアスペルガー症候群と呼ばれることはまだ多いため、本文ではアスペルガー症候群と示します。
アスペルガー症候群の3つの症状は、大まかに分けると次の通りです。
- コミュニケーションの障害
- 対人関係の障害
- 限定された物事へのこだわり・興味
コミュニケーションの障害
表面上は問題なく会話できているように見えても、会話の「間」を読むことができなかったり、裏に隠された思考を読み解くことが苦手です。
明確に言葉にしてもらうまで理解をすることが難しく、比喩表現を疑わないので言葉を勘違いした結果、傷つくといった一面が見られます。
冗談がわからずひどく落ち込んでしまうこともあるでしょう。
対人関係の障害
場の空気を読むことが難しく、相手の気持ちを理解して寄り添う言動が難しい傾向にあります。
社会的なルールや場の雰囲気を平気で無視したような言動をしてしまうこともあるでしょう。
対人関係をスムーズに築くことに困難があります。
複数人で業務を進める社会人は対人関係で成功体験をつかみにくいことから、発達障害の疑いが出る可能性が出てくるようです。
限定された物事へのこだわり・興味
ひとたび興味を持ったことには過度に熱中する傾向にあります。
特に、法則性や規則性のあるものを好み、異常なほどの執着を見せることもあるでしょう。
それと同時に、法則や規則が崩れることを極度に嫌がり、周りが見えなくなってしまうこともあります。
しかし、この特性は、日常生活に強みとして生かすことも可能です。
一つのことにこだわって熱中することで、周囲より抜きん出た才能を育てることもできるでしょう。
実際に、育てた才能を職業にして生かしている人は多くいらっしゃいます。
逆に個人のこだわりを捨てきれず仕事や学業でマイルールにのっとって作業を進めた結果、失敗体験をしてしまうと違和感を持つようになるかもしれません。
アスペルガー症候群については別途記事を用意しています。併せてご覧いただければ幸いです。
アスペルガー症候群の診断基準

アスペルガー症候群に関して気になる症状がある場合、医師に相談して診断を受けることが可能です。
ただし、どこの科でも受け付けているというわけではありません。基本的には精神科や心療内科で診断が可能ですので、気になる方は通院前に問い合わせてみるといいでしょう。
診断方法はアメリカ精神医学会のマニュアル(DSM-5)や、世界保健機関のマニュアルによる診断基準(ICD-10)から診断が下されます。
DSM-5は精神疾患の国際的な診断基準をいい、主に医師が診断に利用しているものです。
ICD-10は世界保健機関(WHO)が作成した診断基準であり、アスペルガー症候群と命名しています。
医療機関では質疑応答やテスト、ヒアリングによって総合的に判断が下された上で、一人ひとりのニーズにあった療育やサポートや投薬を目指すのです。
ヒアリングでは主にライフスタイルや日常生活においての困難に関する調査が行われます。
よって成長の記録に関し詳細なデータがあればあるほど、精密な検査を行うことが可能です。
なお前述したとおり、アメリカ精神医学会のマニュアル「DSM-5」では、アスペルガー症候群は自閉スペクトラム症と診断されるようになりました。
以上により今後アスペルガー症候群の診断が下されるケースは減少していくと考えられています。
アスペルガー症候群に気づくタイミング

アスペルガー症候群んは知的な遅れがなく、見た目では分かりづらい障害の一つです。
見た目で分かりにくいことから、当事者本人であっても自分がアスペルガー症候群とは気づかないまま生活をしている場合もあります。
赤ちゃんの時に診断が下ればいいのにと思う方もいるかもしれませんが、生後すぐにアスペルガー症候群の診断を下すことはありません。
言語や認知、学習などの発達領域が未発達の乳児段階では、症状が分かりやすく出ないからです。
またアスペルガー症候群の症状は、他の発達障害の症状と共通するものも多く、見分けるのが困難なこともあります。
そして他の発達障害の症状と併発する可能性もあるのです。
合併しやすい発達障害の一つとして「ADHD(注意欠如・多動性)」や発達障害の症状が悪化した結果、二次障害として「うつ」「双極性障害」などに悪化する可能性もあります。
症状が悪化する前に適切な処置を行う必要をしてください。
「この症状は発達障害なのでは?」と気になる方は、お近くの精神科や心療内科、市区町村の福祉課、発達障害支援センターなどに問い合わせてみることをおすすめします。
参考元:発達障害者支援センター・一覧
まとめ
今回はアスペルガー症候群の診断基準についてまとめました。
最後に万が一診断が必要になった時に理解しておきたい点をお伝えします。
- アスペルガー症候群は知的障害をともなわず見た目だけでは判断しにくい
- 診断は基本的に精神科や心療内科
- ヒアリング時に迷わないよう普段から症状を把握しておく
普段から自分の症状がどんなタイミングで発病するのか、それに対する影響をまとめておくと診断時に役立ちます。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。