皆さんこんにちは!本日も発達障害等に関する学びや情報交換の場になることを願って投稿させて頂きます。
今日のトピックは「発達障害の症状のうちADHD(注意欠如・多動性障害)」についてです。
近年発達障害について取り上げられることが増え、ADHD(注意欠如・多動性障害)へ関心を持つ方が増えています。
そこで今回はADHD(注意欠如・多動性障害)について特徴や原因、治療法などを解説しますので、参考にしてみてください。
目次
ADHD(注意欠如・多動性障害)とは

ADHD(注意欠如・多動性障害)とは発達障害の1つで、不注意(集中力がない)、多動性(じっとしていられない)、衝動性(考えずに行動してしまう)の3つの症状が見られます。
子どもの20人に1人、成人の40人に1人にADHDが生じるとされており、男女比には偏りが見られません。
文部科学省によるADHDの定義は次の通りです。
ADHDとは、年齢あるいは発達に不釣り合いな注意力、及び/又は衝動性、多動性を特徴とする行動の障害で、社会的な活動や学業の機能に支障をきたすものである。
また、7歳以前に現れ、その状態が継続し、中枢神経系に何らかの要因による機能不全があると推定される。
なお、アメリカ精神医学会のマニュアル「DSM-5」での診断年齢は12歳以上です。
「Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders」の頭文字を取り、略称がDSM、5は第5版を表しています。
日本語へ訳すと「精神疾患の診断・統計マニュアル」となり、米国精神医学会が発行しているものです。
精神疾患の基本的な定義を記しており、精神疾患の治療や精神医学の研究などで利用されています。
DSM-5の詳しい診断方法は別途記事を参照してください。
ADHDの原因

ADHDの症状があられる原因は、生まれつきの脳機能障害といわれています。
よって親の育て方やしつけが直接の原因ではありません。
生まれつきの脳機能障害と家庭環境や生活環境がかみ合わないことから以下の困りごとが発生しやすくなります。
- 忘れ物をしたり物を紛失する
- 授業中おしゃべりをしたり走り回る
- 友達が出来ずに孤立する
ADHDの症状

ADHDの症状には不注意型、多動型、衝動型の3種類に分類できます。
不注意
- 物事を途中で放り出してしまう
- 忘れ物が頻発する
- 集中することが困難であるが、興味の対象には集中過多で切り替えができない
- 片付け・整理整頓が苦手
- 注意力散漫ですぐに気が散る
- 忘れっぽく物をなくしがち
多動性
- 落ち着いていられない
- じっと座っていることができない
- 気がつくと体が動いてしまう
- 過度におしゃべり
- 公共の場などにおいて静かにすることができない
衝動性
- 順番を待つことができない
- 気に触ることがあると粗暴になる
- 会話の流れを読まず思いつくままに発言する
- 他人の邪魔をして横入りしてしまう
ADHDのタイプ別の特徴
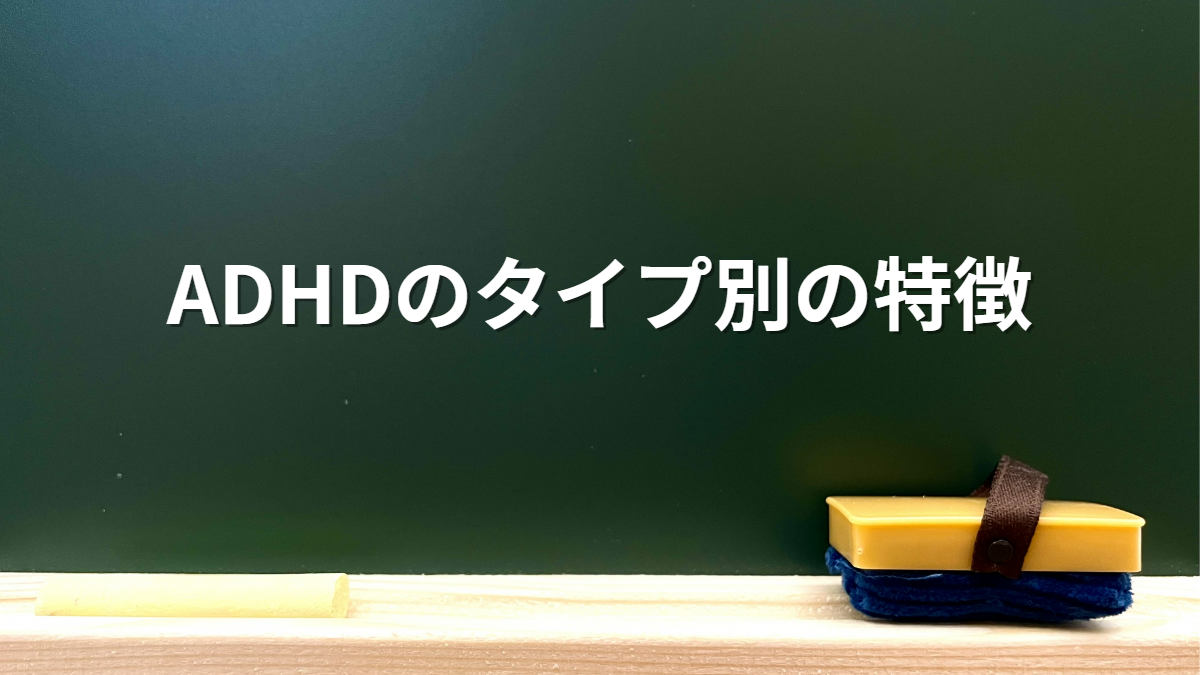
ADHDの症状は人によって現れ方が異なります。
現れ方は多動性と衝動性優勢型、不注意優勢型、多動性と衝動性、不注意性混合性の3パターンに分かれます。
多動性-衝動性優勢型
多動と衝動の症状が強く出るタイプです。
ADHD全体で見ると少ないタイプですが、主に男性に多く見られます。特徴は次の通りです。
- 授業中などじっとしているべき場面でも歩き回ったり体を動かしてしまいがちで落ち着いていられない
- 衝動的で、なんでもないようなことで大声をあげたり乱暴になってしまうため、乱暴で反抗的な性格だと思われてしまいがち
- 衝動的に不適切な発言をする他自分の話ばかりしてしまう
不注意優勢型
不注意の症状が強く出るタイプです。
幼少期の子どもはADHDでなくとも忘れ物を頻発することがあるため、このタイプの場合ADHDであると発覚するのが遅くなることもあります。
また、不注意の特性は、男性よりも女性に多く見られます。特徴は次の通りです。
- すぐに気が散って1つのことに集中できない
- 自分の興味のあることに対しては集中できるが切り替えができない
- 忘れ物や物を紛失することが多く、人の話を聞いていないように見える
混合型
多動と衝動、不注意の症状が混ざり合い強く出るタイプです。特徴は次の通りです。
- 多動性-衝動性優勢型と不注意優勢型両方の特徴を持っており、どちらが強く出るかは個人差がある
- 忘れ物や物の紛失が多く、落ち着きが見られずじっとしていられない
- 決まり事を守ることが難しく順番が守れない、大声を出すなどといった衝動的な行動が見られる
ADHDは他の発達障害や睡眠障害と併発することがあります。
その場合、ここに挙げたもの以外の特徴が見られる場合もあるでしょう。
ADHDの治療法

ADHDを根本的に治療する方法はありませんが、症状を和らげることは可能です。
症状を和らげる方法として主に2種類あります。
- 薬物療法
- 療育
薬物療法
ADHDは脳機能障害による症状とお伝えしましたが、具体的には脳内の神経伝達物質であるドーパミンやノルアドレナリンが不足しています。
薬物療法ではそれらの神経伝達物質を改善するために以下の薬を処方されるようです。
- コンサータ
- ストラテラ
- インチュニブ
- ビバンセ
参考元:処方薬事典|日経メディカル
薬物療法の別の目的として、二次障害を防ぐために用いられることもあります。
療育
ADHDを抱えるお子さんが集中できるよう環境を整えたり、集団生活ができるようコミュニケーションスキルを身に付ける手助けを行います。
療育はご自宅の他、以下の施設でも可能です。(※一部を除く)
- 全国の保健所・保健センター
- 児童発達支援センター
- 児童発達支援事業所
- 発達障害者支援センター
- 放課後等デイサービス
全国の保健所・保健センター
地域保健法で定められている公的機関で、双方協力しながら地域の保健衛生に務めます。
保健所は保健所は行政的な役割を担い、地域住民の健康の保持増進に関する業務を実施します。
対する保健センターは地域の住民向けに健康相談、保健指導、健康診査など、地域保健に関する事業を行います。
参考元:地域保健|厚生労働省
児童発達支援センター
厚生労働省令(児童福祉法)で定められた支援施設で、通所利用を目的とした児童やその家族を支援するものです。
児童発達支援センターは「福祉型」「医療型」に分かれ、福祉型は福祉サービスを提供し、医療型は福祉サービスだけではなく治療も行うと位置づけられています。
近年では後述する放課後等デイサービスを併設した児童発達支援センターもあります。
児童発達支援事業所
児童発達支援センターと同様、厚生労働省令(児童福祉法)で定められた発達障害支援施設です。
対象は0歳から小学校入学前までの未就学生とそのご家族で、発達障害の症状が原因の困りごとを解決するために支援を行います。
発達障害だけではなく、難病にかかったお子さんも対象です。
お子さんそれぞれの特性を活かし、日常生活の基本的な動作を指導、集団生活に必要なスキルを取得する訓練などを行います。
地域密着型の施設ですから、対象のお子さんやご家族だけではなく、保育園や幼稚園、特別支援学校や小学校などの施設とも連携を取っています。
発達障害者支援センター
対象年齢に制限はなく、発達障害を抱える人を対象に支援を行う専門的機関です。
運営は社会福祉法人や特定非営利活動法人などが地域の関連機関と連携して行っています。
活動内容は、発達障害者とそのご家族向けにさまざまな相談に応じ、指導と助言を行います。
放課後等デイサービス
放課後等デイサービスとは、発達障害を含む障害のある小学生・中学生・高校生を対象とした長期通所支援サービスを行う施設です。
お子さんが生活していく上で必要なスキルなどを身に付けるための訓練や社会との交流を行います。
障害のあるお子さんの保護者を対象に育児相談なども受け付けています。
放課後等デイサービスについて詳しく知りたい方は以下の記事も併せてご覧ください。
まとめ
今回は発達障害の特性のうちADHD(注意欠如・多動性障害)について解説しました。
ADHDといっても人によって現れる症状は異なります。
それぞれのお子さんに合った方法で症状を和らげれば、社会に適応できるといわれています。
支援者は一律に当てはめるのではなく、状況に合わせた対応が必要です。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。

