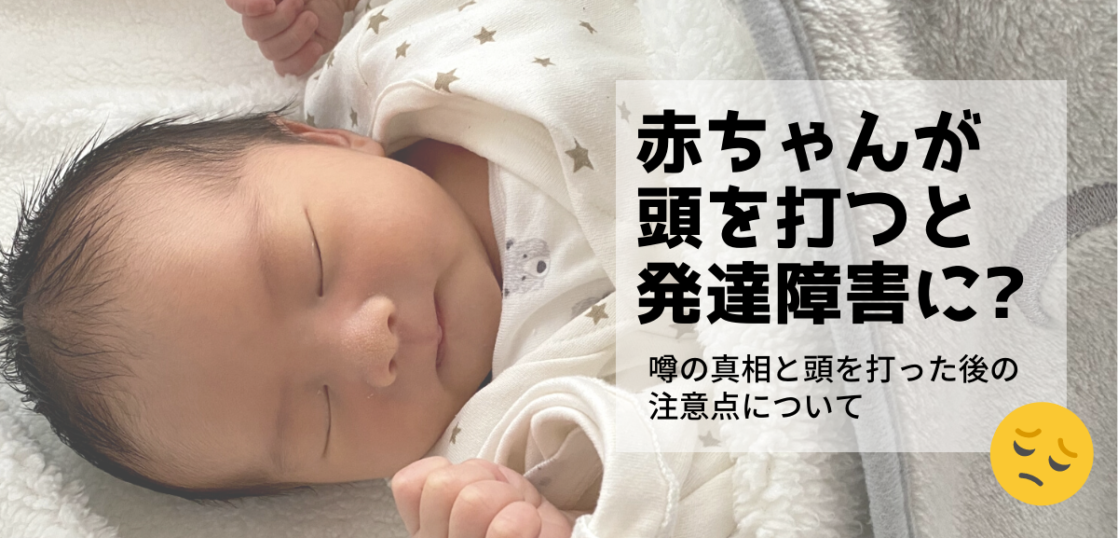皆さんこんにちは!本日も発達障害等に関する学びや情報交換の場所なることを願って投稿させて頂きます。
今日のトピックは「赤ちゃんが頭を打つと発達障害になるか」についてです。
「元気な赤ちゃんが動き回っている時に頭を打って大泣き」というシチュエーションはよくありますよね。そうだとしても、とっさにできることや後遺症が出ないか心配になってしまいます。
そこで今回はまことしやかに噂される、「赤ちゃんが頭を打った後に発達障害になるか?」そして「頭を打った後の注意点」についてお答えします。参考になれば幸いです。
目次
赤ちゃんが頭を打っても発達障害にはならない

結論からお伝えすると、赤ちゃんが頭を打っても「発達障害」にはなりません。
だからといって、どんなに頭を打っても大丈夫という意味ではありません。本項では、発達障害と頭を打つことの関係性の低さを紐解きます。
発達障害とは
はじめに、厚生労働省が定義する発達障害についての説明を確認します。
発達障害は、生まれつき脳の発達が通常と違っているために、幼児のうちから症状が現れ、通常の育児ではうまくいかないことがあります。
引用元:厚生労働省|みんなのメンタルヘルス
以上の説明により、発達障害は”生まれつき”の脳の異常によって起こるものとされています。つまり、生まれた後の赤ちゃんが頭を打って起こる異常は、発達障害とはいえないのです。
もう少し発達障害について掘り下げてみましょう。発達障害は大きく3つに分けられいますが、複数の症状が絡み合っている場合もあります。
自閉症スペクトラム(ASD)
自閉症やアスペルガー症候群、広汎性発達障害などを含めた症状を指します。
- 対人関係の障害
- コミュニケーションの障害
- 興味、行動のこだわり
以上3つが特徴としてあげられます。約100人に1~2人の割合といわれ、男性が女性より数倍多いようです。
注意欠陥多動性障害(ADHD)
発達の年齢に見合わない多動性と衝動性、不注意がみられる状態をいいます。
- 話を聞かない
- ミスが多い
- 友達を叩くことが多いなど
自閉症スペクトラム(ASD)と同様、注意欠陥多動性障害(ADHD)も男性の割合が女性より数倍多いようです。
学習障害(LD)
知的障害とは別で、特定の学習が極端に苦手な状態をいいます。
- 読めない
- 書けない
- 計算ができないなど
学習障害(LD)も男性の割合が女性より数倍多いようです。
参考元: 厚生労働省|みんなのメンタルヘルス
発達障害は先天的なもので病気ではなく『治す』ものではありませんが、症状を改善・緩和する方法は考えられています。
成長と共に状態が良くなることも多く、決して発達できないという障害ではありません。
発達障害の原因についてより詳しく知りたい方は、「発達障害児はなぜ生まれる?原因解明の兆しと暮らしやすい社会にするために」の記事もご覧ください。
また、発達障害の診断名がつくと放課後デイサービスなどの福祉サービスを受けることもできます。興味のある方はこちらも併せてご覧ください。

発達障害以外で頭を打つことのリスクとは?

軽い転倒くらいでは障害や後遺症のリスクは低いと言われていますよ。
赤ちゃんの頭の仕組みについて
頭蓋骨はいくつかのパーツに分かれており、それぞれの継ぎ目が固定されてできています。
赤ちゃんの頭蓋骨はまだ継ぎ目が固定されておらず、骨自体も柔軟性があるため衝撃を受けても吸収でき骨折しにくい特性があるのです。
大泉門が開いている
頭蓋骨の継ぎ目のひとつで、頭頂部にあるひし形の隙間をいいます。この隙間があることで、さらに衝撃を吸収して骨へのダメージを減らしているのです。
脳は髄液(ずいえき)という液体の中に浮かんでいる状態なので、骨や髄液がクッションとなり、脳が簡単には損傷しません。
赤ちゃんの大泉門について詳しく知りたい方はYouTubeで詳しく解説されていますので、確認してみてください。
脳自体の回復力
赤ちゃんの脳はまだ未熟ではあるものの、成長と同時に回復力がとてもあります。仮に軽い損傷を受けたとしても、健康な部分の脳が補い、障害を残さない場合もあるのです。
頭を打つと起こりえる怪我や病気
赤ちゃんの脳が守られているとはいっても、さまざまなリスクは残ります。本項では、頭を打つと起こりえる代表的な怪我や病気について確認していきましょう。
頭蓋骨骨折
強い衝撃によって頭蓋骨が損傷した状態で、一般的にヒビが入ったという状態も骨折に該当されます。赤ちゃんの骨は柔らかいため、頭蓋骨がへこむような骨折してしまうのです。
別名「ピンポンボール型骨折」といい、内部に出血や損傷の危険性もある状態です。外傷によって脳まで損傷する症状を「外傷性脳損傷」と呼び、後遺症を残す可能性があります。
赤ちゃんとは異なる基準で考えましょう。
皮下出血(たんこぶ)
一般的にいわれる「たんこぶ」は、頭皮のすぐ下にある毛細血管が破れたときに起こる腫れのことで、正しくは皮下出血と呼ばれます。
痛みはありますが、たいていは徐々に小さく硬くなっていき、特に後遺症もありません。
しかし、いつまでも柔らかい腫れが残っている場合は注意が必要で、骨折の可能性もあります。特に側頭部は骨が弱いので気を付けましょう。
脳震盪(のうしんとう)
頭への衝撃によって脳が揺れて一時的な意識消失やめまい、頭痛が起こった状態です。
軽度な症状の場合では後遺症を残すことはありませんが、数日以内に何度も繰り返されると、脳が大きく腫れることがあり命の危険も出てきます。
急性硬膜下血腫
1歳までは頭蓋骨が大きく成長するため、脳との隙間が広くなり、逆に2歳未満は脳が揺れやすく血管が損傷しやすい状態になり、7歳未満までは急性硬膜下血腫が多いといわれています。
血管損傷での出血量によって現れる代表的な症状は以下の通りです。
- 意識障害
- けいれん
- 嘔吐
昏睡状態から急激に悪化して最悪は死に至るケースもある恐ろしい状態です。手術が適応される場合には、開頭して血腫を取り除く必要があります。
年齢によって出血方法が異なるんですね。
慢性硬膜下血腫
すぐに症状が現れる急性に対して、慢性硬膜下血腫の場合は数週間や1~2ヶ月後に症状が現れ始めます。
特に2歳未満に多く見られるため注意しましょう。症状としては急性硬膜下血腫と似ていますが、徐々に現れてくるといわれています。
二次性注意欠陥多動性障害
冒頭で、頭を打っても正式な発達障害にはならないとお伝えしました。
近年アメリカの論文で「頭を打つことで二次性注意欠陥多動性障害を起こす可能性がある」という内容を発見しました。
結論としては、3歳から7歳に外傷性脳損傷になると脳損傷のない場合と比べて、注意欠陥多動性障害の症状が出やすいというものです。
つまり、軽度の頭部外傷と注意欠陥多動性障害を結びつける内容ではありませんでした。論文の内容を5分程度でまとめた動画がYouTubeに投稿されています。
論文の内容を文章で確認したい方は海外サイトの記事「Secondary Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder in Children and Adolescents 5 to 10 Years After | JAMA Network」を参考にしてください。全文英語ですが、日本語翻訳することで大まかな内容は把握できます。
赤ちゃんが頭を打った後の注意点と対応

頭を打った時に注意するポイント
ゴツンと頭を打って、痛みと驚きでほとんどの赤ちゃんは大泣きしてしまいます。
実は、すぐに泣いたときはひとまず安心して良い状態で、逆に泣かない場合は危険な状態と疑いましょう。
頭を打って危険性が高い状態をまとめを下記にまとめました。症状が現れた場合は脳に何らかのダメージを受けている可能性があるため、該当する項目がひとつでもあれば病院を受診しましょう。
- 2歳未満で90cm以上の高さから落下
- 2歳以上で150cm以上の高さから落下
- 生後3ヶ月未満
- 2回以上繰り返して吐いた
- 10分以上泣きやまない
- けいれんが起こった
- 5秒以上意識を失った、すぐに眠りなかなか起きない
- 手足が脱力している
- 顔色が悪く元気よく泣かない
- 耳や鼻から水のようなものや血が出ている
- 傷口が開いて出血が止まりにくい
- 2歳未満でおでこ以外にたんこぶができている
参考元:広島医師会子どもサポーターズ、東京ベイ・浦安市川医療センター
頭を打った後の対応
頭を打った後は安静に
意識がはっきりとしていて特に外傷もない場合は、まずは安心して安静にしましょう。最低でもその後12時間は安静を保ち、転倒を繰り返さないようにしてください。
痛みが引き機嫌が直って、嘔吐することもなければ過度な心配はしなくても大丈夫です。逆に、徐々に状態が悪くなる場合は病院を受診しましょう。
2~3日後に悪化するケースもありますので、注意して見ておいた方が良いですね。また、慢性硬膜下血腫の場合は1ヶ月以上経ってから症状が現れる場合もあります。
念のために、頭を打った日をメモやカレンダーに残して経過を把握できるようにしておきましょう。
たんこぶがある場合
毛細血管が出血して腫れている状態ですので、まずは冷やすことが大事です。冷やすことで、血管が縮小して腫れを抑えられ、痛みが和らぎます。
個人差はありますが、完全に治るまでには1ヶ月程度かかるでしょう。いつまでも柔らかいコブが残るようであれば骨折など他の原因が考えられるため、病院に受診してください。
・冷やされた保冷剤をハンカチやタオルなどで巻いて患部に当てる
・ハンカチやタオルを氷水に付けて絞り患部に当てる
・時間は20分~30分が目安
保冷材の代わりに、ビニール袋に入れた氷水でも大丈夫です。氷嚢や水枕があれば、そちらを利用しても良いでしょう。
※直接氷を押し当てると凍傷の原因になりますので注意してください。
出血がある場合
意識がはっきりしていて出血がある場合は以下の手順で止血します。
- 傷口を水で洗い、消毒する
- 傷口を確認する
- 傷が浅ければ清潔なタオルや滅菌ガーゼで押えて止血
- 傷が深い場合、止血しながら救急車か病院受診
意識が無い、もしくは不明瞭で出血がある場合は緊急性が高いため、すぐに止血して救急車を呼びましょう。
出血中に身体や頭を揺らすなど大きく動かしてしまうと、出血がひどくなる危険性があります。
動きが最小限になるように注意しましょう。
病院受診や救急車を呼ぶ場合
病院受診する場合は
- 脳外科、脳神経外科
- 救急科
- 小児科
などが担当科になります。また、医師や救急救命士には次のようなことを伝えるとスムーズに対応してもらえます。親御さんは冷静になって、以下のようにあらかじめ伝えることを把握しておきましょう。
- 頭を打った状況(転倒した高さや何にぶつかったかなど)
- 病院受診、救急車を呼ぶまでの経過
- 症状や怪我の部位
- 応急処置をどのようにしたかなど
転倒・転落予防の方法
赤ちゃんは頭が重く大きく支えるための体の筋肉も未発達で、転倒したときに反射的に手が出るなどの防御反応もありません。
転倒や転落をした場合、赤ちゃん自身が身を守れるわけがなく結果的に頭を打ってしまいます。
怪我を防ぐためには24時間体制で見守りができればそれが一番安全でしょうが、現実的ではありません。そこで、転倒・転落を少しでも減らすための方法についてお伝えしましょう。
心がけとして
当たり前ではありますが、赤ちゃんは危険なことが分かりません。そのため、ちょっと目を離した隙に転倒・転落している事もあります。
基本的に椅子やソファーの上など高く不安定な位置で遊ばせたり、放置したりしないようにしましょう。
環境を整える
事前に転倒・転落の危険性を減らす環境を作ることはとても大事です。
- ベビーベッドの方が安全性は高い
- 床は整理整頓する
- 踏み台になりそうなものは片付ける
- 怪我防止のためベッドの周りなどにクッションやマットを敷くなど
ベビーベッドが準備できない場合は、お布団の方が転落の可能性がなくなります。赤ちゃんが両親と一緒に寝ると、口をふさいで窒息させてしまうリスクがあるためオススメはしません。
以降参考として、いざという時にも身を助けるお役立ちグッズを紹介いたします。
お役立ちグッズ:見た目もかわいい「滑り止めハーネスベルト付き」
「メッシュ素材の夏仕様赤ちゃんの頭を守る滑り止めハーネスベルト付き」はAmazonのCMでかなり有名になった商品です。
リュックのように背負い、後頭部をクッションで保護してくれます。
後頭部はおでこよりも骨自体が弱く、バランスが取れないうちは後方へ転倒するリスクも高いためオススメです。
お役立ちグッズ:仕切り柵「ベビーズゲイト」
赤ちゃんはある程度動けるようになると、危険な場所や階段などにひとりで行ってしまう可能性があるため、 入ると危ない箇所へ策を設置すれば危険を未然に防ぎます。
「ベビーズゲイト」は大人はロックをはずして出入りが自由にできるため、使い勝手が良く価格もお手頃でデザインとしてもシンプルで設置しやすい点がおすすめです。
お役立ちグッズ:ベッドを固定できる「伸縮式ベッドレール」
「伸縮式ベッドレール」はベッドに合わせて伸縮可能です。大人用のベッドで一緒に寝る場合は、転落防止で柵を取り付けると効果が発揮し、複数購入して隙間をなくすように設置すればより安全性が高まります。
もしも頭を打っても、落ち着いて対応できるように心構えはしておきましょう。
まとめ
頭を打った赤ちゃんと発達障害の関係性、頭を打つリスクや注意点についてお伝えしてきました。
発達障害は先天的な脳の異常が原因なので、頭を打ってなるものではないことが分かったと思います。
しかし、脳を損傷するほどの外傷があると、ADHDの症状がでる可能性もあるという論文が見つかり、まだ解明されていない点も多くあります。
強く頭を打つとさまざまなリスクが現れるため、しっかりと対策をするだけでなく、いざという時には迅速な対応ができるように備えましょう。