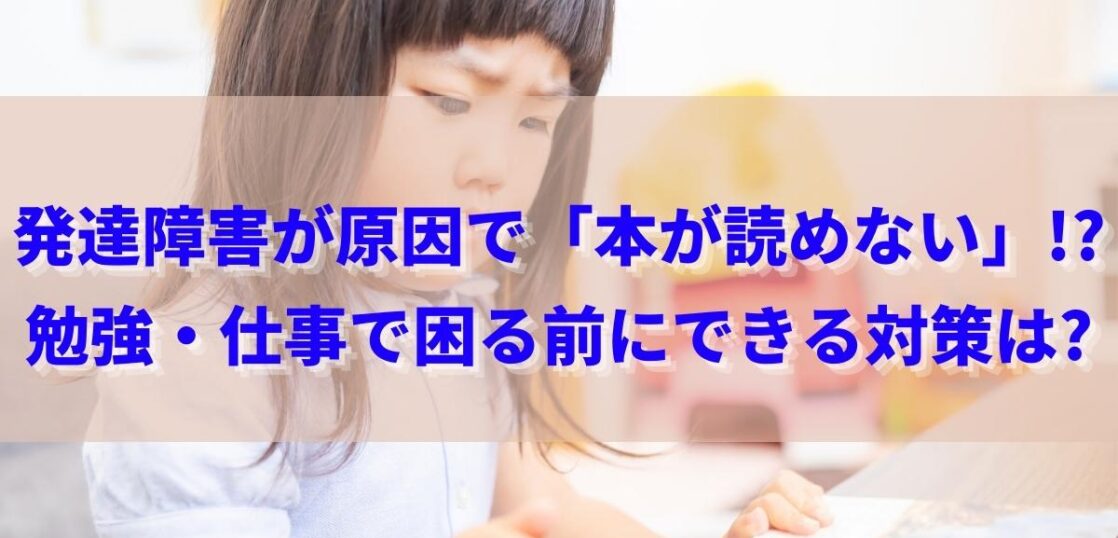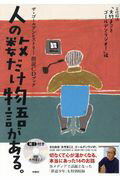皆さんこんにちは!本日も発達障害等に関する学びや情報交換の場所なることを願って投稿させて頂きます。
今日のトピックは「発達障害と読書の困難」についてです。
発達障害からの困りごとの1つに、「本が読めない」という悩みがあります。
ご自身やお子さん、周囲の人などでお心当たりはありませんか?
本は、私たちの身近にあふれている貴重な情報源ともなるものです。
発達障害が原因で「本が読めない」とは、どのような状態なのでしょう?
そして、本人や周囲には、どのような対策ができるのでしょうか。
この記事では、発達障害と「本が読めない」状態について調べ、本人や周囲ができる対策を盛り込んでまとめました。
つらい読書を改善するために、―緒に勉強しましょう!
目次
発達障害からの「本が読めない」状態ってどんなもの?
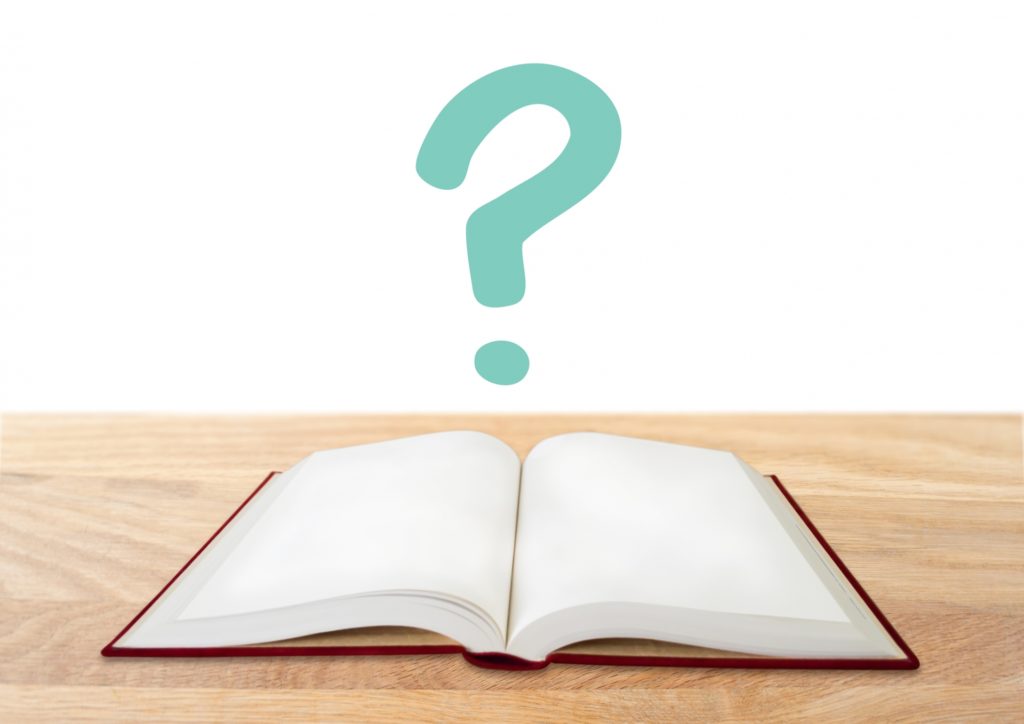
本とは、知らない情報や物語を教えてくれる、豊かで貴重な情報源です。
「お気に入りの1冊」に出会い読書の喜びを知る経験は、知識を重ねることで進化してきた人類にとっては、他のものには代えがたい財産かも知れませんね。
読書には、「集中力」と「文字を読む能力」が欠かせません。
しかし、様々な障害などにより本を読むことが困難なケースもあります。
発達障害もそのうちの1つです。
発達障害の特性がこの「集中力」と「文字を読む能力」に関わってくるケースには、主に2つのパターンがあります。
【発達障害の特性が読書に関わるケース】
- ADHDの特性により集中することが苦手
- 学習障害のひとつ「発達性ディスレクシア」によって文字が苦手
では、それぞれの特徴について詳しくみていきましょう。
そもそも、発達障害とは?
発達障害とは、生まれつき脳の発達に特徴があり、「できること」と「できないこと」の差が極端に大きく開いてしまっている障害の総称です。
発達障害には様々な種類があり、大きく分けて3つに分類されています。
- 注意欠陥多動性障害(ADHD)
→じっとしていられない、注意が散漫になるなど - 自閉症スペクトラム(ASD)
→コミュニケーションが取りにくいなど - 学習障害(限局性学習障害/限局性学習症、LD)
→「読む・書く・計算する・聞く・話す」ことに困難が生じる
1人が複数の特性を併せ持つこともあり、症状の現れ方や程度には個人差があります。
ADHDの特性により集中することが苦手なパターン
ADHD(注意欠陥多動性障害)を持つ人には、主に下記のような特徴があります。
【ADHDの特徴の例】
- 約束を忘れやすい
- 物を失くしやすい
- じっとしていることが苦手
- 衝動的に行動してしまう
※ 特徴や症状の度合いは個人によっても差があり、全ての特徴を持っているとは限りません。
ADHDの特徴から、集中力を必要とする行為が苦手である可能性は否定できません。
例えば「興味のあることにすぐ意識が移ってしまい、何かをやりかけたまま別の行動を始めてしまう」などです。
これが読書に結びついてしまった結果、「本を読もうとしても、周囲の出来事に気が散ってしまう」=「本が読めない」状況が起こる原因となるのです。
ADHDには、不注意が多い「不注意優勢型」と、落ち着きなく行動してしまうことの多い「多動・衝動性優勢型」があるとされています。
両方の特徴が同じくらい出ている場合は「混合型」と呼ばれます。
「発達性ディスレクシア」によって文字が苦手なパターン
「発達性ディスレクシア」は、「学習障害」に分類される発達障害です。
主な学習機能のうち「読む」と「書く」の機能に困難が生じることが特徴とされています。
学習障害は、「読む」「書く」「計算する」「聞く」「話す」のいずれか、あるいは複数の能力に困難が生じる発達障害です。
参考元:文部科学省「学習障害児に対する指導について(報告)」(平成11年7月)
「ディスレクシア(dyslexia)」には、ギリシャ語でdys「困難」、lexia「読む」という意味があります。
別名で「読み書き障害」「読字障害」「難読症」と呼ばれることもあります。
【発達性ディスレクシアの特徴の例】
- 幼児期は文字に興味がない
- 文字が変質して見える
(ゆがむ、踊っている、かすむ、バラバラになる、刺さるように見えるなど) - 促音拗音の誤りが多い(「っ」「ょ」など)
- 同音の文字を間違えやすい(「は」「わ」など)
- 形が近い文字の誤りが多い(「あ」「お」など)
※ 特徴や症状の度合いは個人によっても差があり、全ての特徴を持っているとは限りません。
人は「文字」という記号を頭の中でそれぞれ対応する「音」に置き換えることで「読む」、頭の中に浮かべた「音」を対応する記号に置き換えることによってはじめて「書く」ことができます。
しかし、発達性ディスレクシアを持つ人には、この「記号と音を結びつける行為」が難しいそうです。
誰かに読んでもらって耳から入った情報は理解できますが、自分で読もうとしたり、書こうとしたりすると途端に難しくなってしまうのです。
一説では日本人の約8%(厚生労働省の解説では児童生徒の3.3%)は発達性ディスレクシアがあると考えられているそうですが、「認知度が低い」「全くできないわけではなく、何度か繰り返すと読めるようになる」などのケースから、周囲や本人が気付かないことも少なくないようです。
参考元:e-ヘルスネット(厚生労働省)|「学習障害」
発達性ディスレクシアの「文字に対する苦手」は、長い文章を読む時には次のような症状となって表面化します。
- 音読がたどたどしくなる
- 読むスピードが遅い
- 読むので精いっぱいで内容が頭に入ってこない
- 文末を自分で適当に変えてしまう
- どこを読んでいるのかわからなくなる
細かい文字の長い文章が集まってできている「本」は、発達性ディスレクシアを持つ人にとっては「苦手」が延々と待ち構えている状態だといえるでしょう。
文字を読むこと自体が大きな負担となり、「文字を読むだけで疲れてしまい内容が頭に入って来ない」=「本が読めない」状況が起こるのです。
↓発達性ディスレクシアについては以下の動画を参考にしてください。「読む」ことの難しさが体験型で紹介されています。
参考動画:YouTube「LD疑似体験:学習障害(LD)の中から”読む”ことのへ困難について」悠々ホルン Talk
「生きづらさ」と二次障害について

本は私たちの日常生活にも欠かせない貴重な情報源。娯楽のための本ばかりではなく、教科書や実用書などの知識を得るための本もあります。
年齢に応じて学ぶ文字の種類も増え、難しい漢字や英語も勉強し、義務教育を終える頃には一通り「本が読める」ようになるのが日本における一般的なスタイルです。
日本では義務教育により一斉に勉強することが「当たり前」であり、年齢を見て「できるかどうか」が判断される、つまり年齢と学習具合が結びついています。
休学や障害など何らかの事情で学習できないと「その年齢でこれができないの?」と驚かれてしまったり、場合によっては「なぜ勉強してこなかったんだ!」と頭ごなしに怒られてしまったりと、窮屈な思いをする可能性があります。
文字の読みや形を覚えるだけではなく、正しい使い方も求められますね。
「本が読めない」と感じる生きづらさとは
【本が読めないと感じる生きづらさ一例】
- 先生や上司に怒られる
- 学習や仕事についていけない
- 手順がわからずミスしてしまう
本を読むのが苦手なために日常生活の困難へ繋がり、生きづらさを感じてしまう可能性があります。
小学校1年生で「ひらがな」を習い始めることを最初に、私たちは本を読む能力を身に着けていきます。
学生時代であれば「参考図書を期日までに読んでくる」といった課題が出てれば慌てて読み込む必要が出てくるのです。
社会に出ると仕事のマニュアルや契約書類を読むことも必要とされ、「マニュアルを渡されるだけで、詳しい説明をしてもらえない」場面にも出くわします。
年齢によって状況はことなるものの、本を読むのが苦手なままだとより生きづらさを感じやすくなりがちです。
二次障害のリスクも
負担の多い生活や周囲の理解を得られない生活が続くことで、ストレスや不安から二次障害を発症してしまうこともあります。
二次障害とは、日常的に感じる「生きづらさ」や対人関係のトラブルにより強いストレスや不安を感じ、不登校や鬱(うつ)、引きこもりなどの深刻な状態におちいってしまうことです。
発達障害は外見からは判りづらい障害である為、「本が読めない」といった困りごとを理解してもらえないことも少なくありません。
状況を伝えても「本人の努力が足りないからだ」「なまけている」「不真面目だ」などと責められてしまい、心が傷つく可能性があります。
どうすれば「本が読みやすく」なる?

発達障害の特性からの「できないこと」は、特性に合わせて工夫すれば本が読みやすくなるかもしれません。
例えば、障害などから本が読みづらい人に向けた「オーディオブック」「大活字本」「マルチメディアデイジー」といった形態の「本」を活用する方法があります。特性ごとに工夫を確認していきましょう。
ADHDの特性に合わせた工夫
【集中力を継続する工夫の例】
- 机の周りに「ついたて」をする
- 耳栓やイヤーマフを使用して雑音を避ける
- 目標を短く区切る
ADHDの特性から気が散ってしまい読書に集中できない場合は、周囲からの情報を遮断して本に集中する、あるいは「5ページ読んだら休憩する」「10分読んだら休憩する」など目標を短く区切ることで集中する、など工夫をしてみてはいかがでしょうか。
利用できる環境であればイヤーマフや耳栓を積極的に利用すると不要な雑音から解放され、集中力継続が期待できます。
発達性ディスレクシアの特性に合わせた工夫
発達性ディスレクシアの特性から文字を読むことが苦手な場合は、「読みやすさを補う工夫」や「IT機器を使った工夫」をすることで読みやすくなるかも知れません。
読みやすさを補う工夫
【読みやすさを補う工夫の例】
- シートなどで他の行を隠して読む
- 文節ごとに「/」を入れる
- 色のついたフィルムなどを重ねて読む
発達性ディスレクシアによる文字の読みにくさは、一度に目に入ってくる行の数を減らすことで負担が軽減できるかもしれません。
また、文節ごとにスラッシュ「/」を入れる、色のついた透明フィルム・下敷き・クリアファイルなどを本のページの上から重ねることも、読みやすさを補う効果が得られるといわれています。
IT機器を使った工夫
【IT機器を使った工夫の例】
- 電子書籍を利用する
- タブレット端末などで音読機能を使用する
- 見やすいフォントの書体やサイズに合わせる
- 本のページを拡大する
発達性ディスレクシアによる文字の読みづらさは、電子書籍やタブレット端末のアプリケーションソフトの機能を使用の他に、見やすいフォントの書体や大きさに合わせることで補える可能性があります。
見やすい文字の大きさに合わせて、デジカメやタブレット端末のカメラで本のページを撮影して拡大する、スキャナーのついたコピー機で拡大コピーすることも1つの方法でしょう。
【音読機能のあるアプリケーションソフトの例】「Seeing AI」Microsoft Corporation
「Seeing AI」は、iPhone・iPadで使えるアプリケーションソフトで、画像から取り込んだ情報を音声で伝えるなどのように、AIの機能で視覚の困難をサポートしてくれます。
障害を補う「本」たち
【メディアの例】
- オーディオブック(朗読CDなど)
- 大活字本
- マルチメディアデイジー
障害のある人や本を読む時間の無い人を対象として作られたメディアを活用する方法もあります。
オーディオブック
「オーディオブック」とは「聴いて楽しむ」ことを目的に作られた作品です。
耳から情報を得られるので、文字を読むストレスを感じずに本の内容に集中できるかもしれません。
記録された媒体に合わせて「朗読CD」「朗読テープ」とも呼ばれます。
使いやすい形態のものを探してみましょう!
オーディオブック(朗読CD・朗読テープ)は、図書館にも置かれていることがあります。詳しくはお住まいの地域の図書館にお問い合わせ下さい。
【商品の例】
大竹まこと『人の数だけ物語がある。ザ・ゴールデンヒストリー朗読CDブック』(扶桑社)
【商品の例】
『お話、きかせて!聴く絵本せかいどうわベスト100 朗読CD』(パンロ-リング)
子ども向けの物語は、「読み聞かせCD」という形でも販売されています。
大活字本
「大活字本」とは、障害のある人や高齢者など、通常の本の文字が小さくて読みづらい人に向けて通常の本よりもフォントサイズを大きくして作られた本です。「大活字図書」とも呼ばれています。
全巻揃えると価格が高額になってしまい、収納スペースも多く必要となることも……。
購入するかどうかは、読みやすさを確認してから検討しましょう!
オーディオブック同様に、大活字本も図書館に置かれていることがあります。※詳しくはお住まいの地域の図書館にお問い合わせ下さい。
【商品の例】
河口慧海『チベット旅行記(一)』(響林社)
大活字本については、参考元を参考にしてください。通常の本と大活字本のフォントサイズの違いなどが紹介されています。
参考元:社会福祉法人|埼玉福祉会「図書館事業部|印刷・出版課<大活字事業>」のページ
マルチメディアデイジー
【マルチメディアデイジーで作られた図書の特徴】
- 専用の機械やパソコンにソフトウェアをインストールして再生
- 目次から読みたいページに移動できる
- 音声にテキスト、画像を同期できる
- CD-ROMなどの形で記録できる
「マルチメディアデイジー(Multimedia DAISY)」とは、電子図書に設けられた国際基準のことです。発達性ディスレクシアを含め、「読む」ことが困難な人に向けて作られた図書の形です。
参考元:エンジョイ・デイジー(公益財団法人|日本障害者リハビリテーション協会)「デイジーとは」
療育で「苦手」を軽減する
【療育で苦手を経験する例】
- 特別支援学校 / 特別支援学級
- 放課後等デイサービス
- 発達障害を対象とした民間の学習塾
お子さんが発達障害である場合は、「療育」によって苦手を軽減することで本も読みやすくなるかも知れません。
「療育」とは障害のある児童などを対象にした、困難の種類に応じた解決策と将来の自立・社会参加に向けた支援で「発達支援」とも呼ばれています。
自宅での療育は「家庭療育(家庭内療育)」と呼ばれています。
公共の窓口や、お住まいの地域の療育施設などに相談してみましょう!
「放課後等デイサービス」は、子どもの最善の利益の保障を目的とした、障害のある児童が通うことのできる福祉サービスです。略称として「放デイ」と呼ばれることもあります。
子どもの居場所として保護者が子育ての悩みなどを相談可能です。
周囲にできること・困った時の相談先

身近な人が発達障害で困っている時、周囲の人はどのようなサポートができるのでしょうか。
また、困った時、本人や周囲の人はどこに相談すれば良いのでしょう?
この項目では、「本が読めない」ことへの周囲からのサポートや、相談先の1つとして「発達障害者支援センター」についての情報をお伝えします。
周囲にできるサポートは?
【周囲にできる理解の例】
- 生きづらさを軽減するための環境調整に取り組む
- 発達障害への知識を深める
- 「できない」ことを責めるのではなく、できるようになる方法を一緒に考える
- 助けを求められたら、できる範囲で協力する
- 本人の得意なことを伸ばすサポートする
発達障害の特性からの苦手による「生きづらさ」を軽減する為には、家族や周囲の人の理解も不可欠です。
環境調整に取り組む
【「本が読めない」時の環境調整の例】
- 集中しやすい環境をつくる
(カーテンで仕切るなど、読書専用の静かなスペースを設ける) - タブレット端末やパソコンが使用できる環境にする
- 注意書きなどにイラストを添える
- マニュアル等を動画や音声資料の形で作る
- 読むために必要な時間を本人のペースに合わせて設ける
「環境調整」とは、環境の改善から困りごとを減らし、負担の少ない生活を送れるように工夫することです。
発達障害の対策としての環境調整は「問題が起きる原因は本人にあるのではなく、問題を引き起こしてしまう環境の方に問題がある」とする視点から行われます。
視覚に困難のある人が眼鏡をかけるように、ADHDの人には集中しやすくなる工夫が、発達性ディスレクシアの人には読みやすくなる工夫やタブレット端末などが必要です。
本人が希望している工夫や必要物があれば、周囲もそれらを使える環境作りに協力しましょう。
無理のない範囲で互いに配慮し合えることが当たり前になり、誰もが暮らしやすい環境に近づくといいですね。
発達障害への知識を深める
【知識を深める例】
- どんな特性があるのかを知る
- 困りごとや、助けを必要としている時の応じ方を知る
困りごとを抱えている本人へのサポートには、周囲が発達障害について正しい知識を得ることも大切です。
「発達障害」という言葉は広く知られるようになってきましたが、実際にはどのようなものかを知らない人は大勢います。
困りごとは外見からはわかりにくい為、偏見や周囲の理解不足からトラブルになってしまうこともあり、度重なるトラブルの経験から鬱(うつ)病や引きこもりなどの二次障害に陥ってしまうケースも少なくありません。
また、症状や困りごとの現れ方は個人によって異なります。
一般的な知識を得ることと同時に、「この人の場合はどんな困りごとがあるのか」を知っておくと対応がスムーズになるでしょう。
発達障害についての知識は、本や動画などからも情報を取得可能です。
【本の例】
宮尾益知『LD(学習障害)の子どもが困っていること』(河出書房新社,2019.9)
【動画の例】
↓コンパクトにわかりやすく説明されている動画は、周囲の人にも見てもらいやすいかも知れませんね。
参考動画:YouTube「LD(学習障害・SLD)の特徴【発達障害】」ぽんこつニュース【発達障害&ライフハック】
困った時は「発達障害者支援センター」へ相談しよう
【相談できることの例】
- 日常生活でのさまざまな相談
(気になること、学校や職場で困っていることなど) - 発達支援に関する相談
(家庭での療育の方法など) - 就労に関する相談
(仕事での困難、就職への不安など)
発達障害からの困りごとは、専門の窓口などに相談できます。
その1つ「発達障害者支援センター」は、発達障害を持つ人や児童への支援を総合的に行う専門機関です。
各関係機関や地域と連携し、発達障害を持つ本人と家族、周囲の人達からの様々な相談に応じてくれます。
まとめ
- 「本が読めない」時は発達障害からの特性も疑う
- 原因となる特性に合わせ「集中しやすくなる工夫」や「読みやすくなる工夫」をする
- 「通常の本を読むことが困難」な人に向けて作られたメディアを活用
(オーディオブック、大活字本、マルチメディアデイジー図書など) - 療育により発達障害者の「苦手」を減らせる
- 発達障害者をサポートする人たちも環境調整や知識向上を目指す
- 困った時は「発達障害者支援センター」など第三者へ相談
本は知らない情報や物語を教えてくれる豊かで貴重な情報源です。しかし「本を読む」ことは発達障害者にとって頑張っても読めない、あるいはとても多くの頑張りが必要となる行為です。
誰もが個性に合った形で負担なく、上手に本と付き合えるといいですね。あなたやお子さんが「お気に入りの1冊」に出会えますように。
もっと詳しく・他の情報も知りたい方はこちらのサイトも参考にしてみて下さい!
↓
横浜市都筑区児童発達支援と放課後等デイサービス
運動・学習療育アップ