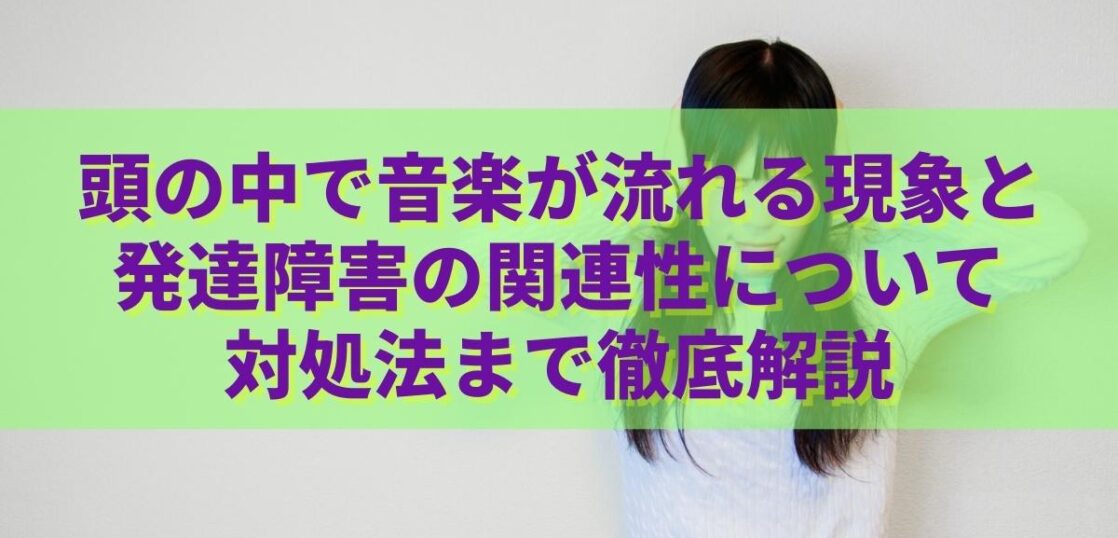皆さんこんにちは!本日も発達障害等に関する学びや情報交換の場所なることを願って投稿させて頂きます。
今日のトピックは「頭の中で音楽が流れる発達障害」についてです。
日常の中にはメディアやお店などから耳に残るメロディーがたくさん聞こえてきますが、ふと思い出して頭から離れなくなったことはありませんか?
特に発達障害があると頭の中で音楽が流れることが多く、しかも苦痛に感じやすいと言われています。
今回はこの現象の解説と対処法の説明をしていきますので、参考にできそうな箇所があればぜひ実践していただけると幸いです。
目次
発達障害に起こりやすい頭の中で音楽が流れる現象とは?

特に考えてもいないのに、しつこく頭の中で流れる音楽は「イヤーワーム」と呼ばれる現象かもしれません。
頭の中で音楽が流れるイヤーワームとは?
イヤーワームは歌や音楽などが繰り返し頭の中で流れてしまう現象のことをいい、自分で止められず強迫的に反復されるという特徴を持っています。
ただ、イヤーワームは誰でも経験することで異常なことではありません。
98%の人はイヤーワームを経験したことがあり、約90%の人は週に1回は体験するといわれています。
男女ともに同じ程度の頻度で現れますが、女性の方が続く時間が長い傾向にあるため不快に感じやすいです。
イヤーワームを直訳してしまうと「耳の虫・耳のミミズ」ですが、特に寄生虫などとは関係はないのでご安心ください。
ディラン効果
ほとんど同じ意味で「ディラン効果」というものがあり、アメリカのミュージシャンであるボブ・ディランの曲が頭から離れないことから名づけられた言葉です。
ボブ・ディランの曲の中でも「風に吹かれて」は、頭に残りやすくイヤーワームが起こりやすいといわれています。
興味のある方に向けて「風に吹かれて」の動画をご用意しました。
本当に頭から離れなくなる人もいるでしょうから、聴くかどうかの判断は自己責任でお願いしますね。
イヤーワームの原因
イヤーワームを引き起こす原因ははっきりと分かっていません。
強迫性障害の一種だともいわれていますが、現時点ではイヤーワームが起きる=強迫性障害ではありません。
不安症(不安障害)のひとつで、不安とこだわりのせいで生活に支障をきたした状態です。
頭に浮かんだことを考え続けてしまう「強迫観念」、特定の行為をしなければ気が済まない「強迫行為」を特徴とします。
例えば、ラッキーナンバーやカラーにとらわれすぎて行動が制限される、戸締りを必要以上に確認し続けるなどがあげられるでしょう。
参考元:厚生労働省 みんなのメンタルヘルス
しかし起こりやすい環境や状態、心理状況などはいくつかあるとされています。
【イヤーワームが起きやすい状態一例】
- 頭をあまり使っていないとき
- 単調な作業をしているとき
- ストレスがあるとき など
流れる音楽はその記憶に関連する感情や風景、体験、匂いなどが関係している可能性が高いです。
ただどんなジャンルの曲でも起こりえるため、日頃から触れている音楽でもイヤーワームは起きる傾向があります。
曲・音楽以外でもイヤーワームは起きる可能性があります。
例えばファミリーマートの入店メロディや、マクドナルドのポテトが揚がるときのアラーム音のように、ごく短いフレーズでもイヤーワームになる可能性があるのです。
頭の中で音楽が流れたときの対処方法

短時間で自然と消えてしまえば特に問題のないイヤーワームですが、苦痛なほどしつこく繰り返されるときのために、4つの対処方法をご紹介しましょう。
ポイントは「別の作業に集中して、無意識で起きるイヤーワームを打ち消す」です。
1.ガムを噛んでみよう
ガムを噛むなどして口を動かし続けると、意識が分散して記憶や音を思い出しにくくすることができます。
また噛む効果にはストレスの緩和も期待ができるので、イヤーワームが止まることがあるのです。
2.頭を使う何かに集中してみよう
基本的にあまり頭を使っていない状態で起こりやすいため、少し考えさせられるものに挑戦すると落ち着くことがあります。
- アナグラム
- クロスワードパズル
- 計算
- ゲーム など
言葉を並び替えて別の意味を作る遊びです。
例えば「東京(とうきょう)」→「教頭(きょうとう)」といった感じで作り変えます。
難易度が高すぎても低すぎても効果が薄いと言われていますので、5文字程度の言葉が丁度良いでしょう。
人によって最適な難易度や集中のしやすさが違いますので、色々と試してみると良いでしょう。
発達障害のある子どもの場合はプロのスタッフが付き添ってくれるサービスもあり、イヤーワームから気をそらしやすい環境の提供も可能です。
興味のあるかたはこちらもチェックしてみてください。
3.頭に流れている音楽もしくは別の曲を聴いてみよう
音楽の一部のみが頭の中で繰り返されてしまい集中できない場合は、頭に流れている曲をすべて通して聴いてみましょう。
通して曲を聞けば、同じフレーズのループから抜け出せる場合があるからです。
別の手段として、自分の好きな耳に残る音楽を新たに聴いて、続いていた曲を上書きする方法もあります。
上書きすることで新しいイヤーワームが発生する可能性もあるので、気分転換の意味合いが強くなるかもしれません。
4.病院受診もひとつの手段
不安症の中の強迫性障害が原因のひとつだと考えられていますので、もしも原因が精神疾患によるものであれば治療で緩和できる可能性があります。
受診する病院としては
- 精神科、神経科
- 心療内科
- メンタルクリニック
- 発達障害であれば小児科、小児精神科
などに行くことでスムーズに対応してもらえるでしょう。
発達障害とイヤーワームの関連性
誰にでも起こりやすいイヤーワームですが、発達障害があるとより出現しやすくなります。
次のツイッターでは興味深いアンケートがとられていました。
内容としては、イヤーワームが起きるかどうかを発達障害の有無で分けてアンケート結果ををパーセントで表示したものです。
割合を計算した結果、発達障害の無い方は約73%、発達障害の方は約81%の方が脳内で音楽が流れると回答しています。
回答率としては非当事者の方が多いので正確なデータとはいえないものの、発達障害の方がイヤーワームを起こしやすいのだと推測できます。
発達障害の方はイヤーワームの不利益を被りやすい?
発達障害の特徴を知れば理由が明確になります。症状についても少しおさえておきましょう。
定型発達の人に比べ発達障害の方はややイヤーワームが起こりやすいです。
イヤーワームが起こりやすいだけでなく集中力が欠けやすい結果、発達障害の人は不利益を被り苦痛に感じやすいのでしょう。
発達障害の症状別に特徴が異なり、症状は大きく3つに分けています。
- 自閉症スペクトラム障害(ASD)
- 注意欠陥多動性障害(ADHD)
- 学習障害(LD)
しかし未だ解明されていない部分が多くあり、明確には判明していません。
上記のうち自閉症スペクトラム障害と注意欠陥多動性障害が関係しやすいと考えられています。
自閉症スペクトラム障害(ASD)
社会的なコミュニケーションを苦手とし、行動や興味などのこだわりが強いことが特徴的です。
- 言葉の遅れやオウム返し
- 会話が成り立たない
- 人に対しての関心が低い
- 感覚過敏や鈍麻
- 興味がとても狭く限定的
- 同じ行動を繰り返し自分の世界に入りやすい など
触覚、視覚、聴覚などの刺激に対してとても敏感になっている状態を感覚過敏、逆に鈍いと感覚鈍麻になります。
下着の材質によって不快感が出たり、日常の音がストレスになる、痛みや暑さ・寒さに鈍感になるため、怪我や熱中症などに注意が必要です
さまざまな症状や個人差はありますが、基本的には対人関係が困難になりやすいでしょう。
特に行動の繰り返しやこだわり、自分の世界に入るといった点がイヤーワームにつながりやすいといえます。
独り言も多く、その一部はイヤーワームが関係している場合もあるようです。
さらに、ストレスに対しての耐性が低く二次障害も起こしやすいです。精神的な不調がより頭の中の音楽を強める可能性があるでしょう。
発達障害の症状により起こる対人関係の難しさや生活の中でのストレスが原因で、二次的に起きる不調を二次障害といいます。
抑うつや不安症(不安障害)などが代表的です。
参考元:厚生労働省 e-ヘルスネット
イヤーワームの原因でもお伝えした「強迫性障害(不安症/不安障害)」にもなりやすいといわれています。
別途詳しい説明がありますので、併せてご覧ください。
注意欠陥多動性障害(ADHD)
年齢の割に集中力がなく気が散りやすい状態(不注意)で、じっとできずにすぐ動いてしまう(多動・衝動性)という特徴があります。
- 周りの刺激にすぐ反応して気が散りやすい
- 話を聞かない
- 順序だてた行動ができない
- 他人の邪魔をしてしまう
- 感情やストレスコントロールができない など
好きなことに対しては集中力が続きやすいという面もありますが、自分がうまくできない点の自覚もあるため、悩みやすくネガティブになりやすい部分もあるでしょう。
自閉症スペクトラム障害と同じく、ストレスや二次障害のリスクも高く、イヤーワームを起こす心理状態になりやすいです。
さまざまな音に気が向きやすく、知らず知らずのうちに頭に残ってしまっている場合もあるでしょう。
発達障害はさまざまな症状を合併している場合が多く、単体で現れることは稀です。
ASDとADHDを併せ持つ方がイヤーワームについて説明と体験談です(約9分程度)。分かりやすい内容ですので参考にしてみてください。
イヤーワーム以外の頭の中で音楽が流れる原因
発達障害有無にかかわらず多くの人々が体験するイヤーワームに対して、特定の病気に起こる音楽幻聴という症状があります。
原因となる病気は大きく2つに分かれ、現れる症状にも違いがあります。
- 統合失調症などの精神疾患
- 難聴などで起こる耳鳴り
統合失調症での音楽幻聴
統合失調症とは精神疾患の一種で、以前は精神分裂病とも呼ばれていました。
脳の神経伝達物質のバランスが崩れた状態といわれていますが、はっきりとした原因は分かっていません。
幻覚や幻聴、妄想などの陽性症状と無関心や意欲低下などの陰性症状がみられる疾患です。
統合失調症の方の中には、幻聴の中に音楽幻聴が含まれ、音がない状態でも歌やメロディが聞こえるように感じます。
参考元:厚生労働省 e-ヘルスネット、日本アイソトープ協会(統合失調症における音楽幻聴の責任部位)
耳鳴りでの音楽幻聴
耳鳴りの症状のひとつで、高音や低音などの音が聞こえるため音楽幻聴と呼ばれています。
実際の音楽や聴いたことのあるメロディが聞こえるわけではなく、苦痛を伴うこともあるでしょう。
音が聞こえにくくなる難聴を合併する場合が多く、原因についての詳細は解明されていません。
頭の中で音楽が流れて困ることは?

「頭の中で音楽が流れることがそんなに困るのか?」「イヤホンで音楽を聴くようなものじゃないの?」とイヤーワームにポジティブな疑問を持つ方もいるようです。
しかし実際は楽しい事ではなく、イヤーワームを患っている人がツイッターで苦しみを呟いています。
苦労する点は主に以下の4点が見受けられます。
- 集中ができなくなる
- 眠れなくなる
- 自分が聞きたいわけではない
- ストレスに感じる
自分で調節できない点がストレスになるようです。自分で調整できないため、イヤーワームが長時間続いてしまい悪循環に陥ってしまいます。
発達障害の当事者にイヤーワームが起きると?
イヤーワームと発達障害の特性が合わさると、上述した苦労がさらに強まると考えられます。
一般的に発達障害の方は注意を複数に向けるのが苦手なため、以下のリスクを背負います。
- 自分の世界に入り込み周りに反応できなくなる
- ひどく注意が散漫になる
- 事故や怪我のリスクが高まる など
必要なことができなくなるだけではなく、自身が危険にさらされる可能性もあるでしょう。
持続時間が長期化しやすい点も相当なストレスになります。
「頭の中で音楽がなっているだけだし…」などと甘く見ず、上で説明した対処を試していただき、ストレスが強い場合は早めに受診も視野に入れてくださいね。
イヤーワームは音楽の聴きすぎに注意
近年の睡眠の質に関する研究結果により、音楽を聴きすぎる人は「イヤーワーム」に陥りやすく、質のいい睡眠を得られないという結果を発表しました。
研究結果ではキャッチャーなメロディ―の鳴り響く音楽だけなく、インストゥルメンタルの音楽でも睡眠の質が低下したとの指摘もあります。
つまり、音楽の内容よりも音楽を長時間聴く行動に問題があるようですね。
イヤーワームに陥らないためには以下の手段を推奨されていますので、できる範囲で試してみてはいかがでしょうか。
- 普段から音楽を聴く場合は、音楽を聴かない休憩時間も共に設ける
- 就寝前にテレビやゲームなど、睡眠を妨げる作業を行わない
- 問題解決やタスク管理など思考や精神を伴う作業を行い、イヤーワームへの反応を避ける
参考元:Why Music at Bedtime Might Not Be a Great Idea | HealthDay
まとめ
発達障害との関連も深い頭の中で音楽が流れる現象は「イヤーワーム」と呼ばれるものでした。
当事者でなくとも体験することが多く、集中力や睡眠に影響を与えるため悩まされている方も多くいます。
対処法はいくつかありますが、根本原因は解明されていないため、生活に支障をきたすようであれば一度病院に相談した方が良いかもしれません。