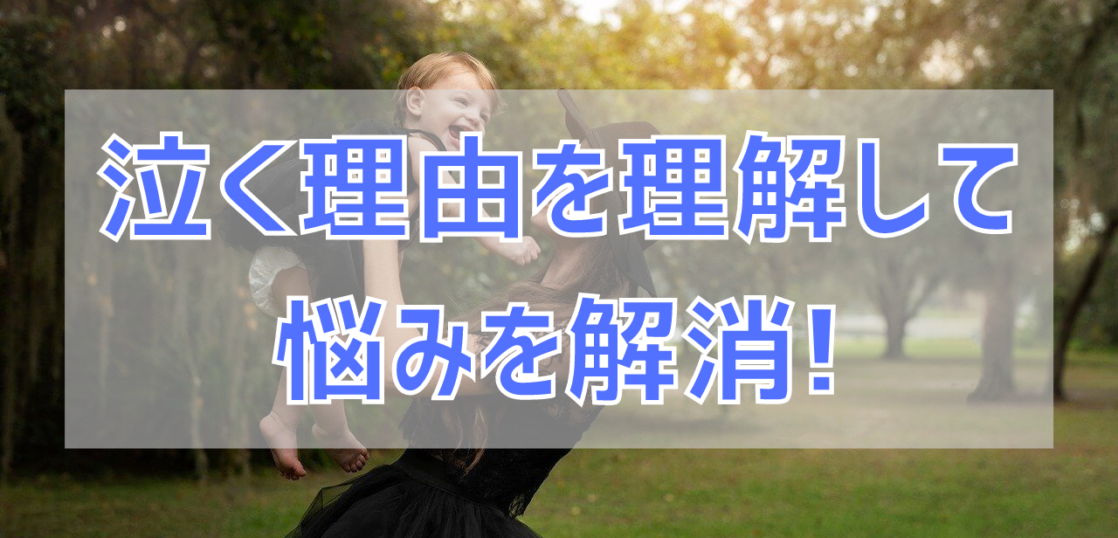皆さんこんにちは!本日も発達障害等に関する学びや情報交換の場になることを願って投稿させて頂きます。今日のトピックは「発達障害 すぐ泣く」についてです。
「自分の子どもが最近よく泣くのはなんでだろう?」「発達障害とすぐに泣くのは関係あるの?」「子どもが泣いている姿を見ると自分も泣きたくなる」などの様々な悩みがあると思われます。
目次
発達障害の子どもがすぐ泣く理由とは?

子どもは自分の不都合を伝えるときや困っているときに、周りに知らせるために泣くという手段を使っているのです。
なぜなら子どもというのはまだ感情のコントールがうまくできず、言葉の知識が大人と比べて少ないからです。
子どもが泣き出した理由が分かれば事前に対策を打つことが可能になり、保護者の負担を減らすことができます。
なぜ泣き出すかを理解できていない状態は保護者にとってもストレスになります。
逆に何に悩んでいるのかをしっかりと把握したり周りと共有することで、つらい思いも楽になることもあります。
どんな時に子どもが泣いているのかを理解する

ある日子どもが夢中になって積み木で遊んでいて夕食の時間になったので、積み木を片付けるために取り上げたら、泣き出してしまったとします。
積み木を取られたとき子どもは「まだ積み木で遊びたい!!」という自分の意志を伝えるために泣くという行動を取ります。
積み木を取り上げた例は誰にとっても分かりやすいかも知れませんが、「なぜ泣いたのか?」の原因が分からない場合もかなり多いと思います。
例えば飲み物をあげたら急に子どがが泣き出したとします。いつも喉が乾くタイミングであげたのに「なんで?」となぜ泣いたのかは理解ができないと思います。
飲み物をもらって泣いた子どもは飲み物が入っている容器が、いつもとは違うというのが原因で泣くこともあるのです。
泣き出す理由は子どもによって様々ですが、注意して子どもに目を向けてどんなときに「泣き出したのか?」を理解することが重要です。
子どもが泣く回数を減らそう!

では泣く回数を減らすために2つの視点から考えていきます。
・子どもが泣かないための防止策
・子どもが泣いてしまったときの対処法
子どもが泣かないための防止策
対策としては子どもへ「変化をなるべく与えない」ことであると考えます。
泣く原因は様々ですが、子どもは変化(特に急な変化)を極端に嫌い、いつも通りが好きな傾向があります。
ここでは三つの防止策について説明します。
・事前に予告する
・いつも通りを意識する
・保護者のストレスを減らす
事前に予告する
積み木を取り上げた場合だと、遊んでいたのにいきなり積み木を取り上げられて子どもの手元から積み木がなくなっています。
このとき積み木を持っている状態(自由に遊べる)から持っていない状態(自由に遊べない)に変化したことに、不安を抱いています。
対策としては積み木を取り上げる前に「あと30分でお風呂だよ」「積み木で遊んだ後はお掃除だよ」などを事前に予告しておく必要があります。
事前告知によって心を徐々に切り替える時間を作ることが大切です。
いつも通りを意識する
飲み物の例で言うと子どもはいつも使っているものに、かなりの愛着を持っています。外出する時にはいつも使っているものを持っていくことが対策となります。
また子どもとの散歩を習慣にしている人は同じ道を歩くなどの対策も必要になります。
子どもが泣く要因はいつもと違う変化が起きているということが多いので、事前に今日1日のスケジュールを確認し、なるべく変化が起きないように事前準備をしましょう。
保護者のストレスを減らす
保護者が悩みを一人で抱え込むことは危険です。保護者の方の辛い状況というのはお子さんにも伝染し、さらに泣く回数が増えて、悪化することもあります。
まずは周りに相談することが大切です。周りに相談する方がいない場合は「小児科」に相談するのもありです。
症状によっては県や市が運営する「発達障害者支援センター」に相談するのもいいと思います。同じようなな悩みを持つコミニュティなども紹介してもらえます。
また最近では子どもについての悩んだときや、ストレス発散法を配信している保護者の方もいます。視聴して参考にしたり、コメントして悩みを共有するのも一つの手だと思います。
一人で抱え込まずにまずは自分の負担を少なくし、子どもと快適な生活を送れるようにしましょう。
子どもが泣いてしまったときの対処法
ですが対策をしっかりしても子どもが泣き出してしまうことがあると思います。
そんなときに注意することは泣き終わるまでしっかり待つことです。
子どもが泣き出したらお菓子をあげたり、取り上げたものを返したりご褒美をあげる人がいます。
しかしご褒美をあげるのはとても良くないです。なぜなら泣けば「自分の要求が通る」と感じてしまうからです。
泣くことで要求が通ると分かると泣くことがクセになり、不都合があると泣き出すようになります。なので泣き出した場合は、泣き止むまで見守ることを意識することが大切です。
公共の場で泣き出してしまったら一度、人がいないところに移動して泣き止むまで待ってあげます。
そして泣き止んだときには子どもを褒めて上げるのが重要です。褒めることで少しずつ、泣き止むまでの時間を短くすることができます。
まとめ
子育てには悩みがつきものです。
中でも子どもがすぐに泣くというのは保護者、子どもどちらにとってもつらいものです。泣く理由を正しく理解し、できる限り対策を打てるようにしましょう。
また保護者の方は一人で抱え込まずに悩みを共有することで少しでも負担を少なくすることが大切です。
保護者が子どもと自分自身の両方を理解することが重要であり、楽しい生活の第一歩となります。