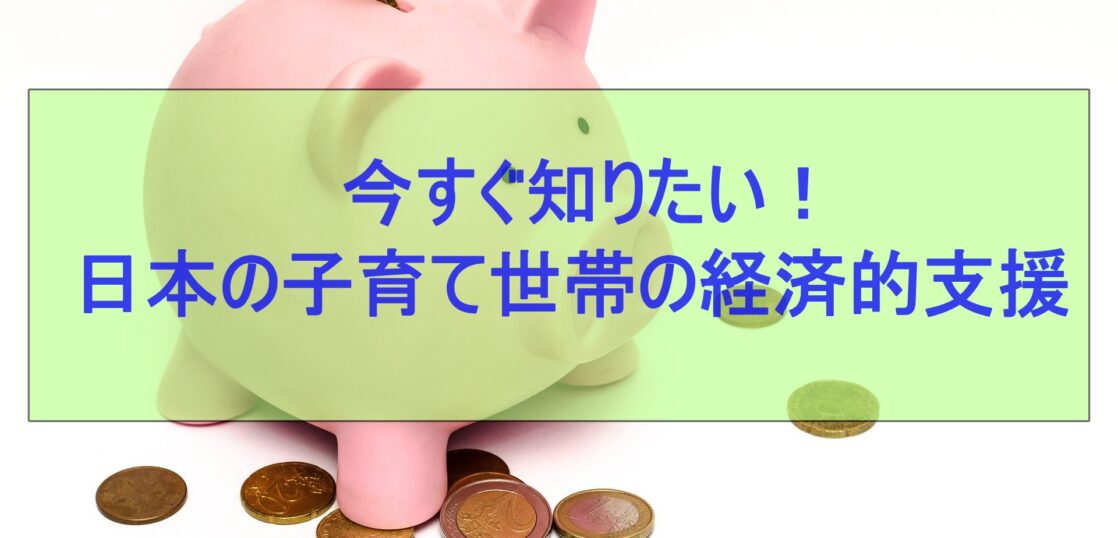皆さんこんにちは!本日も発達障害等に関する学びや情報交換の場になることを願って投稿させて頂きます。今日のトピックは「子育て 経済的支援」についてです。
子育てはお金がかかりますよね。皆さんは子ども1人あたりどのぐらいのお金がかかるかご存じですか?
目次
これだけは知っておきたい!子育て世帯への経済的支援

主に行われている経済的支援を紹介します。
児童手当
児童手当とは、子育て世帯の生活と子ども達の成長をサポートする目的で支給されます。支給対象は0歳~中学校卒業まで(15歳になった最初の3月31日まで)です。
▼各年齢の児童手当の支給月額
| 年齢 | 支給月額 |
| 0~3歳未満 | 10,000円 |
| 3歳~小学校終了まで(第1子及び第2子の場合) | 10,000円 |
| 3歳~小学校終了まで(第3子以降の場合) | 15,000円 |
| 中学生の場合 | 10,000円 |
所得制限もあるため、自分の世帯がもらえるかどうか又はどのくらいもらえるか知りたい時に、自分で所得制限の計算をすることができます。
▼こちらの動画では所得制限の計算方法をご紹介されています。
受給方法は、出生日の翌日から15日以内に、現住所の市町村への申請する必要があります。(月末近くに出生した場合でも、その翌日から15日以内に申請をすれば、申請月から支給が可能です。)
また、児童手当を継続して受給するためには、毎年6月に現況届の提出が必要です。
▼こちらの動画では、児童手当の申請について説明しています!
幼児教育・保育の無償化
2019年10月から始まりました。幼稚園、保育所認定こども園、地域型保育、企業主導型保育を利用する3歳から5歳までの全ての子どもおよび0歳から2歳の住民税非課税世帯の子どもの利用料が無償化される制度です。
ただし、子ども・子育て支援新制度に移行していない幼稚園、認可外保育施設等、幼稚園の預かり保育については、上限が決まっております。
また、障害児が通う施設も3歳から5歳までは無償化の対象です。
▼各施設による幼児教育・保育の無償化一覧
| 施設 | 対象者 | 補償金額(月額) |
| 保育所・認定こども園・地域型保育・企業主導型保育 | 0歳児~2歳児(住民税非課税世帯)、3~5歳児 | 全額 |
| 幼稚園 | 満3歳児~5歳児 | 全額 |
| 子ども・子育て支援新制度に移行していない幼稚園 | 満3歳児~5歳児 | 27,000円 |
| 認可外保育施設等 | 0歳児~2歳児(住民税非課税世帯) | 42,000円 |
| 認可外保育施設等 | 3歳児~5歳児 | 37,000円 |
| 幼稚園の預かり保育 | 満3歳児(住民税非課税世帯) | 16,300円 |
| 幼稚園の預かり保育 | 3歳児~5歳児 | 11,300円 |
| 障がい児通園施設等 | 3歳児~5歳児 | 全額 |
子ども医療費助成
子ども医療費助成とは、通院や入院による保険診療の自己負担分を軽減してくれる制度です。
全国の都道府県・市区町村で実施されていますが、各自治体によって対象年齢や所得制限の有無などが違います。
下記のサイトで、お住まいの自治体が何歳まで助成してくれるかどうか知ることができます。
ひとり親世帯への経済的支援

続いてひとり親世帯への経済的支援を紹介します。
▼実際に受給できて助かるという声もあります。
児童扶養手当
国が行っている支給制度です。離婚、死亡により、母子家庭・父子家庭になった場合や、父母に重度の障害がある場合に、児童を扶養している父・母または養育者に支給されます。
ただし1人で子どもを育ていることが条件のため、児童養護施設に入所している子ども、父または母の配偶者(事実上の配偶者を含む)に養育されている場合は支給を受けることができません。
支給対象は0歳~18歳まで(18歳になった最初の3月31日まで)です。
▼児童扶養手当の金額
| 人数 | 全部支給 | 一部支給 |
| 1人 | 43,160円 | 43,150円~10,180円 |
| 2人目 | 10,190円 | 10,180円~5,100円 |
| 3人目以降1人につき | 6,110円 | 6,100円~3060円 |
また、児童手当には「所得制限限度額」という所得の限度があります。
▼ひとり親の所得制限限度額
| 子どもの数 | 全部支給の所得制限限度額 | 一部支給の所得制限限度額 |
| 0人 (前年度末に子どもが生まれていないケースなど) | 49万円 | 192万円 |
| 1人 | 87万円 | 230万円 |
| 2人 | 125万円 | 268万円 |
| 3人 | 163万円 | 306万円 |
| 4人 | 201万円 | 344万円 |
| 5人 | 239万円 | 382万円 |
▼孤児の養育者などの所得制限限度額
| 子どもの数 | 所得制限限度額 |
| 0人 | 236万円 |
| 1人 | 274万円 |
| 2人 | 312万円 |
| 3人 | 350万円 |
| 4人 | 388万円 |
| 5人 | 426万円 |
児童扶養手当を受給するためには、居住地の市区町村の窓口へ申請しましょう。また受給を継続するためには、毎年8月に現況届の提出が必要です。
▼こちらの動画では、児童扶養手当の申請について説明しています!
住宅手当
ひとり親世帯で20歳未満の子供を養育しており、かつ家族で住むために住宅を借りて、月額10,000円を超える家賃を払っている人を対象としている制度です。
この制度は都道府県や市区町村によって異なり、中には実施していない地域もあるため、お住まいの役所に聞くことをお勧めします。
またこちらのサイトでは、住宅手当が受けられる自治体が載っているため、居住の市区町村が受けられるかどうかを確認することができます。
ひとり親世帯の医療費助成制度
ひとり親世帯を対象に、保護者や子どもが通院や入院した際に、保険診療の自己負担分を軽減してくれる制度です。
自治体によって助成内容が違うため、お住まいの市役所に聞くことをお勧めします。
支給対象はひとり親家庭で、0歳~18歳まで(18歳になった最初の3月31日まで)の子どもとその子どもを育てる保護者です。
またこの制度も所得制限があり、限度額を越えてしまうと利用ができません。
▼ひとり親と孤児の養育者の所得制限限度額
| 扶養親族などの人数 | ひとり親世帯の所得 | 孤児の養育者 同居の扶養義務者の所得 |
| 0人 | 192万円 | 236万円 |
| 1人 | 230万円 | 274万円 |
| 2人 | 268万円 | 312万円 |
| 3人以上 | 1人増えるごとに38万円が加算される。 | 1人増えるごとに38万円が加算される。 |
障害のある子どもに対する経済的支援

最後に障害のある子どもがいる世帯への経済的支援を紹介します。
特別児童扶養手当
こちらの制度は国が行っており、精神又は身体に障害がある20歳未満の子どもがいる世帯に支給されます。
支給条件が定められており、具体的な基準については東京度都福祉保健局のサイトで確認できます。
支給金額は子どもの人数と、障害の度合いによって変わります。
▼特別児童扶養手当の支給金額(令和2年4月より適用)
| 子どもの人数 | 障害等級1級 | 障害等級2級 |
| 1人 | 52,500円 | 34,970円 |
| 2人 | 105,000円 | 69,940円 |
| 3人 | 157,500円 | 104,910円 |
障害等級1級
身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状によって、日常生活ができない程度のもの。 (他人の介助を受けなければ自分の身の回りのことができない程度)
障害等級2級
身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が、 日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの。 (必ずしも他人の助けを借りる必要はないが、日常生活は極めて困難で労働により収入を得ることができない程度)
引用元 2022年4月6日障害年金サポートサービスより抜粋
そして所得制限があり、受給者又はその配偶者や扶養義務者の所得限度額を越えてしまうと利用ができません。
▼受給者本人と受給資格者の配偶者及び扶養義務者の所得制限限度額
| 扶養親族などの数 | 受給資格者本人 所得額 | 受給資格者の 配偶者及び扶養義務者所得額 |
| 0人 | 459.6万円 | 628.7万円 |
| 1人 | 497.6万円 | 653.6万円 |
| 2人 | 535.6万円 | 674.9万円 |
| 3人 | 573.6万円 | 696.2万円 |
| 4人 | 611.6万円 | 717.5万円 |
| 5人 | 649.6万円 | 738.8万円 |
特別児童扶養手当をもらうには、居住地の市区町村の窓口へ申請しましょう。また受ける続けるには、毎年8月に現況届を提出しなければなりません。
▼こちらの動画では、特別児童扶養手当の申請について説明してしています!
▼特別児童扶養手当についてもっと知りたい方はこちらのサイトをご覧ください。
障害児福祉手当
国の制度で、身体的又は精神的な重度の障害があるために日常生活を自分の力で生活することができず、常に介助を必要とする20歳未満の子どもがいる世帯に支給されます。
支給金額は一貫して月額14,880円です。(令和2年4月より適用)
受給者又はその配偶者や扶養義務者の所得限度額を越えてしまうと、限度額を超えてしまうと受給されません。
▼受給者本人と受給資格者の配偶者及び扶養義務者の所得制限限度額
| 扶養親族などの数 | 受給資格者本人 所得額 | 受給資格者の 配偶者及び扶養義務者所得額 |
| 0人 | 360.4万円 | 628.7万円 |
| 1人 | 398.4万円 | 653.6万円 |
| 2人 | 436.4万円 | 674.9万円 |
| 3人 | 474.4万円 | 696.2万円 |
| 4人 | 512.4万円 | 717.5万円 |
| 5人 | 550.4万円 | 738.8万円 |
障害児福祉手当を受けるには、居住地の市区町村の窓口へ申請しましょう。また、継続してもらうには、毎年8月に現況届を提出しなければなりません。
▼こちらの動画では、障害児福祉手当の申請方法について説明しています!
まとめ
今回は日本の子育て世帯への経済的支援について紹介しました。
ほとんどの制度は役所の窓口へ申請する必要があるため、忘れないように手続きしましょう。また、受給の対象になるかどうか不安な場合は、役所へ確認しに行くことをお勧めします。
今回紹介した経済的支援以外にも自治体独自で行っているサービスもあるため、自治体のホームページで調べたりしてみて下さい。