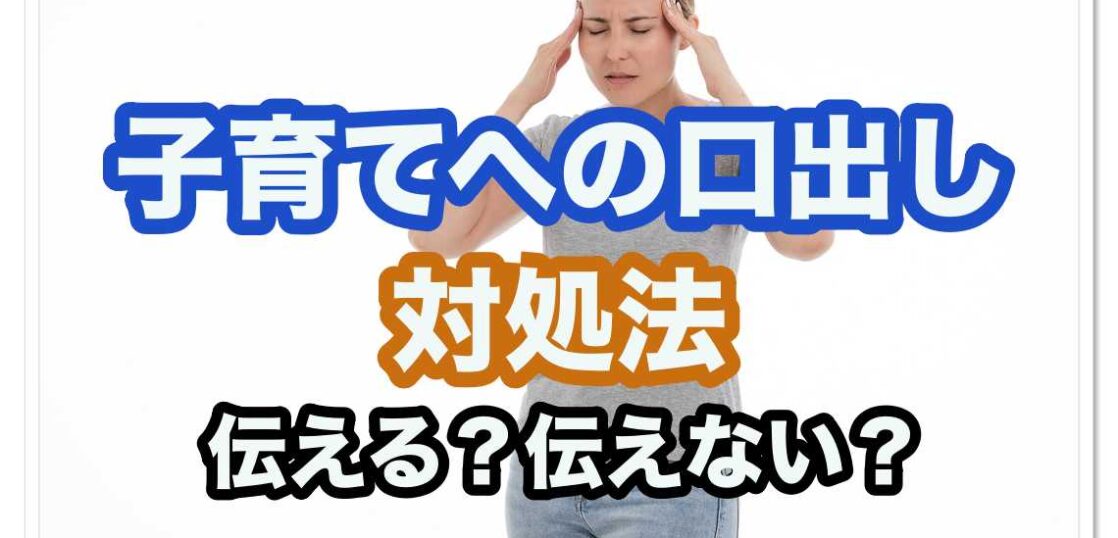皆さんこんにちは!本日も発達障害等に関する学びや情報交換の場になることを願って投稿させて頂きます。今日のトピックは「子育て 口出し」についてです。
子育て中の口出しにストレスを感じている方は多いようです。
「口出しがつらいことを伝えた方がいいのかな…」
「相手も悪気はないのだし聞き流した方がいいよね…」
など、悩んでしまいますよね。
ということで今日は子育てへの口出しに関する対処法を解説いたします。
目次
子育てへの口出しをストレスに感じた場合の対処法

子育てへの口出しにストレスを感じる場合、相手にどのように伝えるか、あるいはどうやって気にせずやり過ごすか、悩んでしまうこともありますよね。
ここでは以下の項目について解説します。
- 相手に気持ちを伝える場合【伝え方&対処法3選】
- 相手に気持ちを伝えない場合【考え方&対処法3選】
1.相手に気持ちを伝える場合の伝え方&対処法3選
相手に気持ちを伝える場合の3つの対処法をご紹介します。
実の両親には自分で伝え、義理の両親には夫や妻に伝えてもらうのもおすすめですよ。
子育てへの思いや考えを共有する
直接に口出しへのストレスを伝えるのではなく、視点を変えて話し合う方法です。
「考え方は違うけれど子どもを大切に思う同じ立場の者同士」という方向性を意識しながら話してみましょう。
- 口出しをしてくる相手に「子どもにどんな大人になって欲しいと思ってる?」などの質問をして相手の思いを知る。
- 「私(私達夫婦)は子どもがこんなふうに育ってほしいと思っていて、それを見据えて今こんなことをしている」という思いや考えを話す。
- 「できれば皆で方針を共有して同じ目的に向かって子どもを見守っていきたい」と伝える。
思いや考えを共有することで、同じ目的に向かって子どもを見守れます。
また、時々ズレてもその都度修正しやすくなります。
「本当に困っている時は助けてほしい」と伝える
子育てへの口出しにストレスを感じている場合で、子育てへの思いや考えの共有が難しい場合はどうでしょうか。
子育ては子どもの親である夫婦のものですので、夫婦の考えを優先しましょう。その場合は以下のように伝えてみましょう。
▼【伝え方の一例】
「心配してくれてありがとう。けれど30年前のお父さんやお母さんが子育てをした時代と今の時代では子育てに対する考え方や子育てをする環境は大きく違う。私達なりに夫婦で力を合わせて精一杯やっているから温かく見守って欲しい。そして本当に困っている時は助けてほしい。」
お互いの価値観などの違いを認め、口出しがストレスになっていることをやんわりと伝えつつ、見守りや手助けを依頼することで協力関係はキープします。
思いきってはっきり伝える
子育てへの口出しにストレスを感じていることをはっきり伝えることで関係が改善されるケースもあります。
▼【伝え方の一例】
「子どものことは親である私達が一番考えている。口出しはしないでほしい」
お互いの性格を見極める必要はありますが、はっきり伝えたほうが伝わりやすく、お互いに気持ちよくやれる場合もあります。
ここでも「子どもを大切に思う気持ちは皆同じで、感謝している」というベースの部分を伝えるなどアフターフォローがあるといいかもしれません。
2.相手に伝えない場合の考え方&対処法3選
毎回話し合ったり気持ちを伝えるのは難しいですよね。
相手に伝えない場合には「聞き流す」「考え方を変える」「距離をとる」などの対処法があります。
聞き流す
子育てへの口出しは無理してすべて聞くことはありません。
「そういう考えもあるんですね」とサラリと受け流してしまいましょう。
また「役に立ちそうなものだけ聞いておく」というように取捨選択するのもいいですね。
▼こちらは子育てへの口出しにも十分参考になる動画です。「口出しをスルーする技術」について詳しく解説されていますよ。
相手が何も考えずに発言していることも多々あります。「そういう考えもあるんですね」と受け流したり、役に立つ情報だけ取捨選択して、聞き流してしまうのもおすすめです。
考え方を変えてみる
子育てへの口出しがストレスになっている場合であっても、「相手にこちらの気持ちを分からせよう」とするのは難しい場合があります。
そういった場合には「お互いの意見や価値観の違いを受け入れてしまった方が楽だし早い」と考え方を変えることがおすすめです。
ましてや親世代との相違は30年分あるわけですから、理解し合えない方が自然なのです。価値観ってけっこう強固です。
「わかってほしい」「それくらいわかるはず」という思いは誰にでもあると思いますが、基本的には親子でも夫婦でも親友でもひとりひとり違う人間です。
最初のうちは慣れないかもしれませんが、「わかり合えないのが当然!」と分かり合えないこと自体を受け入れてしまうのもおすすめです。
距離を置く
状況によっては、口出しをしてくる相手としばらく連絡を取らないなど、距離を置くことでストレスを少なくする必要があります。
口出しの域を超える強い干渉の場合や、積み重なったストレスで心が不安定になっている場合などには、自分の心を守る必要があるからです。
そうした場合にはまず自分の心を休め、子どもが健全に育つ環境をキープすることを優先してくださいね。
心が不安定になるなど、口出しの相手と関わることによるストレスが大きい場合は、まず心を休めることを優先し距離を置くことも大切です。
発達障害への不理解がある場合は

動画や記事や本を一緒に見ることで理解を深めることもおすすめです。
▼神奈川県公式チャンネルです。発達障害の特性や接し方、発達障害のある人の気持ちがわかりやすく説明されている他、支援機関についても紹介されています。
▼発達障害を持つ子どもへの接し方のポイントがまとめられている記事です。
▼また、理解してもらうことが難しそうな場合や、発達障害の子どもを持つ保護者と話したいときなどにはこちらの記事を参考にしてみてください。発達障害カフェの情報や相談先についても解説されています。
▼以下のような本も参考になります。
| 著者名 | 小林みやび |
| 発売日 | 2014年04月15日頃 |
| 価格 | 1,540円(税込)送料無料 |
| 内容紹介 | 発達障害の子どもの母として、先輩ママとして、学校で学習支援をする支援者として、保護者が知っておきたい情報を凝縮。困っている子どもとの接し方、教師とのかかわり方、療育の考え方など、保護者と子どものためのアドバイスが気持ちをらくにする。 |
| レビュー | ・こんな本が読みたかった! 私が普段子どもたちと接したり、子どもたちのことで関係機関とやりとりをする時に感じていたことをまさに代弁してくれています。 ・徹底した当事者目線の本で、まさに「保護者による保護者のための本」だった。 実際に用いた支援ツールも参考になる。気になった行動記録シートとやることカードは早速導入してみようと思う。 ・「パソコンやタブレットは将来的に発達障害のある子どもの味方になってくれるツールだと思っているので、けっこう早くから触らせていた」というくだりになるほど! 保護者にもクールダウンが必要、など、辛い思いをしている保護者に伝えてあげたいことがたくさんあった。 |
親から子どもへの口出しについて

そんな時は以下に紹介するアドバイスや動画も参考にしてみてください。
▼白梅学園大学学長で教育学が専門の汐見稔幸さんは以下のように述べられています。
「指示」「命令」「禁止」の言葉が多いと、子どもは自分で考えて、どっちにしようかなと考える余地がありません。
中略
例えば、「あと5分?」「あと10分?」という風に「提案」「依頼」するかたちで子どもに聞いてあげると、子どもは自分で選んで答えます。このように、子どもが自分で考えて選択すれば、意外と子どもは言うことを聞きます。
「指示」「命令」「禁止」から、「提案」「依頼」に言い方を変えることは、慣れるまでは時間がかかると思います。しかし、時間をかけてでも変えていくと、子どもは自分に任されることが増えていくので、親の言うことを聞くことが多くなります。
引用元:NHKすくすく子育て情報
ただでさえ大変な子育ての中で見守るということは相当の忍耐を要しますが、子どもは口出ししないで見守っていると「思っていたよりはできる」「子どもなりに一生懸命考えてやっている」ことに気づきます。
今は大変ですが、将来主体性を持って生きる大人にするためには、少し見守ってあげることも大切ですね。
▼もし、過干渉かな?と心配になった場合には以下の動画も参考にしてみてください。
まとめ
今日は子育てへの口出しに対する対処法をご紹介しました。
- 子育てへの口出しがストレスになっている場合は、子育てへの思いや考えを共有してみましょう。
- そうした話し合いが難しい場合は自分に合った方法で気持ちを伝え、子育ての協力関係はキープしましょう。
- 気持ちを伝えない場合には、聞き流す・考え方を変える・距離を置くといった対処法が有効です。
- 子どもが発達障害の場合には動画や記事、本を使って知識を共有することもおすすめです。
- 特性への理解が難しい場合は発達障害カフェなどで思いを共有したり、相談機関へ相談してみましょう。
- 親から子どもへの口出しの場合は、できるだけ子どもを見守ることを意識しましょう。
今日の記事が少しでも皆さまのストレス軽減のお役に立てれば幸いです。