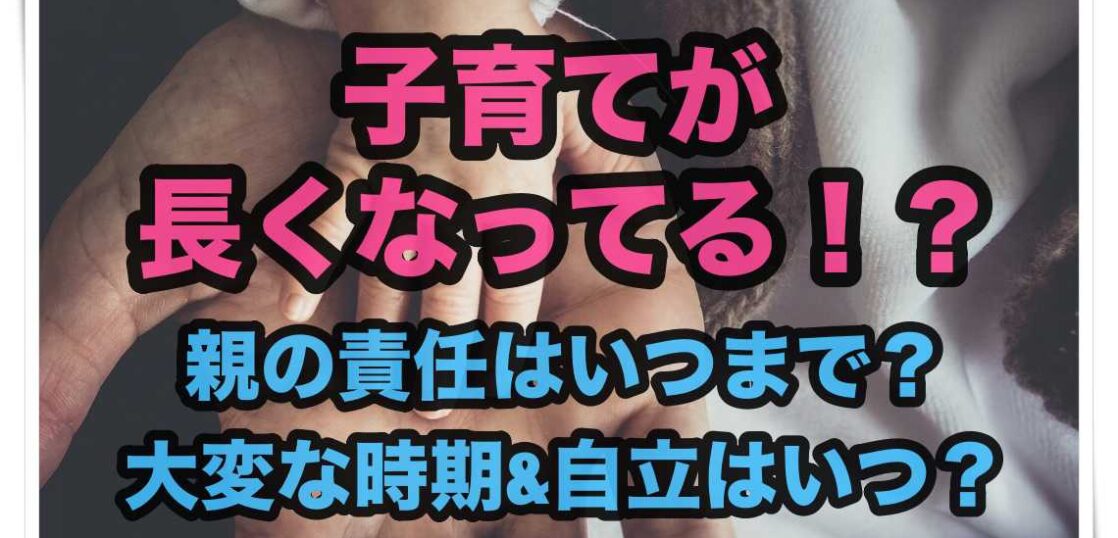皆さんこんにちは!本日も発達障害等に関する学びや情報交換の場になることを願って投稿させて頂きます。今日のトピックは「子育て いつまで」についてです。
「子育てって長い」「いつまで続くの?」「子育てのゴールとは?」と感じる方も多いのではないでしょうか。
目次
【子育て】親の責任はいつまで?自立はいつ?

子育て、っていつまででしょうか? 子どもが結婚したら終わりですか? 30になっても同居してご飯作って 子育て、っていつまででしょうか? 子どもが結婚したら終わりですか? 30になっても同居してご飯作ってあげてたらまだ、子育て中ですか?
引用元:Yahoo!知恵袋
子育てはいつまで?と考えたとき、「親の責任はいつまで?」という疑問が浮かぶのではないでしょうか。
法律上は18歳まで
民法での成年年齢
2022年4月1日から、成年年齢は20歳から18歳に変わりました(改正民法)。これは「父母の親権に服さなくなる年齢=18歳」という意味になります。
参考:政府広報オンライン
児童福祉法での児童の年齢
こちらも18歳です。児童福祉相談所の対応年齢も原則18歳未満ですし、育児放棄の対象も18歳未満となっています。
参考:法令検索 児童福祉法
子育てが長くなっている?
たとえば養育費の支払い義務は個別の事案によって判断されます。
A 子の養育費について,「子が成年に達するまで養育費を支払う」との取決めがされていることがあります。成年年齢が引き下げられた場合にこのような取決めがどうなるか心配になるかもしれませんが,取決めがされた時点では成年年齢が20歳であったことからしますと,成年年齢が引き下げられたとしても,従前どおり20歳まで養育費の支払義務を負うことになると考えられます。
また,養育費は,子が未成熟であって経済的に自立することを期待することができない場合に支払われるものなので,子が成年に達したとしても,経済的に未成熟である場合には,養育費を支払う義務を負うことになります。このため,成年年齢が引き下げられたからといって,養育費の支払期間が当然に「18歳に達するまで」ということになるわけではありません。例えば,子が大学に進学している場合には,大学を卒業するまで養育費の支払義務を負うことも多いと考えられます。
なお,今後,新たに養育費に関する取決めをする場合には,「22歳に達した後の3月まで」といった形で,明確に支払期間の終期を定めることが望ましいと考えられます。
引用元:法務省 民法(成年年齢関係)改正 Q&A
現代では社会が複雑化・高度化していて、学ぶことも多く、また時間がかかります。
また、学ぶことが多い割に「体験や経験」は不足していることが多く、親子共に「大人といえるのはいつなんだろう…」という感覚に陥りやすいのかもしれません。
ほんとうの自立とは
現代における自立は「年齢では決められない」といえます。
年齢にかかわらず、
- 親離れなどができたとき(精神面の自立)
- 養育費がかからなくなった状態(経済面の自立)
の両方を満たした上で、
- ひとりで生きていける
- パートナーや仲間などの誰かと生きていける
- 支援制度などを活用しサポートを受けながら暮らしていける
などのいずれかの状態になった時点で自立といえるのかもしれませんね。
精神的に親離れができ、経済的にも養育費が掛からなくなった状態で、ひとりで、あるいは誰かと、また支援制度などを活用し生きていけるようになった時。
子育ての大変な時期はいつまで?楽になった時期は?

では子育てにおける「大変な時期」はいつまででしょうか?
ピークは3歳と中学生?
一般的に子育てが特に大変なのは0〜3歳と言われていますが、中学生が一番大変という声もあります。
【0〜3歳までが大変な理由】
- 言葉での意思の疎通ができないから
- 好奇心旺盛かつ善悪の区別や自制心はまだないから
- 生活のほとんどすべてにおいて親の手が必要だから
- 大人とは別の食事の準備も大変だから
- イヤイヤ期があるから
▼「中学生が一番大変」というリアルな声。
・7人子供いますが、中学生ですね!
・同じく中学生です。 乳児の寝不足、2.3歳のイヤイヤ期なんかより、かなりキツイです。
・同じく中学生。いきなり子供から大人っぽく成長するし、親に対して反抗というか素直な小学生から変わっていくから扱いが難しくなる感じで苦笑
引用元:Yahoo!知恵袋
高校卒業くらいまでは大変という声も
高校生までという声もありました。
子育ては何歳までというより、大変さは変わりながらも高校まではずっと続きますよね。
引用元:Yahoo!知恵袋
成人したら&稼げるようになったら楽になる
「成人したら・稼げるようになったら」楽になったという声はこちらです。
成人したらある程度楽になります
引用元:Yahoo!知恵袋
反抗期→思春期→受験→就職〜 子供が自分の稼ぎで生活できる様になるまで、何かとイライラしますよ(^_^;)
引用元:Yahoo!知恵袋
結婚してから!?
今は結婚しない方も増えましたが、結婚までしてやっと安心できるという意見も。
子どもが成人して結婚するまで子育ては楽にならないですよ。 ウチのジジババが私が嫁さん貰った時に「お前が結婚してやっと楽になったよ」と言っていましたからね。
引用元:Yahoo!知恵袋
子育ては意外と短いかも
しかし、子離れは意外と早く、そして突然やってくるという声もありました。
▼こちらの動画では、子離れは突然で、一気に寂しくなるというということでした。子どもが巣立つ前に親が自分のやりたいことを考える必要があることや、親の愛情バロメーターが低いと永遠に終わらないケースもあることが解説されています。
発達障害のある子どもの子育てで特に意識しておきたいこと

発達障害のある子どもの場合は、上記で紹介した内容に加え、さらに以下の内容が大切になってくると考えられます。
子どもの頃から適職を探す意識を持つ
発達障害は脳の機能の発達スピードが遅い(育ちにくい)部分と、早い部分(育ちやすい)部分の差が非常に大きいとされています。
つまり得意と不得意の差がとても大きいので、子どもの頃から以下を意識しておくのがおすすめです。
- 本人の特性に合った得意を生かせる仕事を探すこと
- 本人の特性に合わせて環境を整えること
- 困ったことがあれば素直に周りに協力を求めること
▼発達障害のある子どもがぶつかりやすい壁や小さい頃にしておけばよかったと思うこと、実際に就いている職業などについて書かれている記事です。
▼こちらは環境を整える際に参考になる記事です。
自立のために将来受けられる可能性がある支援とは
また、発達障害を持つ人の自立について、これからさらに可能性や選択の幅は増えると考えられますが、たとえば現在の横浜市では以下のような支援を受けられる可能性があります。
- 障害者自立生活アシスタント事業(横浜市)
- 発達障害者支援センター(横浜市)
- 障害者就労支援センター(横浜市)
- ハローワークでの職業リハビリテーションやトライアル雇用事業、ジョブコーチ支援、生活支援など(厚生労働省)
発達障害のある子どもの子育てにいつまで続くの?と感じたら
定型発達の子どもの何倍も大変だと言われることもある、発達障害のある子どもの子育て。
もし発達障害のある子どもの子育てに「一体いつまで続くの…?」と限界を感じた場合、以下の記事を参考にしてみてください。
▼相談先やメンタルケアの方法、親子が一時的に距離をとることや離れて暮らす場合についても解説された記事です。
まとめ
今日の記事のまとめは以下になります。
- 成人年齢が引き下げられ、法律上の親の責任は18歳までと言えるが、実際は異なる場合が多い。
- ほんとうの自立とは、年齢に関わらず、精神面と経済面両方の自立ができた時といえる。
- 子育ての大変な時期は「3歳まで」や「中学生」という意見が目立つが、どの時期にもそれぞれの大変さはある。
- 子育てが楽になった時期は、高校卒業や成人したこと、経済的に手が離れたことなどがポイントになることも。
- 発達障害のある子どもの子育ては、特性や個性による得意と不得意を早めに見極めたり、環境を整えることがよい自立につながる。
今日の記事が皆様のお役に立てれば幸いです。読んで頂きありがとうございました。