皆さんこんにちは!本日も発達障害等に関する学びや情報交換の場所なることを願って投稿させて頂きます。
今日のトピックは「お子さんの発達障害をどう受け止めて子育てするか」についてです。
松永正訓『発達障害に生まれて』(中央公論新社,2018.9)という本をご存知でしょうか?
この本には、自閉症と診断された子どもを持つ、1人の母親の姿と葛藤が描かれています。
子育てはマニュアルの無い大仕事です。
発達障害であれば、なおさら難しいと感じてしまうかも知れませんね。
お子さんとは切っても切り離せない発達障害という個性を、保護者はどのように受け止めて子育てすれば良いのでしょうか。
この記事では、発達障害を持つお子さんを育てる上でも大切となる「個性」にスポットを当ててお伝えしていきます。
『発達障害に生まれて』を既に読んだことのある方も、これから読む方も、お子さんの将来に向けて一緒に勉強していきましょう!
目次
『発達障害に生まれて』はどんな本?

『発達障害に生まれて』は、中央公論新社から2018年9月に出版されました。
サブタイトルは「自閉症児と母の17年」です。
作者である松永正訓さんは小児科医の先生ですが、独自の視点から「発達障害」を捉えた著作を何冊も執筆されています。
この本では、発達障害の特性を持って生まれた子どもと、その母親の姿が、ルポルタージュ(取材からの報告)の形で描き出されています。
本のモデルとなったのは、知的障害を伴う自閉症である「勇太くん」。
発達障害の診断を告げられた勇太くんのお母さんは、なかなか診断を受け入れることができませんでした。
「普通」の枠に収まらない勇太くんとの生活の中で、何度となく周囲の視線にさらされながら、お母さんは理想の子育てとのギャップに苦しみます。
思い通りには進まない悩みと葛藤だらけの子育ては、 ありのままの勇太くんを発達障害ごと心に受け入れていく過程でもありました。
お母さんは「子どもを変えるんじゃなくて、親である自分が変わらないといけないんだ」と気付きます。
「普通」であることにこだわっていたのはお母さんの方だったのです。
本の内容はお母さんの視点ですが、『発達障害に生まれて』というタイトルを見ると、タイトルが勇太くんの視点であることがわかります。
勇太くんの気持ちに寄り添う決心をしたお母さんの心が、このタイトルには込められているのでしょうか。
子どものありのままを心から受け入れられた時、親はようやく本当に子どもの個性を尊重し、巣立つ手伝いをすることができるのかも知れません。
『発達障害に生まれて』は、手さぐりで子育てをするお母さん・お父さんの、親子の有り方を見つめ直すヒントとなる1冊です。
【書籍情報】
書名:『発達障害に生まれて――自閉症児と母の17年』
著者名:松永正訓
出版社:中央公論新社
出版年月日: 2018/9/10
形態:四六判 256頁
言語: 日本語
ISBN-10:4120051153
ISBN-13:978-4-12-005115-9
【外部リンク】
中央公論新社(Topページ)
単行本版『発達障害に生まれて』 書籍情報のページ
電子書籍版『発達障害に生まれて』 書籍情報のページ

発達障害に生まれてposted with ヨメレバ松永正訓 中央公論新社 2018年09月10日 楽天ブックス楽天koboAmazonKindle
↓松永正訓さんの他の著作はこちらをご参考下さい
【外部リンク】中央公論新社 「著者名:松永正訓 を含む書籍一覧」
↓その他の松永正訓さんの活動はこちらをご参考下さい
【外部リンク】松永クリニック ホームページ
【外部リンク】歴史は必ず進歩する! 医師・松永正訓のブログ
個性を尊重した子育てってどんなもの?

子育てには、個性を認め尊重することが大切であるとされています。
『発達障害に生まれて』でも、子どもである「勇太くん」のありのままを受け入れることで、お母さんは子育ての希望を見つけました。
では、個性を尊重した子育てには、どのようなメリットと工夫があるのでしょうか?
個性を尊重すると自尊心が育つ!?
お母さんお父さんがお子さんの個性を尊重することは、お子さん自身が「自分の個性を大切にする」ことに繋がります。
自分を大切にする気持ちは「自尊心」と呼ばれます。
【自尊心があると得られる効果の例】
- 生きていることが楽しいと思えるようになる
- ものごとを肯定的に受け止められるようになる
- 他人の評価に惑わされなくなる
- 不安感が減り、感情が安定する など
自分が大切だ・自分のことが好きだ、というと「うぬぼれ屋じゃないのか」と思われてしまうかも知れませんが、自分を好きになることは生きていく上でとても重要な感情です。
「生きていく」ことに、自分を好きだという感情がどう影響するんでしょうか?
人生におけるモチベーションが大きく変わってきます。
もし自尊心が育たないまま成長すると、何をするにも「自分にできるだろうか……」「自分がやっても良いのだろうか……」と消極的になってしまう恐れがあります。
自分には価値が無いと思い込み、自分の欠点を理由に何にも挑戦しなくなるかも知れないのです。
自尊心は子どもの頃の経験を通して作られ、育っていくといいます。
お母さんお父さんがお子さんの個性をどう捉えるかは、お子さんの自尊心を形作る上で、とても大きな影響力を持つでしょう。
お子さんが自尊心を育てられるよう、個性を尊重できる子育てをしましょう。
二次障害のリスクが軽減できることも
個性を尊重した子育てで自尊心を育てることは、二次障害のリスクの軽減にも繋がります。
二次障害とは、発達障害の特性からの苦手や対人関係のトラブルにより強いストレスや不安を感じ、不登校や鬱(うつ)、引きこもりなどの深刻な状態におちいってしまうことです。
こうした二次障害のリスクにお子さんがさらされた時、「お母さんやお父さんは理解してくれている」と感じることで安心を覚え、ストレスや不安が抑えられるかも知れません。
大人になり親元を離れる時が来ても、「お母さん、お父さんが信じてくれた」という経験は自信の元となります。
「個性」とは、良い事ばかりではない
「個性」は良いものだと思われがちですが、必ずしも良い事ばかりとは限りません。
短所もまた個性であるからです。
ありのままを受け入れるということは、お子さんの短所も長所も全てを受け入れるということです。
自分が好ましくないと思っている部分を受け入れることは、実の親子であっても、なかなかすんなりとできることではないでしょう。
それを受け入れるには、自分の価値観を崩すことにもなりかねないからです。
つい頭ごなしに、「なんでそんなことするの!」「悪いくせだ!」と叱ってしまうこともあるかも知れませんね。
お母さんお父さんは子どもの悪いところを治そうとして良かれと思って叱りますが、子どもにとってはそれが、「自分が否定された」と感じる一場面となってしまいます。
親が子どもの個性を尊重しようとしていても、こうしたケースは度々起こり得ることでしょう。
どうしても「短所=治さなければいけない部分」と捉えてしまいがちだからです。
お子さんをありのまま受け入れるには、「短所もまた個性である」という視点がまずは必要不可欠となります。
短所を受け入れる事で、問題の改善ができるようになる
短所の存在を認めないことは、問題の改善の機会を失うことでもあります。
好ましくない部分を否定しておさえ込むことは、表面的には問題が解決したように見えますが、「自分」を抑え込み続けるお子さんの中にはストレスが残ります。
お子さん自身が納得する形で折り合いをつけることで、こうしたストレスは軽減されるでしょう。
「どうすれば周囲との折り合いがつけられるか」を考えることは、短所がどのようなものかを正しく理解することからはじまります。
お子さん自身も自分の短所をよく知り、どうすればそれを改善できるのかを自分で考えられるようになるかも知れません。
自分を分析する力や、自己解決の力が身に付くことは、お子さんがいつか大人になって親元を離れた後にも役に立つでしょう。
個性を尊重しつつ、社会のルールを教えるには?
個性を尊重するといっても、もちろん、守るべき社会のルールは教えていかなければならないでしょう。
ここでお母さんお父さんは葛藤することになります。
社会のルールとお子さんの個性の間で、板挟みになってしまうのです。
電車に乗っている時にも大きな声で歌ってしまうと他の人の迷惑になってしまいますよね?
かといって、「好きなだけ歌うといいよ」と言ってしまうと、今度は社会のルールを教えることができません。
周囲の人からも「なぜ叱らないんだ」とお母さんお父さんが怒られてしまうことにもなるでしょう。
お子さんの個性を尊重しつつ、社会のルールも教えなくてはいけないという、2つの事を同時にこなさなければならないのです。
けれども、これは不可能なことではありません。
「歌うのは楽しいね。でも、電車の中では静かにしようね」と、お子さんに肯定的な声掛けをしてから、続いて社会のルールを教えるなどの工夫をしてみましょう。
伝える時は発達障害の特性に合わせて
お子さんの発達障害の特性によっては、口頭で伝えても上手く伝わらないことがあります。
目で見る方が理解しやすい場合はイラストや図を使って説明するなど、お子さんの得意なアプローチから伝える工夫をすると良いかも知れません。
外出先でイチから絵を描くのは難しいこともあるでしょう。
そんな時は、起こりそうな事態をあらかじめいくつか予想して、「絵カード」のような形で持ち歩くのも1つの方法にできそうです。
「絵カード」とは、言葉だけのコミュニケーションが苦手な場合に補助的に使うイラストや写真のことです。目的に応じて、指示カード、手順カードなどの種類があります。
↓絵カードは市販でも売られています。
お子さんの好みや目的に応じて、お気に入りのものを探してみましょう。
【商品の例】
世界文化社 発達障害の子が迷わず動ける!絵カードPriPri発達支援6
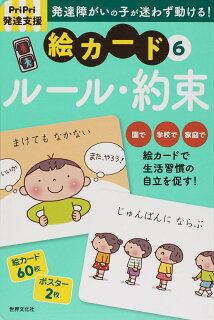
発達障害の子が迷わず動ける!絵カード PriPri発達支援 6 /世界文化社/佐藤曉posted with カエレバ楽天市場AmazonYahooショッピング
なぜ「普通」を求めてしまうのか

お子さんの個性を尊重しようと思っていても、つい「扱いにくい子だなぁ……」と感じてしまうこともあるかも知れません。
「こんな行動をするなんて、普通じゃない……」
「普通の子だったら良かったのに……」
そう思って、お母さんお父さんも苦しい気持ちになってしまうことはありませんか?
普通とは何だろう?
そもそも、「普通」とは何なのでしょうか?
辞書を引くと、「ありふれた」「あたりまえ」という言葉と一緒に、「たいてい」「一般に」という意味が出てきます。
(参照元:コトバンク「普通(フツウ)とは」)
「たいてい」や「一般に」という感覚は、多数決のようなものではないでしょうか。
だいたいの人がその時々で「あたりまえ」と感じていることを指して、なんとなく「普通」と言っているのです。
「普通」という言葉を使う時、人は集団の中に自分を置きたがっているのかも知れません。
たくさんの人と同じ行動を取る時、人は安心を感じるといいます。
こうした心理は「集団心理」と呼ばれています。
お子さんに「普通」を求める時、お母さんお父さんの心理には不安があるのではないでしょうか。
お子さんをどう育てればいいのかわからない、お子さんの将来がどうなるのかわからないという不安が働いてしまって、つい周囲を見てしまうのかも知れません。
そして、周囲とお子さんを見比べてしまい、その違いにますます困惑してしまう悪循環におちいっている可能性もあります。
親自身の不安を和らげて、子どもの成長を見守る
集団の安心を得られないことへの不安や、自分の価値観がひっくり返ってしまうかも知れない不安を乗り越えてお子さんの個性をまるごと受け入れることは、容易ではないでしょう。
未知のものに対する不安や、先のことがわからない不安は、情報を集めたり誰かに相談したりすることで和らぐことがあります。
同じ境遇にある人の体験を聞くのも良い方法となりそうです。
【情報の入手先や相談先の例】
- 発達障害を持つ人や、発達障害を持つ子どもを育てた人の体験記を読む
- インターネットやSNSで情報を集める
- 学校の先生・療育施設に相談する
- 公共の窓口に相談する など
『発達障害に生まれて』(中央公論新社)を含めて、発達障害を持つ人や保護者の体験記などは多数出版されています。
発達障害の特性や症状は個人により異なりますが、悩みや改善の方法など、共感する部分や参考になる部分もあるでしょう。
インターネット掲示板や、ブログ、TwitterやFacebookなどのSNSでも、同じ悩みを持つ人の考えを知ることができます。
学校の先生や療育施設の先生は、多くの子どもの事例や発達障害の子どもの事例を知っています。
↓こちらのサイトでも、発達障害や子育ての情報を得ることができます
横浜市都筑区児童発達支援と放課後等デイサービス
運動・学習療育アップ
お住まいの市区町村の公共の窓口でも、子育てや将来の不安を相談することができます。
発達障害の悩みは「障害福祉課」などの窓口、子育てに関する悩みは「子育て支援課」などの窓口で受け付けてくれます。
(地域によっては、担当窓口が異なる・窓口の名称が異なる場合があります)
情報を集めたり、誰かに相談したりして、まずはお母さんお父さん自身の不安を軽減しましょう。
お子さんの個性を受け止め、成長をゆったりと見守る余裕ができるようになるかも知れません。
お子さんは、お子さんに合ったペースで成長しています!
できるだけ周囲と見比べずに、お子さんの成長を見守ってあげたいですね。
生活に不安がある場合の相談先:発達障害者支援センター
発達障害の悩みは、「発達障害者支援センター」に相談することができます。
「発達障害者支援センター」は、発達障害を持つ人や児童への支援を総合的に行う専門機関です。
各関係機関や地域と連携し、発達障害を持つ本人と家族、周囲の人達からの様々な相談に応じてくれます。
【発達障害者支援センターに相談できることの例】
- 日常生活でのさまざまな相談
(気になること、学校や職場で困っていること など) - 発達支援に関する相談
(家庭での療育の方法 など) - 就労に関する相談
(仕事での困難、就職への不安 など)
子育ての不安も相談することができますよ!
↓こちらの外部リンクより、全国の相談先を探すことができます。
【外部リンク】発達障害情報・支援センター(厚生労働省)
「相談窓口の一覧」
個性が尊重される社会へ
現在日本は、障害があってもひとりひとりが自分らしく活躍できる社会になりつつあります。
2016年4月に施行された「障害者差別解消法」では、障害のある人への不当な差別が禁止され、合理的配慮が義務付けられました。
国連の「障害者の権利に関する条約」の締結に向けた国内法制度の整備の一環として、全ての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に向け、障害を理由とする差別の解消を推進することを目的として、平成25年6月、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(いわゆる「障害者差別解消法」)が制定され、平成28年4月1日から施行されました。
引用元:内閣庁「障害を理由とする差別の解消の推進」
合理的配慮とは、障害を持っている人も他の人と同じように社会生活を送れるように、社会の方を変えていこうというものです。
社会全体が、「障害」を受け入れようと葛藤しながら動いています。
ここに掲げられている「人格と個性を尊重し合いながら共生する社会」が実現した時、人それぞれが違う個性を持っていることが当たり前になり、「みんな違う」ということが「普通」になっていくのかも知れませんね。
まとめ
それでは、これまでの情報をまとめてみましょう。
- 個性を尊重した子育てをすることで、自尊心が育つ!
- 個性を否定しないで社会のルールを教えるには工夫が必要!
(まず気持ちを肯定する・特性に合わせた伝え方をする など ) - 本やインターネットで他の人の体験を知ることで、不安を軽減できるかも知れない!
- 子育てや将来の不安などは、誰かに相談しましょう!
(学校の先生や、公共の窓口、発達障害者支援センター など) - 障害を持っていても生きやすい環境へと、社会の方も変わりつつある!
ありのままのお子さんを発達障害ごと受け入れるまでには、多くの悩みや葛藤があるでしょう。
昨今、LGBTや人種、文化の違いなどが何かと話題に上るようになりました。
発達障害ばかりではなく、これらの違いも受け入れられる多様性を求められる社会になりつつあります。
お子さんは発達障害を通して、一足先に、個性を豊かに尊重し合える世界を見ているのかも知れませんね。
松永正訓『発達障害に生まれて』(中央公論新社)、まだ読んでいない方はこの機会にぜひ読んでみて下さい!
もっと詳しく・他の情報も知りたい方は、
こちらのサイトもご参考下さい!
↓


