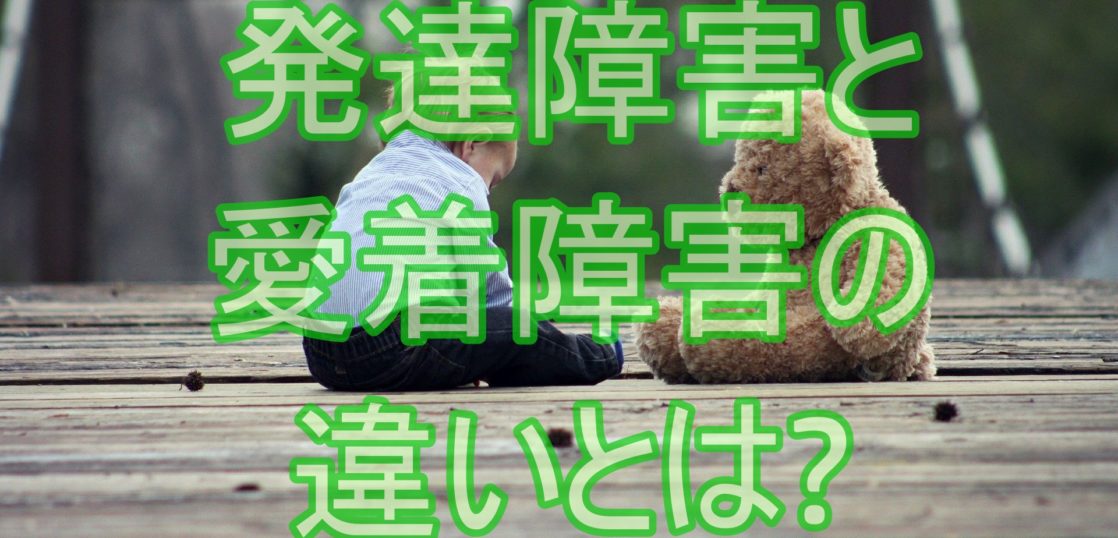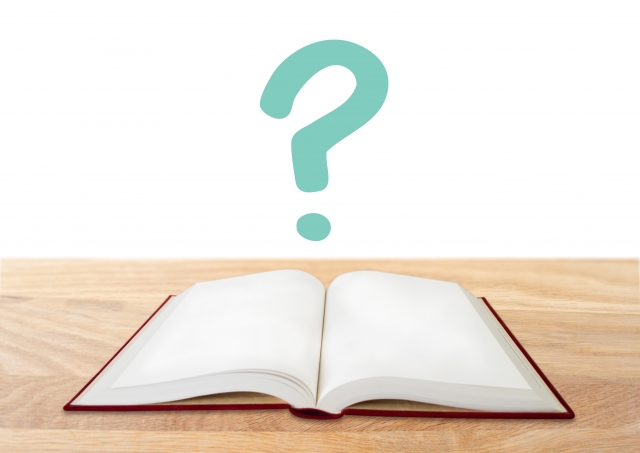皆さんこんにちは!本日も発達障害等に関する学びや情報交換の場所なることを願って投稿させて頂きます。
今日のトピックは「発達障害と愛着障害」についてです。
今この記事に辿り着いた方の中には、発達障害と愛着障害、両方について詳しく知りたい、もしくはその違いや関係性が知りたい、といった方が少なくないのではないのでしょうか?
そこで今回は広がった意味合いはどのようなものなのか、また愛着障害と発達障害の違いや類似点について、詳しく見ていきたいと思います。
目次
愛着障害とは

ではまず始めに、愛着障害について見ていきましょう。
医学的にみた愛着障害
冒頭で述べたように、愛着障害とは小児期を中心にした医学的な疾患名で、その定義はかなり限定的なものです。ネグレクトや虐待、養育者が頻繁に変わったかなど、愛着形成が極端に制限される環境だったかどうかが診断基準になっています。
愛着の形成とは、子どもの人間に対する基本的な信頼が育まれている状態です。
例えば一番最初の段階は赤ちゃんのときになります。空腹を感じたり、おむつの交換を求めたりして、周囲に助けを求めます。そのときに養育者が対応してくれる、スキンシップを取ってくれる、などで優しさの体験を積み重ね、人に対する信頼を獲得していくのです。
成長ともない周囲の人との関わりを通して、さらに愛着関係がきちんと形成されると自立心・自尊心が育まれていき、人間関係や社会性を発達させていく土台となります。
しかし愛着形成がうまくいかなかった場合、その特徴は「反応性愛着障害」と「脱抑制性対人交流障害」して解説されます。どちらも人との距離の取り方に、困難を感じている状態です。
反応性愛着障害
反応性愛着障害のある子どもは、辛いことがあっても、周囲の人に頼る、甘えることが苦手です。プラスの感情を表に出すことがあまりなく、マイナスな感情の発露が目立つようになります。これは人を過度に警戒している状態と考えられます。
脱抑制性対人交流障害
反対に脱抑制性愛着障害のある子どもは、警戒心が薄く、初めての場所でも振り返らずに行ってしまう、初対面の大人にも人見知りなくべったりする、場にそぐわず過剰になれなれしい態度で相手に接する、などが見られます。これは人の注意を自分に向けようとしている状態と考えられます。
このように「誰にも頼れない」か「誰彼構わず注意をひこうとする」という両極体になってしまう傾向があるのです。
心理学的に使われている愛着障害
心理学的にみた愛着障害とは、子どものころの愛着形成がうまくいかなかったため、大人になってから社会生活・人間関係の構築の難しさ、生きづらさなどを感じることです。
医学的な症状でもあったように、人にうまく頼ることができずに、ひとりで抱え込んでしまう。また自立心や自尊心の低さから、人生の重要な選択において、なかなか自分を信じられず苦労をすることも多いと言われています。
具体的な特徴をいくつか挙げてみましょう。
・安定した人間関係を築くことに不器用さがあり、結果的に仕事やプライベートでトラブルを抱えやすい
・精神疾患を発症しやすく、発症した場合、重くなったり長引いたりしやすい
・感情のコントロールに困難を抱えている
・自分を肯定的に見ることが苦手
・「全か無か」思考になりやすい
・微熱や胃腸の症状が続く、疲れやすいなどの自律神経系のアンバランスがある
・自分の生理的欲求(空腹など)がわかりにくいことがある
・発達障害と似た症状がみられることがある
引用:LITALICO 仕事ナビ「愛着障害とは?」
これらのストレスから、うつ病、自律神経失調症など、二次的な病気に繋がってしまうケースもあります。
発達障害との類似性
さて、全項目で大人の愛着障害には「発達障害と似た症状がある」とありましたが、それはどのような点なのでしょうか。
改めて発達障害とは
ここで、いったん発達障害とはどのようなものか見ておきましょう。
発達障害は大きく、自閉症スペクトラム障害(ASD)、注意欠如・多動性障害(ADHD)、学習障害(LD)の三つに分けて考えられます。この3つの共通点は生まれつき脳の発達の仕方が通常と異なることですが、適切なフォローによって、生きづらさを緩和することができます。
自閉症スペクトラム障害(ASD)
コミュニケーションにおいて、言葉をそのまま受け取ってしまう(比喩が分からなかったり、行間や場の空気が読めない、曖昧な言葉に混乱するなど)ため、他者とのコミュニケーションに難しさを感じることがあります。
また興味を持ったことに集中するあまり、他がおろそかになってしまったり、物事や行動に強いこだわりを持ち、その変更を極端に嫌うことがあります。
多動性障害(ADHD)
大きくふたつ特徴があり、ひとつめは多動や衝動性。これは授業中じっとしていられなかったり、静かに待つことが苦手で他人の邪魔をしてしまうなどです。
ふたつめは不注意。これは何かに集中できず気が散ってしまいやすい、順序だてて物事に取り組めないなどとして現れます。
学習障害(LD)
知的な遅れがないけれども、読むこと、書くこと、計算することのどれかについて(ひとつに限らないこともあります)、修得と表現がとても困難であるケースです。
この三区分の中で、愛着障害との類似性を指摘されるのは自閉症スペクトラム(ASD)と多動性障害(ADHD)です。
共通する症状とは?
その類似する点とは何なのでしょう。「医学的にみた愛着障害」の項目でご説明した通り、愛着障害があると人との距離感が両極端になりがちです。
自閉症スペクトラム障害(ASD)と愛着障害
人に頼ることが苦手、他者と交流することに困難を感じる、といった特徴は、自閉症スペクトラム(ASD)と似ています。
例えばASDですと、言外のコミュニケーションをくみ取るのが難しく、他者と交流することに困難を感じます。また、自身のこだわりが強いこともあって、物事を他者と協力したり共有したりできず、ひとりで進めてしまうことがあります。
多動性障害(ADHD)と愛着障害
一方、知らない場所でも構わず進んでいってしまう、場にそぐわず過剰になれなれしい態度で相手に接するといった特徴は、多動性障害(ADHD)との類似性が認められます。
無計画に見える行動、場にそぐわない行動、馴れ馴れしさといったものは、ADHDの特徴である「衝動性」からも起こりうることだからです。
自分はどっち?と思ったら
大人になってから社会生活で何からの困難を感じたとき、「自分は発達障害なのではないか」「愛着障害なのではないか」と考えたり、他者から指摘されたりことがあるかもしれません。
しかし現れている症状だけでは、一概に発達障害と愛着障害のどちらであるか、はっきりとさせることは極めて難しいと言えるでしょう。
自己判断はしない
インターネット上には簡易的な診断サイトなどがありますが、それを利用して「自分はこれだ」と自己判断してしまうことはとても危険です。
なぜなら、愛着障害と発達障害では対応の仕方が全く異なるからです。
愛着障害の対応
愛着障害の場合は、幼少期に得られなかった安心を補うことが挙げられます。そのために自分が安心して過ごすことのできる、頼り先や居場所を確保することが必要です。そういったものは心理的な「安全基地」と呼ばれます。
それは家族や友人、カウンセラーなどの助けを求められる人を作るだけでなく、趣味などリラックスできることを作る、なども含まれます。
発達障害の対応
当事者の抱えている苦手や不得意を把握し、不得手な部分を丁寧に学び、社会生活に必要な力を付けていく。周囲もその特性を理解し、適切なフォローアップを行っていく。また得意を伸ばし、長所としていくことなどが挙げられます。
また感じている困難の原因は一つだけでなく、発達障害と愛着障害の併発、また他の精神疾患などの合併でもあるかもしれません。
誤った自己判断によって不適切な対応を取ると、症状が悪化したり、かえって複雑になってしまう可能性もあります。そうなる前に専門機関に相談しましょう。
専門家へ相談
まずは精神科、心療内科など専門機関に相談してみましょう。それが難しれば、まずはかかりつけ医でもいいかもしれません。自分が抱えている困難を人に聞いてもらいましょう。
そして専門家による診察やカウンセリングなどを通して、自分の困難は何が要因になっているのか、焦らずに振り返り、どうしていくか考えていくことが大切です。
以下の記事で、相談先についてまとめてあります。ぜひ参考にしてみてください。
まとめ
発達障害と愛着障害は、根本は異なるのに表に現れる症状が似ているため、とても判断が難しいものです。こういった記事で両者の違いをご説明することはできても、「では自分はどっちなのだろう?」という答えを、パッと解説することはできません。
複数の要因が重なっていることもありますし、どこを優先的にケアしていくべきなのかも、個人によって異なります。まずはぜひ、専門機関等へご相談をしてみてください。
今回の記事が少しでも参考になれば幸いです。