皆さん、こんにちは!本日も発達障害に関する学びや情報交換の場所となることを願って投稿させていただきます。
今回のトピックは、「発達障害のスクリーニング検査」についてです。
「実は、発達障害かも?」「相談したいな。」と思った際、いったい誰に相談したら良いのでしょうか?。
そして、具体的にスクリーニング検査とはいったいどういったものなのでしょうか?
そういう疑問を持った方もいるのではないでしょうか?
この記事では、発達障害のスクリーニング検査をこれから受けるという方に向けて発信して行きます。
では早速、みていきましょう。
目次
発達障害のスクリーニング検査内容ってどんなもの?
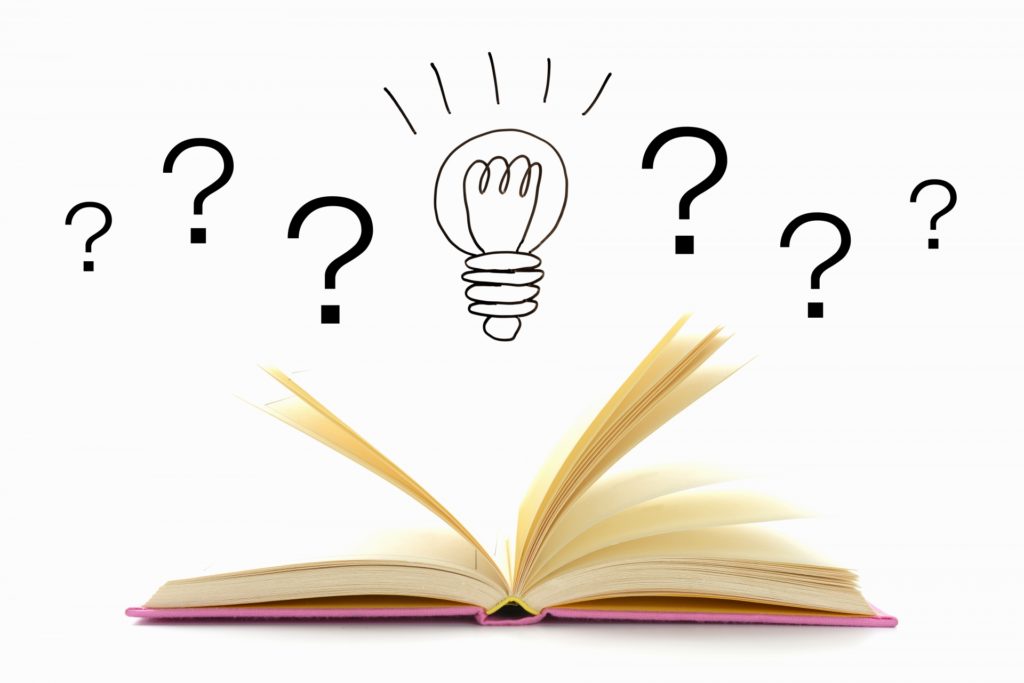
そもそも「スクリーニング」とは?
スクリーニングとは、「選別」「ふるい分け」のことを言います。
支援をを求めている人たちの環境や置かれている状況、潜在的な発達遅延や可能性などを調査し、課題・複雑性・緊急性を「ふるい分け」することを言います。
スクリーニング検査は、どんなことをするの?
スクリーニング検査の目的は、発達障害の遅滞や発達障害の可能性を早期に発見することが目的です。
メリットとして、簡単かつ正確、安価で短時間で行うことができる点。また、多くの対象児に施工することができます。
母子保健法に基づき、乳児健康診査、1歳6ヶ月健康診査、3歳児健康診査でも活用されています。
発達障害の検査には、このようなものがあります。
- 発達検査:遠城寺式発達検査、新版K式2002発達検査、デンバーⅡ発達検査
- 知能検査:田中・ネビーⅤ、WISC-Ⅵ
- 自閉症特性検査:M-CHAT,PARS-TR(新面接式自閉スペクトラム症評定尺度)、ADOS-2
代表的なものを紹介します。
発達検査:遠城寺式発達検査
運動・社会性・言語の3分野の質問項目から構成されています。「移動運動、手の運動、基本的習慣、対人関係対人関係、発語、言語理解」の6つの領域での診断をする。その為、子供の発達を観察把握し、一人ひとりの全体的な発達障害の状態を明らかにできます。
適用年齢 0から4歳7ヶ月
所要時間:15分
検査方法
生活年齢を中心に検査問題を進めていき、合格であれば、月の領域の問題を行っていきます。しかし、不合格が3つ続いいても、それ以上検査を進める必要なく、合格○、不合格×という形で記入していきます。
メリット
- 検査結果を何度も記入可能できる為、過去の検査結果と比較して発達状況を継続的にいることができる。
- グラフを活用することができる為、発達障害のある保護者が見てもわかりやすい。その為、そのまま発達指導にも役に立てることができる。
- 発達グラフに表すことができる為、全体像から発達の様子を捉えることができる。
改訂日本版デンバー式発達検査
適応年齢:生後16日〜6歳までの就学前
時間:20分程度
特徴:乳幼児の発達を
「個人ー社会」「微細運動ー適応」「言語」「粗大運動」の4領域、
104項目から全体的に捉えて、評価します。
診断的なレッテルを張ることを目的としているのではなく、発達的に障害がある可能性が高い子供を見つけることを目的としています。
メリット
- 早期対応、早期発見、早期支援(専門的な医療、保険サービス等)につなげることができる。
- 客観的に確認することができる。
- 周産期に問題のあったようなハイリスクの子供について発達の経過を検討していくために有効である。
検査方法:対象児の暦年齢を計算し、暦年齢線と呼ばれる垂直線を引いて、基準を設定し、項目を決めていく方法となります。
それぞれの領域で3項目が不合格になるまで続けていき、項目の成否を帯の50%の印の近くに「合格:P」「不合格:F」「拒否:R」「これまでやる機会がなかった:NO」で記入していきます。
年齢水準に比べ、遅れの項目がどのくらいあるか、領域の場所によって、異常、正常、疑問、不能かの判定を行っていきます。
自閉症特性検査:PARS-TR
適応年齢:3歳以上 ※面接は、対象者の母親に行う。
所要時間:
全項目版 約1時間半(回答・評価)
短縮版 約30〜45分(回答・評価)
特徴
- 自閉スペクトラムの発達・行動症状について母親に面接し、その存否と程度を評定する57項目からなる検査。
- 対象児者の適応困難の背景に自閉スペクトラムの発達・行動症状に影響する環境要因の観から把握する。
- 基本的な、困難性に加えて支援ニーズと支援の手がかりが把握できる。
- 幼児期および現在の行動特徴と症状に影響する環境要因の観点から把握する。
- 反構造化面接により発達・行動症状を把握することを通じて養育者の対象者に対する英回を深めることができる。
発達検査と知能検査等を組み合わせて受けることがあります。
理由としては、
- 発達障害の確定診断を行う際の参考情報のため。
- また、指導方法を決めるため。
いくらかかるの?
知能検査は、公的病院・民間病院で受けることができます。
精神科や臨床心理士による検査が受けられる病院を受診することをお勧めします。
また、「児童発達支援センター」でも受けることが可能です。
費用に関しては、検査内容や病院によって異なるため、受診する病院に問い合わせてみましょう。
また、診断書または報告書を書く場合には、別途料金がかかります。こちらも病院に問い合わせて確認してみることをお勧めします。
診察状必要だと認められない場合、保護者の希望により、病院・クリニックが独自に設定した保険外診療プランで検査を受ける場合などがあります。
その際は、保険適応外です。
そのため、検査費用及報告書費用合わせて約1万〜2万円が必要となる場合もあるでしょう。
治すのではなく、生きやすくする。

発達障害は、決して治るものではありません。脳の機能不全による得意不得意の問題なため、本人の「特性」をいかに引き出していくかがポイントとなります。
そのため、検査を受け、治療方針を医師や専門職、家族などと一緒に方向性を示していきます。
発達障害の治療は、障害の原因を根本的に治すことが目標ではなく、社会の中でいきやすくするための治療・援助がメインの方法です。
以下のものがあります。
子供の場合
- 環境調節
- ペアレントトレーニング
- 薬物療法
環境調整
「時間の整理」を行わせるというような訓練をさせていきます。「何をどんな手順で行えば良いのか」「終わりの状態の把握」「待つことの大切さ」などを学習されていきます。
ペアレントトレーニング
ADHDへの理解を深める為、子供の対応方法を学ぶ保護者のためのトレーニングです。(保護者=ペアレント)しかし、現在では実施している医療機関が少ないのが現状です。
大人の場合
- コーピング
- カウンセリング
- 信頼関係の構築
- 合併精神障害への対応
- 社会技能訓練
コーピング
生きやすくするための、治療方針に則った告知やアドバイスを指します。職場選択での助言や、人間関係間での適応対応方法などのアドバイスを行こなっていきます。
カウンセリング
専門家と本人で行い、自分の感情を伝える。そして、客観的に本人の状況を伝え、また、それに対する助言、アドバイスを行う。
合併精神障害への対応
発達障害には、二次障害などの合併症が多いため、薬物療法や対処療法を行います。
二次障害とは、障害などの影響により、うつや引き篭りなど精神障害を併発してしまう状態を言います。
社会技術訓練
人が社会で生きていく上で必要な技術を習得するための訓練を受けます。医療機関によっては、プログラムや進め方に違いがありますが、コミュニケーション力や想像力を補う訓練を行なっていきます。
症状によっては、薬物療法を行う。
症状によって、薬物療法を行う場合があります。
自閉症スペクトラム症にも薬物療法が使われる場合があります。「アリピプラゾール(エビリファイ等)」が使われることがあります。しかし、あくまでも、対症療法でしかありません。
しかし、タイムスリップ現象に劇的に効く人もいると言われています。
抑うつ症状を合併している人には、抗うつ薬を処方することがあります。脳内のセロトニンとノルアドレナリンの調節をしてくれる薬です。
ADHDに効く薬があります。ADHDで内服される薬の代表として、「アトモキセチン(ストラテラ)」「メチルフェニデート(コンサータ)」「グアンファシン(インチュニブ)」があります。インチュニブは、小児用に使われますが、成人にも適応されています。
どこの機関に相談したらいいの?

「よく分からないから相談したい…」となった際、どこに相談したら良いのしょうか?
まずは、お住まいの地域にある身近な相談窓口の利用をお勧めします。
注意が必要なのは、子供も場合、大人の場合でいく機関が違いますので、下記を参考にして下さい。
<子供の場合>
- 保険センター
- 子育て支援センター
- 児童相談所
- 発達障害支援センター
<大人の場合>
- 発達障害者支援センター
- 障害者就業・生活支援センター
- 相談支援事業所
通院している、心療内科や精神科の専門家に相談するの良いと考えています。
発達障害を抱えているからと言って、手帳を持たない人もいます。また、一般就職で入る方も多くいます。
その為、主治医がいるのであれば、主治医の意見、判断を聞いた上で、他の機関に相談するか判断をもらうことも大切だと思います。
体験談を話すと、心療内科に通っていて、心療内科で検査を受けた際にADHDの診断をもらいました。
ADHD診断後、再就職等をする際、障害者就業・生活支援センターに相談した方がいいかと相談しました。しかし、医師や臨床心理士からは、「障害者就業・生活支援センターへの相談はいらない。一般就職で大丈夫だ。」という判断され、その代わりに、カウンセリングを通して、対人関係の対応方法を学んでいるという事例もあります。
まとめ
この記事ではスクリーニング検査について解説してきました。
- スクリーニングとは、支援をを求めている人たちの環境や置かれている状況、潜在的な発達遅延や可能性などを調査し、課題・複雑性・緊急性を「ふるい分け」をいう。
- スクリーニング検査の目的は、発達障害の遅滞や発達障害の可能性を早期に発見することが目的。
- 費用に関しては、検査内容や病院によって異なるため、受診する病院に問い合わせることをお勧め。
- 障害の原因を根本的に治すことが目標ではなく、社会の中でいきやすくするための治療・援助を行う。
発達障害を抱える人たちは、叱られたり、注意を受けたりすることが圧倒的に他の人と比べて多いです。
そのため、自己肯定感が低いまま、自己形成をしてしまうケースが多いと言われています。
また、人間関係をうまく築くことができず、いじめや抑うつ障害、不安障害などの精神疾患の二次障害を引き起こすケースもあります。
発達障害を早期発見することが大切です。

