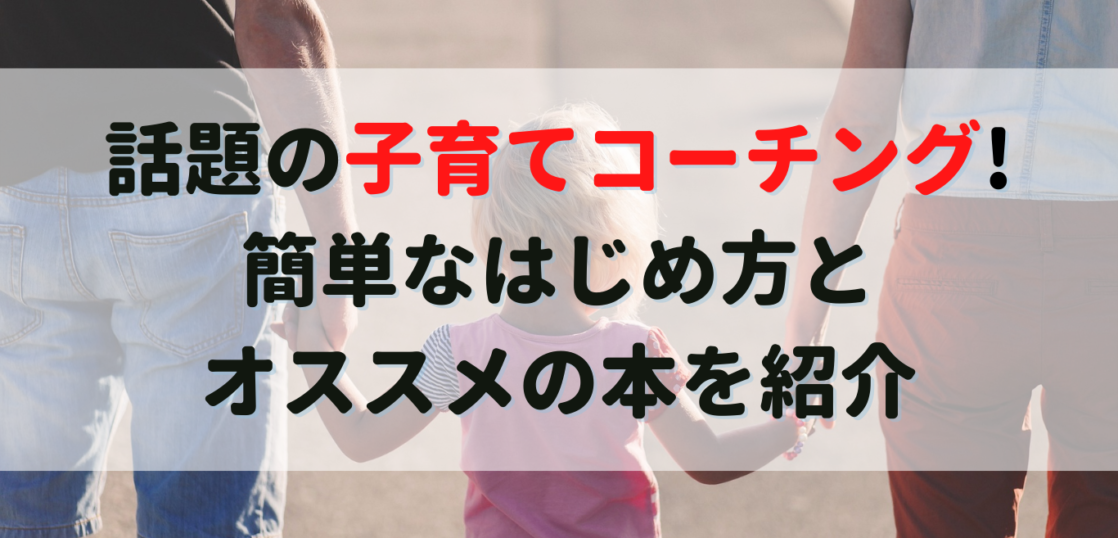皆さんこんにちは!本日も発達障害等に関する学びや情報交換の場になることを願って投稿させて頂きます。今日のトピックは「子育てコーチング」についてです。
最近何かと話題の「子育てコーチング」。
言葉は聞いたことはあっても、詳しい内容は知らない、なんだか怪しそうと思っている方も多いのではないでしょうか。
実際はそんなことはありません。
今回は日常の中にも簡単に取り入れられる「子育てコーチング」の基礎と、コーチングを勉強するのにオススメの本をご紹介します。
目次
子育てコーチングとは

子育てコーチングとは、「コーチング」と言われるスキルを育児に応用したものです。
コーチングと言われて、真っ先にスポーツの「コーチ」を思い浮かべる方も多いかもしれませんが、子育てコーチングで取り入れる「コーチング」も皆さんがイメージするコーチと同じように、相手の成長のために手助けをする手法です。
もう少し具体的に言うと、「コーチング」とは、子どもが自分から行動するように勇気づけ、やる気をもたらす、相手の成長のためのコミュニケーションスキルと言えます。
なにか問題を抱えている相手に対して、答えを教える行為ではありません。
子育てでコーチングをする理由

ここまで子育ての分野でコーチングが注目されている理由は大きく2つあります。
自主性をのばす
コーチングの目標は、その人自らが成長することであり、子どもたちの自主性や自発性を養うことができます。
コーチングでは「何かをしなさい」のような答えを大人から与えないので、子どもたちが自ら考える力やそれを実行する力が育まれるのです。
自己肯定感が育まれる
自分の主張を丁寧に聞いてくれる相手がいることは子どもにとって理想的な環境ですよね。
コーチングで行われる傾聴などを通して、子どもの自己肯定感が高まります。
子育てコーチングの方法

それでは、育児にコーチングを取り入れる方法について紹介します。
コーチングの実践でまず大切なのは「傾聴」と「質問」です。
傾聴
1つ目のステップは傾聴、子どもの話をよく聴くことです。
まずは、子どもが言っていることを聴きましょう。
途中で話をさえぎったり、アドバイスなどを挟まないように注意してください。
また、子どもにとって「きちんと話を聞いてくれているんだな」と伝わるように、うなずきや相槌を打つとさらに良くなります。
質問
コーチングにおいて、傾聴と同じくらい大切なものが、質問です。
子どもが表現していることを尊重しながら、質問してみましょう。
答えがはい・いいえのクローズドクエスチョンではなく、たとえば、「どうしてそう思ったの?」「どうすればできると思う?」のような子どもが自由に答えられるオープンドクエスチョンを心掛けてください。
質問を通して、コーチングの肝である、子どもの中にある答えを引き出すことが大切です。
もっと学びたいときにおすすめの本【2選】

この記事では子育てコーチングの導入部分を紹介してきました。
さらに子育てコーチングについて学びたい、習得したいという方には、コーチングの本を読んでみることをオススメします。
子育てコーチングの教科書
| タイトル | 子育てコーチングの教科書 |
| 著者名 | あべまさい |
| 出版社 | ディスカヴァ-・トゥエンティワン |
| 出版日 | 2015年03月 |
“教科書”と入っているタイトルですが、寄り添ってくれるような文章で、とても読みやすく、繰り返し読んでいます。コーチングをもっと学びたくなりました。
BookLive「子育てコーチングの教科書のレビュー」
子育ての様々な子供とのコミュニケーションについて失敗談を交えながらコーチングの手法で解決する方法。(中略)
BookLive「子育てコーチングの教科書のレビュー」
我が子の最高の笑顔と能力を引き出すためにこの本をバイブルにして、日々を大事にしていこうと思います。
子どもの心のコーチング
| タイトル | 子どもの心のコーチング 一人で考え、一人でできる子の育て方 |
| 著者名 | 菅原裕子 |
| 出版社 | PHP研究所 |
| 出版日 | 2007年10月17日 |
ヘルプではなくサポート。
BookLive「子どもの心のコーチング 一人で考え一人でできる子の育て方」
子どもを自律させるのが親の役目。
子どものひびのために花の種を蒔くことが親の仕事。
我が子が「一人で考え、一人でできる子」になれるよう、子の良き理解者として、子の成長をサポートしようと思った。
BookLive「子どもの心のコーチング 一人で考え一人でできる子の育て方」
まとめ
今回は子育てコーチングについて紹介してきました。
・子育てコーチングでは子どもの自主性や自己肯定感を養える
・コーチングのスタートは「傾聴」と「質問」
・もっと深く知りたいときは、本で学ぶのがオススメ
皆さんもできるところから生活に「子育てコーチング」を取り入れてみてはいかがでしょうか?