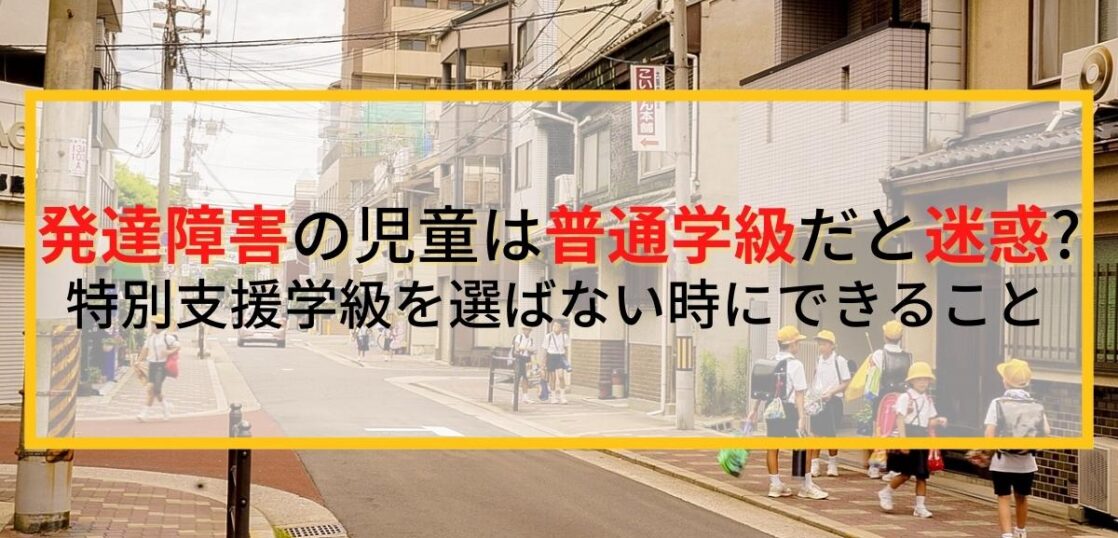皆さんこんにちは!本日も発達障害等に関する学びや情報交換の場所なることを願って投稿させて頂きます。
今日のトピックは「発達障害と、普通学級での迷惑」についてです。
発達障害を持つお子さんの学習環境をどうするか、お悩みではありませんか?
「普通学級に入れたいけど、先生や他の児童の迷惑じゃないかな?」「いじめられたらどうしよう……」と、不安に思われている保護者の方もいらっしゃるでしょう。
この記事では、発達障害を持つ児童と普通学級への関わりにスポットを当て、考えられるメリット・デメリット、普通学級で過ごす時の工夫などをお伝えしていきたいと思います。
一緒に、お子さんの学習環境について勉強しましょう!
目次
発達障害の児童は普通学級だと迷惑?
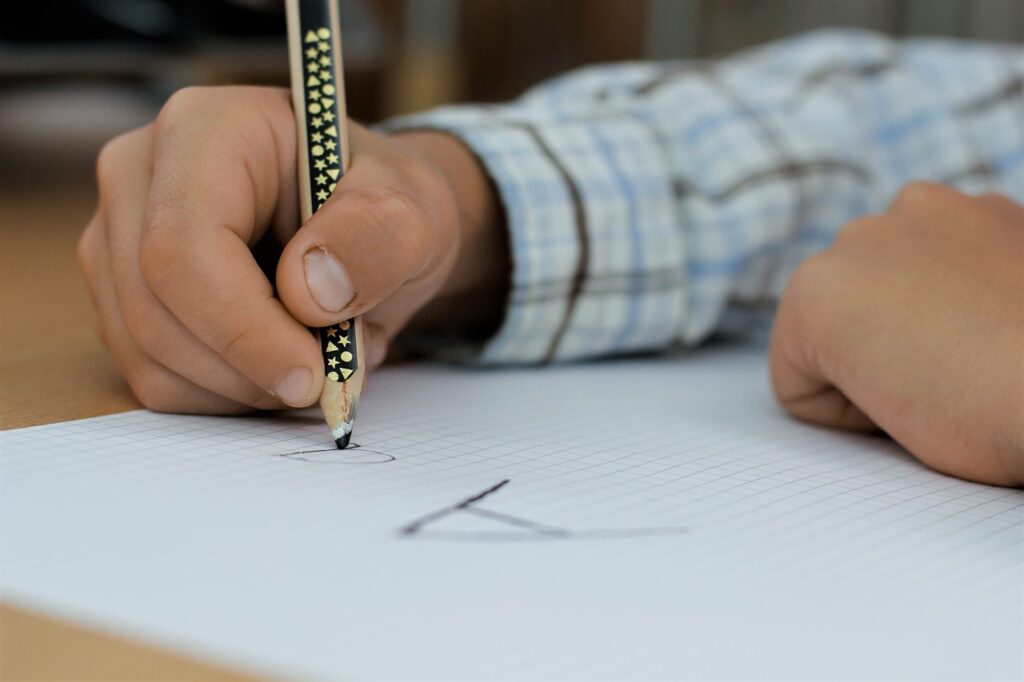
SNSで保護者のリアルな意見を調べたところ「発達障害児が普通学級にいるのは迷惑」と感じる人が少なからずいると判明しました。
一部ツイートをまとめた結果は以下の通りです。
- 「発達障害児が普通学級に居て迷惑をしている」と生徒を通して保護者が訴えても意見を認めてもらえない
- 発達障害があるのに普通学級に入れた結果、変な行動をして迷惑をかけて多くの普通の子に支障が出る
- 発達障害等があるなら見合った特殊学級に入れれば良い
以上のように「発達障害児が普通学級にいると障害のない同級生に迷惑をかけるのでは?」と懸念する様子がうかがえます。
例えば周囲との違いやコミュニケーションのすれ違いなどからトラブルに発展するケースや、発達障害を持った児童への対応で授業が中断するケース。他の児童の学習に影響が出てしまうと苦情が出てしまうのは明白です。
しかし、反対に良い結果となったケースも存在します。
私は発達障害のグレーで、ずっと普通学級に在籍していました。
(中略)
普通学級に通ったからこそ行きたい大学に行けて、いわゆる普通の学生生活も経験出来たのかなと思っています
ルルーこと西濱優衣香/HSP・ASD当事者・音大生ピアノ講師
発達障害を持った児童と発達障害のない児童が入り混じり学習や交流することで、多様性について学びより柔軟な人間関係を築けた例もあるのです。
▼グレーゾーンについては当ブログ内でも別記事として紹介しています。興味のある方はご覧ください。
発達障害児の学習環境

小学生に進学するタイミングで選択できる学習環境は、普通学級を除いて数種類あります。
- 特別支援学校
- 特別支援学級
- 通級による指導
- 交流級
発達障害児のお子さんをどの学習環境に入れるべきか悩む保護者の方は多いですが、どの学習環境も一長一短です。
障害の状態が軽度であれば周囲の児童と同じ普通学級(通常学級)に通う方法もあります。
しかしグレーゾーンのお子さんへの対応は難しいかもしれません。判断基準があいまいだからです。
あるいは支援級に行きたいのに、診断がついていないので行けない場合もあるでしょう。
学習環境の種類
現在日本では発達障害を持った子ども達の周りには様々な学習環境があります。
特別支援学校
重い障害などから通常の学校に通う事が難しい児童を対象に、「生活上の自立」ができるように知識と能力の習得を支援する学校です。
幼稚部/小学部/中学部/高等部があり、それぞれに応じた教育を受ける事もできます。
特別支援学級
小学校・中学校の中に置かれています。障害などから通常の授業に参加しにくい児童を対象に、少人数でそれぞれの障害に合わせた授業や指導が行われます。
以前は「特殊学級」と呼ばれていました(2007年の学校教育法改正に伴って名称が変更)。
通級による指導
周囲の児童と同じ普通学級に在籍しながら、障害に応じた個別の指導を受けるなど、特定の活動を行うことができます。
「通級」「通級指導」「通級制度」とも呼ばれます。
交流級
特別支援学級に在籍しながら、ホームルームや給食の時間、一部の授業など、特定の活動を普通学級で一緒に行うことができます。
受け入れの対象となる障害の種類や程度は、地域によって異なります。
また、各学校によっては通級や交流級が無い場合もあります。
学習環境選定時の見極めポイント
実際にどの学習環境を利用するのかは、各市町村の教育委員会の判断や、障害の状態、児童が持っている学習環境への希望、学校側の受け入れ状況など、相談して擦り合わせた上での決定となります。
学習環境の選定時のチェックポイントは「45分間の授業に耐えられるか」「他の児童に暴力などを振るわないか」がよく挙げらます。
普通学級から特別支援学級への転級や、特別支援学級から普通学級への転級も可能であるようです。(詳しくは各学校へ問い合わせて下さい)
お子さんのその時その時の状況に合わせて、学習環境を選べそうですね。
学校見学も選択時の参考に
下記の動画は自閉症スペクトラムと診断された朝陽くんの親御さんが、実際に学校に見学に行かれた時のものです。
質問内容なども参考になりますのでぜひご覧下さい。
合理的配慮により発達障害児の学習環境は広がる
2016年4月に「障害者差別解消法」が施行されたことで、普通学級においても障害を持った児童への「合理的配慮」が義務付けされました。
参考元:内閣庁「障害を理由とする差別の解消の推進」
「合理的配慮」って、具体的にはどのようなものなんですか?
現場の配慮により、発達障害児における学習環境への選択は幅が広がったといえるでしょう。
障害が軽度で集団の中で一緒に活動することが充分できるようであれば、他の児童と同じ普通学級に所属して通常の授業へ参加が可能です。
現状は学習環境にムラがある
特別支援学級が1クラス約8名であるのに対し、普通学級は標準1クラス40名(小学1年生は35名)での一斉授業になります。
「合理的配慮」が義務付けられたといっても、先生1人では生徒ひとりひとりに合わせた対応を十分に取れないのが現状です。
発達障害には早期の療育が効果的とされているので、普通学級にこだわらずに特別支援学級を選択し、まずは個人のペースで学習と周囲との関わり方のコツをつかむ方法も効果が得られるかもしれません。
そして充分に自信がついてから普通学級に転級するのも1つの手段といえそうです。
普通学級の方が良いか特別支援学級の方が良いかは環境によって大きく左右され、学校それぞれで特色は異なります。
どのような先生がいるのか、同時期に同じ場所で学習する他の児童がどのような子かによっても変わってきます。
実際にはメリットやデメリットだけでは計れないのが現状のようです。
去年までは普通級でOKだったのに、今年の先生は配慮が足りない…などもあります
通うのはお子さんなので本人がつらい思いをしないで済むように、お子さん自身の希望や先生の考えなどを良く聞いて、相談しながら学習環境を決めていきましょう。
Twitterでは様々な環境からの声があります。
普通学級に通うメリット・デメリット

発達障害を持った子どもが普通学級に在籍すると、どのようなメリットとデメリットが得られるのでしょうか?
普通学級に通う場合のメリット
一般的なカリキュラムで授業を受けることができる
特別支援学級ではひとりひとりに合わせた学習ペース。故に学習内容の遅れが気になる保護者の方はいらっしゃします。
比べて普通学級であれば、周囲の児童と同じカリキュラムで授業を受けるので、特別支援学級のように学習内容の遅れへの心配は減るでしょう。
より多くの子ども達と触れ合うことができる
特別支援学級に入ると、少人数の環境だけで交流が完結してしまいがちです。
他の児童との触れ合いができるように交流の時間が設けられるものの、機会としてはどうしても普通学級よりも少なくなります。
普通学級に仲の良い友達がいる場合は、一緒に授業を受けたいという理由などから普通学級を選択することもあるでしょう。
環境次第では、発達障害を持った児童と発達障害の無い児童が入り混じれば、より多様性に富んだ経験を積めるかも知れません。
良い刺激を与え合えば、みんなで成長できる可能性があります。
一般の高校へ進学しやすくなる
一般高校への進学を目標にする場合、普通学級への選択を推奨します。
高校受験には内申点が必要ですが、支援級は内申点がつかない自治体・学校が多いからです。
高校は小学校や中学校のように義務教育ではないので、特別支援学級に関する定めがありません。
発達障害を持った学生への支援環境が整っていない場合があります。
したがって小学校・中学校では特別支援学級に通っていても、高校になってから急に普通学級に入らなければならなくなる可能性があります。
残念ながら、内申点は普通級に登校して生活態度も整えないと…というのが実情のようです。
普通学級に通う場合のデメリット・リスク
普通学級に通うと学習への不安や学校生活でのストレスで、不登校などの二次障害に繋がるリスクがあります。環境によってはいじめなどに発展してしまうケースも考えられます。
デメリットやリスクもしっかり見据えて、慎重に検討しましょう。
療育に当てる時間が少なくなる
普通学級では通常の学習にほとんどの時間を割くため、特別支援学級に居る場合に受けられるような特性に合った指導や支援を受ける時間は少なくなってしまいます。
発達障害には早期の療育が効果的であるとされています。
場合によっては普通学級で過ごすかたわら「通級による指導」を受けるか、放課後等デイサービスの利用など学校以外の場所で、障害の特性から起こる苦手への対処法を学ぶ必要が出てくるかも知れません。
「放課後等デイサービス」は、2012年4月に児童福祉法に位置付けられた支援方法です。様々な障害を持つ子どもに対して、学校や家庭とは異なる環境を通して、ひとりひとりに合った発達支援を行います。
「子どもの最善の利益の保障」「健全な育成」が主な目的です。また、保護者へのケアも行っています。(詳細は団体によって異なります)
参考元:厚生労働省 「放課後等デイサービスガイドラインについて」
授業ペースについていけない可能性がある
発達障害の特性によっては授業に集中できなかったり、充分理解する前に授業内容が先へと進んでいってしまったりということもあるかも知れません。
一斉授業についていけない場合、発達障害児はわからないまま放っておかれたり、逆に発達障害児に先生が掛かりきりになった結果、授業が中断される事態に繋がるおそれがあります。
頻繁に授業の中断が余儀なくされると他の児童や保護者から苦情が出るかも知れません。
発達障害児側すると、自分が授業を中断させる原因となってしまい、悩んでしまうケースもあるようです。
落ち着いて過ごせない可能性がある
発達障害児が大勢の中で生活するというのは、多くのストレスにさらされることでもあります。
大きな物音や話し声、誰かにぶつかったりぶつかられたりといった突発的な出来事もあるのです。
障害の特性をあらかじめ伝えていたとしても、突発的な出来事の発生を全て防ぐのは不可能。
臨機応変な対応が必要な環境で落ち着いて学習できず、結果的にお子さんが学校へ通いたがらなくなる可能性も出てきます。
周囲の児童とのトラブルや、いじめを受けることもある得る
コミュニケーションの行き違いによって周囲の児童との間にトラブルを抱える事もあり得ます。保護者を交える騒動となることもあるかも知れません。
また、宿題を免除するなどの配慮をされ過ぎることで周囲の児童の方にかえって不満が溜まり、いじめに発展してしまうケースもあるようです。
発達障害の特性からの苦手や対人関係への不安などから、不登校や鬱(うつ)、引きこもりなどの状態におちいってしまう事です。
「迷惑」にならないために:普通学級に通う場合にできること

普通学級に通うと決めたならば、デメリットやリスクはできるだけ減らしたいですよね。
学校側の支援を期待するだけではなく、お子さん自身や保護者にはどのようなことができるでしょうか?
学校との連携も大切にしていきたいところです。
工夫と療育による、授業やトラブルへの備え
お子さん自身が苦手を克服するよう頑張って工夫をこなすだけでも、授業ペースへの不安やトラブルへの備えが可能です。
授業への備え
授業のペースについていけるように、発達障害の特性に合わせて工夫する事ができます。
受け入れが可能かどうかは学校との相談の上にはなりますが、保護者が授業に付き添うことで上手くいくケースもあるようです。
【特性に合わせた工夫の例】
- 読み書きが苦手な場合
タブレット端末を使い、黒板を撮影する・音読機能を使用する - 集中力が続かない場合
他からの刺激を減らせるよう、授業中は窓にカーテンを引いてもらう - 口頭での説明の理解が苦手な場合
あらかじめ授業の要点をまとめて書いておく
上記の例のように工夫や療育などで苦手分野を相殺していけば、学習への意欲を向上できるかもしれません。
お子さんの特性や個性に合わせて、無理のない範囲でできることを見つけていきましょう。
周囲への配慮
授業中に発達障害児が補助用具を使った場合、音が鳴ってしまい周囲の児童の集中のさまたげになってしまう可能性もあります。
事前に周囲の理解を求めたり、先生と一緒に更なる工夫を考えたりといったことも必要になりそうです。
【例】
授業中に教室を出入りする必要があれば、他の児童の前を横切らずに済むようにドアの近くの席にしてもらう など
トラブルへの備え
コミュニケーションが苦手、衝動的に手が出てうなどで周囲とのトラブルになる可能性もあります。
トラブルへの備えには周囲に理解と協力を求めると同時に、お子さん自身も周囲との関わり方を学ぶことが必要です。
具体的に伝えなければ周囲もどう動けば良いのかわかりません。あらかじめ伝えておけば防げるトラブルもあるはずです。
またお子さん自身にも、療育などでソーシャルスキルを身に着けるなどの工夫ができます。
周囲との関わり方を知識として学ぶことで、コミュニケーションなどのトラブルを減らすことができるかも知れません。
周囲に理解と協力を求める為には「どのような特性があるのか」「どういった場合には、周囲にどう対応して欲しいのか」などを伝えておくと良いでしょう。
療育・放課後等デイサービスについては、
↓こちらのサイトも参考にしてみて下さいね。

横浜市都筑区児童発達支援と放課後等デイサービス
運動・学習療育アップ
学校との連携
保護者と先生の方針を一致させる
保護者と先生の考えが食い違っていると、お子さんは混乱してしまいます。
発達障害の有無に関わらず全ての関係に言える事ではありますが、より良い環境を整えるためには学校との連携も不可欠です。
先生の持っている考えを聞いたり、家庭での様子などを伝えたりすることで、お子さんに合った学習環境に近付けることができるでしょう。
保護者も先生も人間!大人も休める環境に
保護者も先生も人間なので労わり合い、時には休むことも必要です。
学校とは児童だけでなくその保護者や先生など、とても多くの人が集う場所ですから、人間関係もその分複雑になります。
発達障害を持ったお子さんであれば、周囲との違いからトラブルが起こってしまったり、苦情が寄せられてしまったりする事もあるかも知れません。
また、児童一人ひとりに細かな対応をしなければならない先生も大変な仕事です。事態によっては保護者と保護者の板挟みになってしまいます。
地域の窓口などで相談することもできますよ!
つらくなったら特別支援学級へ
無理に普通学級での学習を続けずに、特別支援学級へ移ることも選択のひとつです。
発達障害の特性による困難は状況によって変わります。または周囲との関わりの中でお子さんが疲れることもあります。
万一の場合に備え、状況に応じていつでも転級できるよう、学校側や市町村の教育委員会などと事前に相談や打ち合わせを行っておくと安心ですね。
まとめ
- 普通学級(通常学級)に通うことは、選択肢のひとつ!
- 環境次第で、良いケースにも悪いケースにもなり得る!
- 工夫や療育など、トラブルに備えてできることもある!
- 先生との相談や状況に応じた転級など、学校と連携しよう!
お子さんがどのような環境に出会えるかは、お住まいの地域や先生によって大きく変わってくることもあるでしょう。
メリット・デメリットだけではなく、事前にどんな学校か調べたり先生と相談を行ったりなど、しっかり準備して就学先を決めたいですね。
お子さんが小学校・中学校で過ごすかけがえのない時間。できる限りの工夫と備えで、楽しく学習できる、より良い環境に近付けられると良いですね!
ひとりでも多くの子どもが、自分に合った「学びの場」に出会えることを願います。
もっと詳しく・他の情報も知りたい方は、
こちらも参考にしてみて下さい!
↓
横浜市都筑区児童発達支援と放課後等デイサービス
運動・学習療育アップ