皆さんこんにちは!本日も発達障害等に関する学びや情報交換の場になることを願って投稿させて頂きます。
今日のトピックは「発達障害と不眠」についてです。
発達障害の特性を持つ子どもが不眠症状を抱えることは珍しくありません。
この記事では発達障害の子どもの不眠問題や対処法を解説しました。是非参考にしてください。
目次
発達障害と不眠症(睡眠障害)の関係
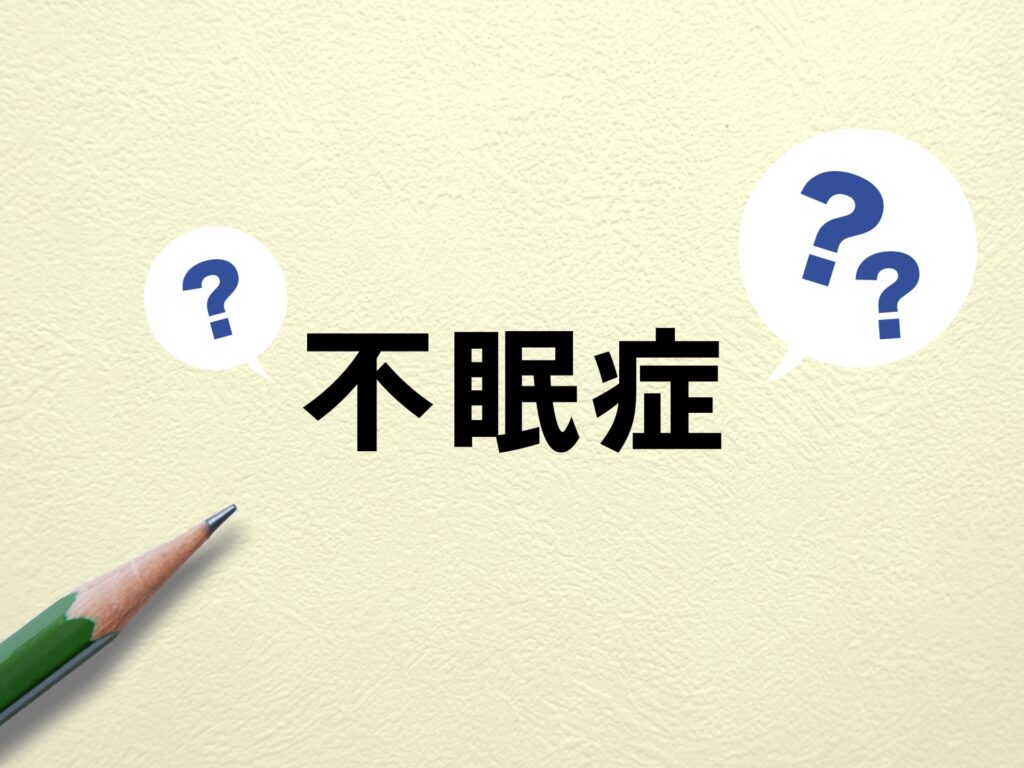
不眠(症)とは睡眠障害の一つであり、以下の症状を引き起こし睡眠不足になります。
- 寝付くまでに時間を要する
- 夜中に目が覚めてしまい眠れない
- 目が覚めてしまった後に照明やテレビを付けたり、両親がそばにいてくれないと眠れない
発達障害のうちASD(自閉スペクトラム症)およびADHD(注意欠如・多動性)の症状を持つ方は、睡眠障害(不眠症など)を併発する可能性が高いといわれています。
たとえばこだわりの強いASDの症状を強く持つ人が、寝る前に趣味に没頭してしまい寝る時間になっても止められません。
結果的に睡眠時間が削られてしまう状況はありえるでしょう。
発達障害と睡眠に関する記事がございますので、併せてご覧ください。
不眠症に陥る原因

発達障害と睡眠障害が併発する原因は不明です。
しかしながら、発達障害は脳機能が十分に働かないこと、睡眠と覚醒を調節する中枢神経系の機能が十分に働かないことが関係している可能性があります。
具体的な原因をご紹介しますので参考にしてください。
気持ちの切り替えが難しい
こだわりや過集中により、就寝前に取り組んでいたことから睡眠へと切り替えるのが難しいことがあります。
感覚過敏
音や光に対しての感覚が過敏なために覚醒しやすい傾向にあります。
睡眠に関するホルモン(セロトニン・メラトニンなど)の不足
発達障害のある人は、メラトニンやセロトニン・メラトニンなど、ホルモンの元となるトリプトファンの量が、通常値よりも大きく離れていると考えられています。
これらのホルモンの過不足は、体内時計をコントロールする上で悪影響を及ぼすため、不眠症状を起こしやすいとされています。
感覚統合の未熟さ
感覚統合が未熟で、自分の身体の位置や動き、力の入れ具合を感じる固有覚が未発達である場合、ボディイメージがつきづらく、コントロールが働かなくなります。
このことが不安感につながり、不眠の原因となるとされています。
うつ
うつをはじめとする発達障害の二次障害として発症した症状が、不眠に繋がることもあります。
不眠による悪影響

発達障害の方が不眠症になるとどういった悪影響を及ぼすかについて、一覧にまとめました。
- 集中力の低下
- 行動の変化
- 感情の不安定化
- 社交的関係の問題
- 自尊心の低下
集中力の低下
集中力が低下すると作業スピードが遅くなる、情報処理能力や判断力の低下、モチベーションの低下を引き起こします。
行動の変化
倦怠感やイライラ感を引き起こすため、体が十分に動かなかったり突如怒り出すかもしれません。
結果的に不眠症がさらに重症化する可能性があります。
感情の不安定化
感情の不安定化が進むと以下の状況に陥ります。
- 怒りっぽくなる
- 涙もろくなる
- 不安感が高まる
- 物忘れが激しくなる
- 喜怒哀楽が激しくなる
本人も周りの人もどうすればいいのかわからず互いに疲れてしまいます。
社交的関係の問題
不眠症により疲れがたまり集中力が低下しているため、社交的な場面に参加する意欲が低下、参加してもコミュニケーション能力が低下しているので十分に対応できません。
自尊心の低下
不眠症によって疲れがたまっているため、正常な判断が出来ず自己評価が低くなったり自己批判します。
家庭で可能な対処法

不眠症に陥ると、日中の集中力ややる気がなくなり生活しにくくなってしまいます。
本項では、規則正しい生活を取り戻すために家庭で可能な対処法を確認していきましょう。
生活リズムを整える
生活リズムを見直すことは、不眠を改善することにつながります。
具体的には、早寝早起き、一日三食を規則正しくとる、昼寝をしすぎない、適度な運動、夕飯やお風呂の時間の見直しが大切です。
入眠前のローテーションを作る
入眠前に決まった行動をとることで、睡眠に入りやすくなります。
寝る前に歯を磨いたら絵本を一冊読む、などの簡単な取り組みを決めておきます。
毎日同じ習慣・手順を踏んで眠りにつけば、睡眠に取り掛かるのがスムーズになるでしょう。
気分転換する
どうしても入眠しづらいときは、無理に寝かせようとすると、かえって逆効果になる可能性もあります。
そこで、気分転換するべく、思い切って起きてしまうのも一つの方法です。
部屋の電気をつけて布団の外に出てみたり、リラックスできる音楽を聴いてみましょう。
眠れないことで不安になったり寝ようと意識しすぎることで、興奮状態に陥り眠れなくなることは少なくありません。
就寝環境を整える
寝室の環境は、睡眠の質に大きく関係します。
眠りにつきやすくなる空間づくりはもちろん、朝起きやすくなるように工夫しましょう。
ベッドの位置を日当たりの良い場所に変えたり、遮光性の高いカーテンを利用するなどの工夫がおすすめです。
その上で毎朝決まった時間にカーテンを開け、起床時に日光を浴びるよう心がけてください。
インテリアの色はなるべく落ち着いた色を選ぶと、より眠りにつきやすくなります。
また、発達障害のある子どもの場合、感覚統合が未熟なことからボディイメージがつきづらく、不安感を引き起こしていることがあります。
この場合、体にぴったりとフィットするような寝具があると、寝付きやすくなるでしょう。
病院で可能な対処法

家庭内で環境を整えても状況が変わらない場合は、病院での処置が必要です。
病院ではどのような処置が必要なのかを解説していきます。
受診する科
推奨する受診科は、発達障害を担当している病院のうち心療内科や精神科、小児科などです。
初回は保護者同伴で、どんな生活態度なのかを聞かれます。
「いきなり受診は不安」「受診したくても予約が取れない」といった場合は、お住いの発達障害者支援センターで今後について話し合いましょう。
発達障害者支援センターとは、発達障害を抱えている人へ支援することを目的とした専門機関です。一般的には都道府県や社会福祉法人、特定非営利活動法人などが運営しています。
参考元:発達障害者支援センター・一覧
薬物療法
家庭内での環境を整えても不眠症が解決しない場合はスクリーニング等の後、薬物療法で対処します。
一般的には睡眠導入を誘発する薬を処方されることが多いでしょう。
まとめ
発達障害のうち、ASD(自閉スペクトラム症)やADHD(注意欠如・多動性)を抱える人は不眠症(睡眠障害)に陥りやすいことが分かりました。
家庭内で入眠しやすい環境を整え、時には薬物療法を活用して不眠症を解消していただければと思います。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。


