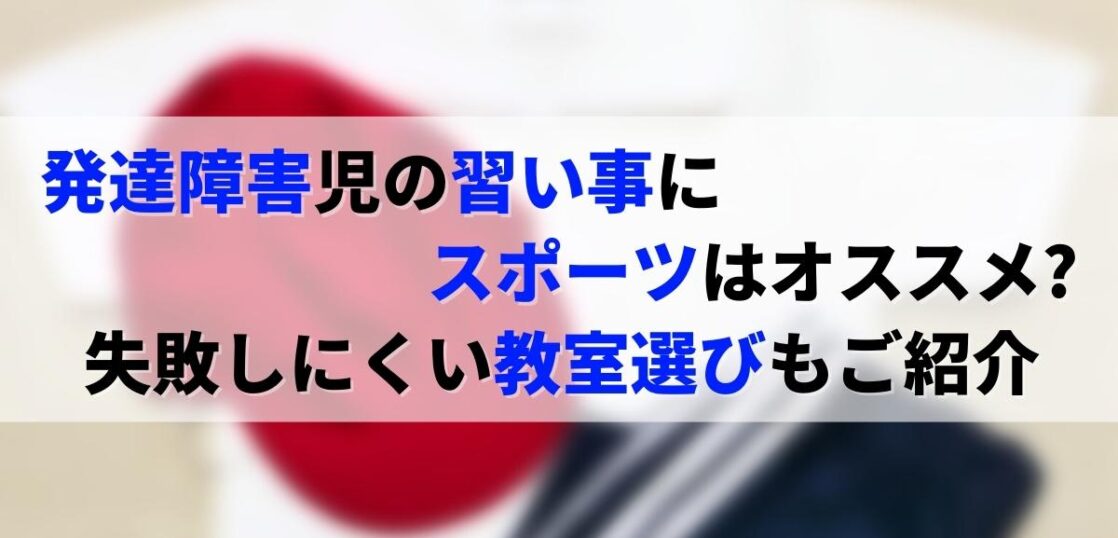皆さんこんにちは!本日も発達障害等に関する学びや情報交換の場所なることを願って投稿させて頂きます。
今日のトピックは「発達障害児の習い事にスポーツは適正かどうか」についてです。
発達障害は大分類として自閉スペクトラム症であるASD、多動・注意欠如が見受けられるADHD、学習障害が目立つLDがあります。
今回は発達障害児全般を対象に、向いているスポーツの習い事やおすすめな理由、習い事の選び方、スポーツ以外におすすめな習い事を解説します。
目次
発達障害児は少人数・個人スポーツの習い事に適正あり

結論からいうと、発達障害児に少人数・個人スポーツの習い事は適正があります。自分のペースで学べる可能性が高いからです。
発達障害のお子さんは相手のペースに合わせるのが苦手で、自分のペースを乱されると集中力が欠けてしまいます。
その結果、落ち着けず習い事が長続きしなくなるのです。
その点少人数・個人スポーツは基本的に自分のペースで学べるため、発達障害の特性に合っているといえます。
コミュニケーションが苦手な発達障害の子供も安心というメリットもありますよね。
ここからは、特におススメできる少人数・個人向けスポーツを3点ご紹介します。
水泳
水泳は習い事の中で人気ナンバーワンのスポーツです。
学校の授業カリキュラムに入っているので、子供が苦労しないようにという親心があるみたいですね。
そして、水泳には以下のメリットがあります。
【水泳のメリット】
- 水泳は体を左右対称にバランス良く使うので、適切な体の使い方を学ぶには最適
- 浮力があるので、体力がない子供でもできる
- 基本的に個人で行う習い事なので、自分のペースを保ちやすい
- 全身を使った運動は脳の発達にも良いと言われている
水泳の効果をより詳しく知りたい方は、別途記事を用意していますので興味があればご覧ください。
武道(空手・剣道)
武道にもメリットがあります。
【武道(空手・剣道)のメリット】
- 個人スポーツである
- スポーツを通して礼儀作法(相手を思いやる心・挨拶など)を学ぶことが可能
- 集中力を養えるため、学習にプラスの効果がある
記事投稿者である私は小学校から高校まで剣道をしていました。
剣道経験者として実感した点は、礼儀作法を身につけておいて良かったと実感しています。
剣道によって幼いころから「挨拶、ありがとう、すみませんでした」といった礼儀作法を身につけられたからです。
ダンス
最後に、ダンスのメリットについて紹介します。
【ダンスのメリット】
- 自分のペースで踊ることができる(ダンスは個人レッスンな場合が多い)
- 音楽に合わせて体を動かすので、体だけでなく脳の活性化にもつながる
- 好きなように体を動かせる(ADHDの多動性や衝動性も気にならない)
リズムを体得するには時間がかかるかもしれませんが、細かいルールに縛られることなく、楽しみながら学べます。
以上の通り、各スポーツによって特色は異なりますし、発達障害の特性も人それぞれで異なります。
保護者の方はお子さんの特性とスポーツの特色が合ったスポーツを選んであげてください。
団体スポーツでも得られるものはある
発達障害児に団体スポーツが向いていない理由は、相手の立場に立って考えてたり、相手のペースに合わせて行動する協調性が必要なためです。
団体スポーツはチームプレーを重視するので、個人スポーツよりも高いコミュニケーション力が求められます。
よって団体スポーツは無理ではありませんが、個人スポーツに比べてハードルが高くなることは覚えておく必要があります。
スポーツの習い事をするメリット

発達障害のお子さんにスポーツの習い事をおすすめできるメリットは主に3点あります。
- 楽しみながら社会性を育む
- 適切な体の使い方を学ぶ
- 運動による学習へのプラス効果
楽しみながら社会性を育む
習い事にスポーツがオススメな理由は、人間関係や社会生活で困らないためのスキルを楽しみながら学べるからです。
以下に示すように、スポーツには社会性を育むための要素がたくさん含まれています。
【社会性をはぐくむための要素】
- ルールを守ることの大切さを学ぶ
- 役割を理解することによって責任感を養う
- 対戦相手がいる場合、相手の立場で物事を考える
- 挨拶や礼儀作法などを学ぶ
上記であげた社会性は、発達障害児だけではなく定型のお子さんであっても、社会から孤立しないためにも、是非とも身につけて欲しいものばかりです。
しかし社会性が大切だとしても、大人ではなく子供が、授業以外に座ったまま先生の授業を聞いて学ぶとしたらどうでしょう。
話の途中で退屈になってしまい、興味を示さない可能性がありますよね?
子供は楽しいことが大好きなので、楽しみを提供するスポーツを上手く活用するのは賢いやり方です。
以上のことから、楽しさの中に経験して欲しい学びを含めるスポーツの習い事が子供の学びには効果的と言えます。
適切な体の使い方を学ぶ
発達障害児の身体的な特徴として、定型のお子さんよりも体のバランスが取りにくかったり、道具を使いこなすのに時間がかかったりと不便な状況に陥りやすいです。
発達障害児は脳の一部の動きに異常が見られるため、周囲からの刺激や自分自身の体に関する情報をうまく取り込めず、適切に体が反応しない場合があります。
【発達障害児の身体的な特徴一例】
- 転びやすい
- ブランコや滑り台でバランスを上手く保てない
- 頭を上手く洗えない
- 折り紙の折り目を合わせられない
- ハサミを上手く使えない
よって発達障害児には体の適切な動かし方を身に付ける必要があるのですが、体の動かし方は感覚的なものなので、言葉で説明するのは難しいと言われています。
以上のことから、感覚的な事を学ぶには「実際に体を動かして体験して、経験値を蓄積する」方法が有効と言えます。
適した身体の動きを学ぶ際に「楽しみながら、体の動かし方を学べる」スポーツは、子供たちにとって最適なツールと言えるのです。
運動による学習へのプラス効果
最近の脳科学の研究で、運動は脳に良い効果があることがわかってきました。
例えば「脳を鍛えるには運動しかない(NHK出版・2009年)」の著者であるハーバード大学医学部のジョン・J・レイティ博士は、著書の中で運動には以下の効果があると伝えています。
【運動による脳に良い効果(著書より抜粋)】
- 脳細胞が増える
- 気持ちを前向きにして集中力を高めるドーパミンが作られる
- うつの予防につながるセロトニンが作られる
- 集中力や記憶力が高まる
- 学力があがる
もちろん個人差は存在するものの、それでも運動が「集中力や記憶力」や「学力」に良い効果があるという調査結果は期待が膨らみます。
以上のような効果を生かした「運動療育」というものもあり、運動療育については別途記事を設けておりますので興味があればご覧ください。
失敗しにくいスポーツ教室の選び方

次にどうすればなるべく失敗をせず、長く通える教室に出会えるのかを紹介します。
発達障害に理解ある教室を選ぶ
発達障害の特性に合ったスポーツを選ぶのと同じくらい大切になるのが、発達障害に理解ある教室を選ぶことです。
発達障害に対する知識や理解を持つ教室でない場合、子供たちが辛い経験に遭遇してしまうかもしれません。
保護者の方はお子さんがつらい思いをする前に、教室の先生に発達障害に対する知識や理解があるのかを尋ねてみましょう。
希望する教室に発達障害への理解が難しそうであれば他を当たるか、保護者の方が率先して教室へ情報提供するなどの行動が必要になります。
とはいえ、できれば発達障害の子供を受け入れて指導した実績のある教室を選ぶのが望ましいでしょう。
ここで発達障害に理解ある教室を1つ紹介しますね。
上記ツイートは発達障害児を中心とした特性のある子ども達のフットサルチーム「リトルキッカーズ」のツイッターアカウントのものです。
フットサルを通して、集団生活に必要なスキル向上を行なっています。
また子供だけでなく、親たちが悩みを打ち明けたり、相談したりし合える居場所にもなっているようですね。
活動内容を詳しく知りたい方は「リトルキッカーズ(HP)」をどうぞ。
「フットサル」は団体スポーツなので、発達障害の子供にとって苦手とされていますが、発達障害に理解ある教室ならば「団体スポーツ故の苦手を楽しみに変える」とのことです。
放課後等デイサービスを利用
ここまでの説明を読んで「スポーツ選び。教室選び。自分で探すのって結構大変かも…」と感じた保護者の方には「放課後等デイサービス」をオススメします。
障害を抱えている子供の居場所と療育を提供するサービス。
それでは、放課後等デイサービスを利用するメリットを2つ紹介しますね。
メリット1:発達障害の特性を理解したスタッフがいる
放課後等デイサービスを利用する1つ目のメリットは「発達障害の特性を理解したスタッフが対応すること」です。
発達障害に対する誤解や偏見は未だ残っています。意を決して習い事を始めたとしても、誤解偏見が子供たちの意欲やる気を奪いかねません。
逆に障害に対する理解がある場合、子供たちは安心して新しいことに挑戦できるのです。
「わかってくれない。理解してくれない」という心配をする必要がありません。
メリット2:運動療法に力を入れた放課後等デイサービスの増加
2つ目のメリットは「運動療育に力を入れた放課後等デイサービスが増えてきている」ことです。
「発達障害の子供、スポーツで自信 専門の教室広がる」
参考元:日本経済新聞 2018.12.17
もちろん「運動療育」は単に子供を遊ばせるだけでなく、発達障害の特性を理解した上で、子供の発達につながる運動プログラムを提供しています。
つまり、放課後等デイサービスは「発達障害の特性に合った運動療育」と「理解ある指導者」との両方のニーズを一度に満たしてくれるお得なサービスと言えますね。

横浜市を中心に活動を行なっている放課後等デイサービス「運動・学習療育アップ」では、運動療育に力を入れています。
適切な体の使い方を身につけるだけでなく、学習にも効果があるとされる運動も実施していますよ。
放課後等デイサービス「運動・学習療育アップ」について詳しく知りたい方は以下のリンク先を確認してください。
▷▷▷放課後等デイサービス「運動・学習療育アップ」◁◁◁
スポーツ以外にオススメの習い事ってある?

もしも、子供がスポーツに興味関心を示さないとしたら、どうすれば良いのでしょうか。
全ての子供がスポーツが好きとは限りませんよね。そこで、今後人気が出て来るかもしれない習い事を一つ紹介しますね。
プログラミング
2020年度より小学校でプログラミング教育が必修化されます。
もちろん子供を全員IT企業に就職させることが目的ではありません。
このプログラミング教育の目的は、プログラミング的(論理的)思考を養うことです。
わかりやすく言うと「物事を順序立てて考え、試行錯誤しながら、問題を解決する力」を養うことが目的になります。
プログラミングは発達障害児に少なくとも3つのメリットがあります。
【プログラミングのメリット3点】
- プログラミングはルールが明確。曖昧な表現が苦手、物事は白黒したい傾向にある発達障害児に向いている
- 基本的に個人で学ぶことになるので、自分のペースを保ちやすい
- 自宅に居ながら学べる(オンライン講座)ので、コミュニケーションが苦手でも乗り切れやすい
今後プログラミングや在宅ワークの需要は増える可能性が高まっているため、お試しで子供に勧めてみるのも良いかもしれません。
近年子供向けのパソコン教室を見かけることが増えてきました。放課後等デイサービスでも同様の傾向が見られるので、お近くのデイサービスを調べてみると良いでしょう。
スパーク運動療育
「うちの子は体を動かすのは大好き。でも、家の近くに子供が気に入ったスポーツや教室がない。プログラミングも興味無さそう…」
そんな悩みを持つ方に、自宅で楽しく取り組める「スパーク運動療育」を最後に紹介します。
動画の中では、「スパーク運動療育」著者である清水貴子さんが、さまざまな場所でお子さんと一緒に楽しく体を動かす方法を何種類か紹介しています。
興味を持たれた方は、動画の中で紹介されている「スパーク運動療育」を手に取ってみてください。
本の内容を簡単に紹介すると、単なる「家庭でお手軽にできる運動あそび」の紹介本ではありません。
- 発達障害の子供の脳をきたえるには運動が効果的であることの詳しい説明
- 子供への接し方の8つのポイント
- 発達障害の特性の説明
なども合わせて紹介してあるので、より効果的に運動しながら遊びもできるようです。
イラストが多くわかりやすいため、手始めに自宅で何か始めてみたい方にお勧めします。
まとめ
- 発達障害児に運動の習い事はオススメ
- 集団スポーツより個人競技の方が向いていることが多い
- 発達障害に理解がある教室を選ぼう
発達障害児は、運動が苦手ということも多いため「運動を習わせた方がいいのかな…でも本人の負担になったり、周りの人に嫌がられたりしないかな…」と悩むことも多いかと思います。
ですが解説した通り、運動はメリットがたくさんあるので、ぜひ本人が楽しく続けられる競技・教室をさがしてみてくださいね!
最後までお読みいただき、ありがとうございました。