皆さんこんにちは!本日も発達障害等に関する学びや情報公開の場所となることを願って投稿させて頂きます。
今日のトピックは「発達障害で育てにくい子への接し方」です。
「言うことを聞いてくれない。」「何を考えているかわからない。」ということは子育てをしていると誰しも経験すると思います。
それが発達障害と診断された子だった場合、特に顕著になり、育てにくいと感じてしまいますよね。
今回は、発達障害と診断されたり、育てにくいなあと感じてしてしまったりした場合、子供とどう接したら良いかを紹介していきます。
目次
育てにくい子こそコミュニケーションが大事

家族、親子でコミュニケーションをとることは、発達障害の子が将来、「社会」で支障なく生きていくことに繋がります。
家族は子供が接する最初の「社会」です。この小さな社会での経験が、多くの人が属する社会に馴染むために必要になってきます。
実際、近年の発達障害の増加傾向は、核家族化やスマホ、タブレットの普及によって、家族と接する機会が減ったことが要因の一部として考えられます。
親子で一緒に遊ぶ
子供とコミュニケーションをとるのに最適なのは一緒に遊ぶことです。共に遊ぶことで子供の好みや特性を知ることもできます。
ここで大切なのはしっかり目を合わせることです。
自閉症スペクトラム障害を持つ子供はこだわりが強い傾向があり、一つのおもちゃから目を離さずにずっとそのままでいてしまうことが多いです。このままではコミュニケーションは中々取れません。
そんな時は子供に触ってあげたり、声を掛けたりして目を合わせるようにしましょう。そして、子供と目が合ったら褒めてあげましょう。
これを繰り返していくことで、少しずつコミュニケーションをとることに繋がっていきます。
おススメの遊びは塗り絵
一緒に遊ぶとは言っても何をやったら良いかわからない場合は塗り絵がおすすめです。
塗り絵には以下のような様々な効果があります。
- 色彩感覚を磨ける。
- 達成感を味わえる。
- 脳が活性化される。
- 集中力が身につく
- ペンの使い方のトレーニングになる。
他のにも色んな効果がありますが、今回注目するのは、上の2つです。
塗り絵でコミュニケーション
塗り絵を行うときには色を選ぶ必要がありますよね。
食べ物のように大体の色が決まっているものと家や車のようにどんな色で塗っても良いものがあります。
この色選びの時に親子でコミュニケーションをとりましょう。
「この家はどんな色にしたらきれいかな?」「いつも食べてるトマトはどの色だったかな?」など色々と声掛けをしてあげることで、自然とコミュニケーションをとることに繋がります。
この時に子供に色を押し付けないように注意しましょう。特に発達障害を持つ子供の場合、色に何らかのこだわりがあることが多いです。
発達障害を持つ子の色のこだわりについてはこちらで紹介しています。
また、一つ一つ塗れるごとにしっかり褒めてあげることで、子供も達成感を感じて自信ややる気がアップします。
どのくらい塗れると良いの?
子供と塗り絵をしていて枠からはみ出ていたり、塗れていないところがあったりすると、これで良いのか不安になると思います。
発達のスピードや得意不得意があるので参考程度ですが、年齢に応じた目安はこのようになっています。
| 年齢 | ぬり絵の発達段階 | 塗りすぎ・塗り残し | |
| 第1段階 | 2歳前半~ | 図の中を塗るという認識がなく、 図の上をなぐり描きしたり、 図に点を打ったりして、マーキングする段階 | 塗りすぎあるいは 塗り残しが大変多い |
| 第2段階 | 2歳後半~ | 図の中を塗ることを認識し 始めるが、図の中にギザギザ線や グルグル丸を描いて、「塗れた」と思う段階 | 塗り残しは大変多いが、 塗りすぎはほとんどない |
| 第3段階 | 3歳~ | 図の中を塗ることを理解し、 塗りつぶすことに集中するが、 塗りすぎに注意を払わない段階 | 塗り残しが急減するが、 塗りすぎが増加する |
| 第4段階 | 4歳半~ | 図の中をきれいに塗ることを意図して塗る段階 | 塗り残しと塗りすぎが 共に少なくなる |
えのほん」 メイト
塗り絵はこちらのシリーズがおすすめです。
2歳から3歳
3歳から4歳
| 商品概要 | 自由に遊んで色彩感覚、創造力を豊かに育む、ぬりえ、らくがきの本のシリーズ。 はじめてぬるほんは低年齢版。はみだしてもちょっとしかぬらなくてもOK。 |
| 価格 | はじめてぬるほん 935円 どんどんぬるほん 1,045円 Amazon 2021年8月14日時点 |
| 特徴 | 自由にのびのびと塗ることができる。 ボリュームがある。はじめてぬるほん79p、どんどんぬるほん200p |
| レビュー | 【はじめてぬるほん】 ・2歳9ヶ月の娘に「初ぬりえ」として購入しました。 自由に自分で描いたりする本なので、うちの子が適当に塗っても何とか形になります。(30代女性) ・2歳の娘は今は絵本としてたのしんでいますがもうしばらくするとぬりえとしても楽しめそうです。 (30代女性) 【どんどんぬるほん】 ・思ったより沢山書くところがあって、3才児には一日一枚がやっとこさ・・・ これが全部書き上がったとき、その子の物語になってくれるのが楽しみ。(30代男性) ・親が一緒になってやりたいくらい楽しいシリーズです。(30代女性) |
怒る時に気を付けたいこと
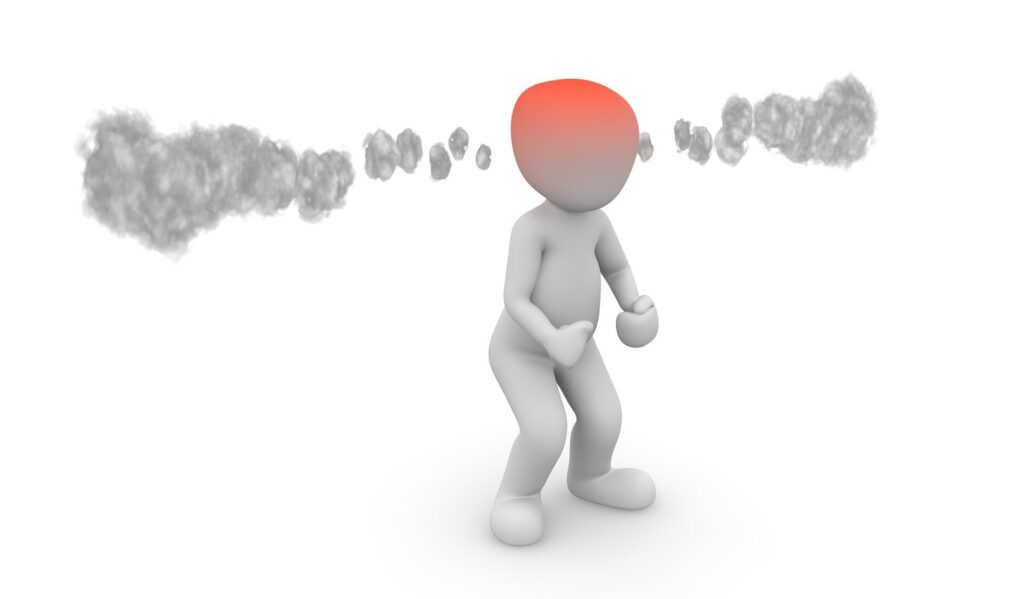
子供を怒ったり、何かを教えることも大事なコミュニケーションです。しかし、やり方を間違えると反って子供の発達を妨げてしまう恐れがあります。
特に発達障害を持っている場合、聴覚過敏になっていることが多いので大きなストレスにもなってしまいます。
聴覚過敏についてはこちらで紹介しています。
まずは自分が落ち着く
子供が何か悪さをしたり、言うことを聞いてくれなかったりすると、どうしても感情的になって怒ってしまいますよね。
しかし、怒る側が感情的になり怖い顔になってしまうと、子供は何が悪かったのかを考えるよりも、恐怖の方を強く感じてしまい、どうして怒られたのかが分からなくなってしまいます。
どのようにして子供に伝えるか一度冷静になって考えてから注意すると良いです。
それでも親だって人間なのでストレスが溜まっているときなどは、ついつい感情的になってしまうものです。
強く怒鳴ってしまったと場合は、感情的になってしまったことを子供に謝りましょう。
その時伝えたいことだけに絞る
一度子供を叱り始めると、連想ゲームのように次から次へと色んなことを思い出し、まとめて言ってしまうことありませんか?
例えば、片づけをしないことを注意していた時に、おもちゃを壊した時のことや買い物で駄々をこねた時のことも、一緒に怒ってしまうなどです。
話が長くなると子供の集中力が切れて、聞いてくれなくなります。また、一度にたくさんのことを言われて混乱してしまうこともあります。
注意するときは、そのとき何が悪かったのかを短く的確に伝えるよう心掛けると良いです。
感情的にならず、その時何が悪かったのかを伝えたり、考えさせたりする。
長くならないように注意!
褒めると脳が発達する

ここまで親子のコミュニケーションについて考えてきましたが、今回何度か出てきた「褒める」ということは子供と接する際にとても重要になってきます。
発達障害は脳の異常が原因であるため、完治しないと考えられています。しかし、発達しにくいだけであって、社会に出ても支障がないくらいに能力を伸ばすことも可能です。
褒められると何が起こる?
褒められるということは大人になっても嬉しいものですが、実は人間の脳は褒められるとお金をもらった時と同じような反応を示すという研究結果があります。
参照 【生理学研究所】「褒められる」ことは報酬— 脳の”喜ぶ”様子を画像で捕らえた!—
子供の場合、行動を褒めることによって、脳が刺激されて発達し、その行動をまたしてくれるようになります。
自己肯定感を高めるにはどう褒める?
褒める効果は行動を強化するだけではありません。自己肯定感を高めたりや自信をつけたりする効果もあります。
発達障害を持っていると成長するにつれて、周囲との違いに苦しみ自己嫌悪に陥ってしまうこともあります。
小さい頃から褒められ自己肯定感を高めていくことで、周囲との関係も良好に築けるようになります。
結果ではなく行動を褒める
褒めると聞くとどうしても結果の方を思い浮かべてしまいますよね。子供がテストで100点を取ってきた時、多くの人は「100点をとった」という結果を褒めてしまいます。
結果を褒めるのも大事ですが、自己肯定感を高めるには、100点をとるために「頑張って勉強した」という行動を褒める方が効果的です。
結果のみ褒めていると、失敗して結果が出せなかったときに大きな喪失感を抱えてしまうかもしれません。
小さな成功を褒める
褒めるのが大事なのはわかっているけど、中々褒めることなんてないと感じてしまう人もいると思います。
そういう時は褒めることのハードルを下げてみてください。子供が向かっている課題を細かく分けて考え、1つの段階を成功する毎に褒めるのが良いです。
例えば、ご飯をこぼさずきれいに食べるということを目標としたとき、それを次のように分けます。
- お箸、スプーンなどをちゃんと持つ。
- 一口で食べられるように切ったり、すくったりする。
- 口に入っているものを飲み込んでから次のものを食べる。
何か達成したら褒めて、一つずつ課題をクリアしていくことで、最終的な目標を達成できます。褒める回数も増えて子供の成功体験も増えるので一石二鳥です。
こちらの動画が子供の褒め方について参考になります。
子供は褒められたことよりも、怒られたことの方が強く残ってしまいます。怒り方にも注意して、できるだけたくさん褒めてあげましょう。
余計な刺激はなるべく避ける

頑張って目を合わせようとしても、子供が塞ぎ込んでしまい難しい時もあるかもしれません。
発達障害を持つ場合、感覚過敏になっていることが多いです。知らぬ間に大きなストレスを抱えてしまい、コミュニケーションがとりづらくなることもあります。
感覚過敏を持っているとどうなるかは、こちらの動画で紹介されています。
太陽の光や周りの雑音など、様々な刺激がストレスになってしまいます。感覚過敏でなくても、ADHDの場合、動くものに気を取られて集中できなかったり、目を合わせることできなかったりします。
日常生活の中で、子供が過ごしやすい環境を整えることも、子供とのコミュニケーションをとるためには必要になってきます。
まとめ
発達障害と診断されている子やなんとなく育てにくいなあと感じてしまう子との接し方について書いてきました。
ポイントは以下の4点です。
- 親子で一緒に遊ぶ時間を作り、その中でなるべく子供と目を合わせてコミュニケーションをとる。
- 子供を叱る時は感情的にならず、何が悪かったのかを端的に伝えるか考えさせる。
- 子供が頑張ったこと、やろうとしている姿勢をいっぱい褒めてあげる。
- ストレスを感じにくい環境や子供が集中しやすい状況づくりを心掛ける。
色々と紹介してきましたが、「わかってはいるけど、中々実践できない。」「こんなこと気にしている余裕ないよ。」と感じた方も少なくないと思います。
正直な話、家事や仕事もしつつ、これらすべてを完璧に実践できる人はほとんどいないのではないでしょうか。親だって人間ですからね。
それでも、少しずつ意識していくことで、子供と共に親も一緒に成長していけたら良いですね。愛情を持って接すれば、子供にもその思いはいつか伝わってくれるはずです。



