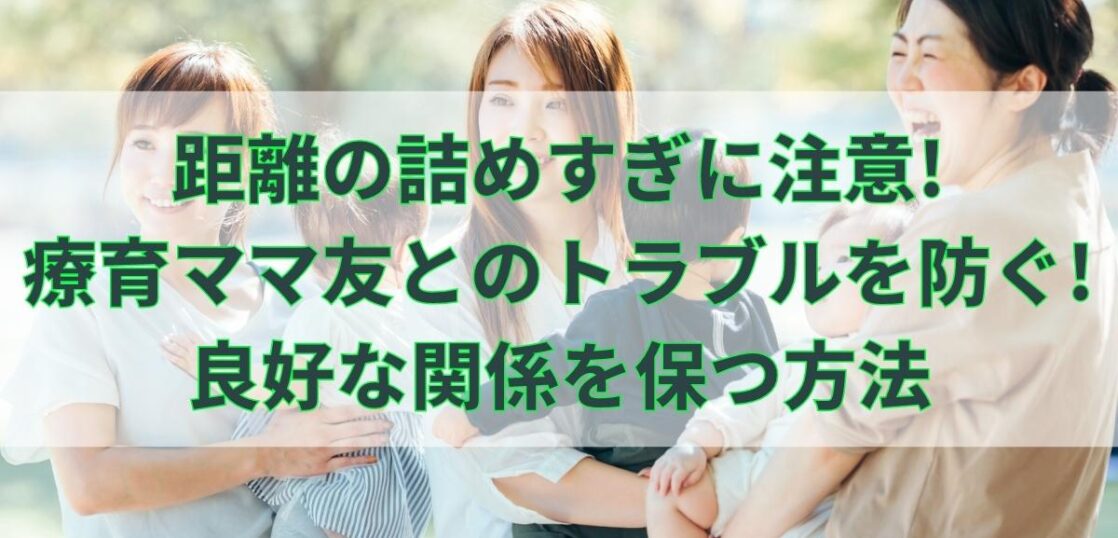皆さんこんにちは!本日も発達障害等に関する学びや情報交換の場になることを願って投稿させて頂きます。
今日のトピックは「療育ママ友との付き合い方」についてです。
「定型発達の子どもをもつママ友には、発達障害児の子育ての大変さは伝わらない」
「療育ママ友と繋がって、共感し合えていたと思ったら、話した後に何か疑問が残ったり、比べられたりしてモヤモヤする」
療育ママ友との距離をうまくとれずお困りの方は、上記のような経験はありませんか?
今回紹介する「療育ママ友との距離の取り方」を参考にして、必要のないトラブルやストレスを無くしていきましょう。
目次
療育ママ友との付き合いで大事なのは心地良い距離感

どんな人間関係も簡単ではありません。
一人ひとり考え方や解釈の仕方が違い、自分と全く同じという人はいないと思った方が良いでしょう。
共通点があるほど人は仲良くなりやすい
世の中には「類似性の法則」というものがあります。類似性の法則は「共通点が多いほど人は親近感を持つ」という意味です。
発達障害の子育てに悩み、心細く感じている時に療育ママ友と話すと、気持ちを分かってもらえたり「自分だけじゃない」と安心し、頼りにできる存在です。
急激に仲良くなったその後のズレ
そのままお互いに心地良く関われるのであれば、何も問題はありません。
しかし急激に仲良くなった後、徐々に「何か合わない」とズレを感じることはよくあります。
以下はご縁があって仲良くなった療育ママ友と我慢して付き合いを続け、ストレスを感じる方のお気持ちツイートです。
【仲良くなった後に生じる療育ママとのズレ一例】
- 「言いたいけど言えない」
- 「言われたアドバイスに納得できないけど、ありがたく受け取ってしまう」
自分と相手のちょっとした「ズレ」から、仲良くなった関係にヒビが入り、気まずくなってしまったという悩みを抱える方も多いとされています。
療育ママ友と良い関係を保つために必要な事
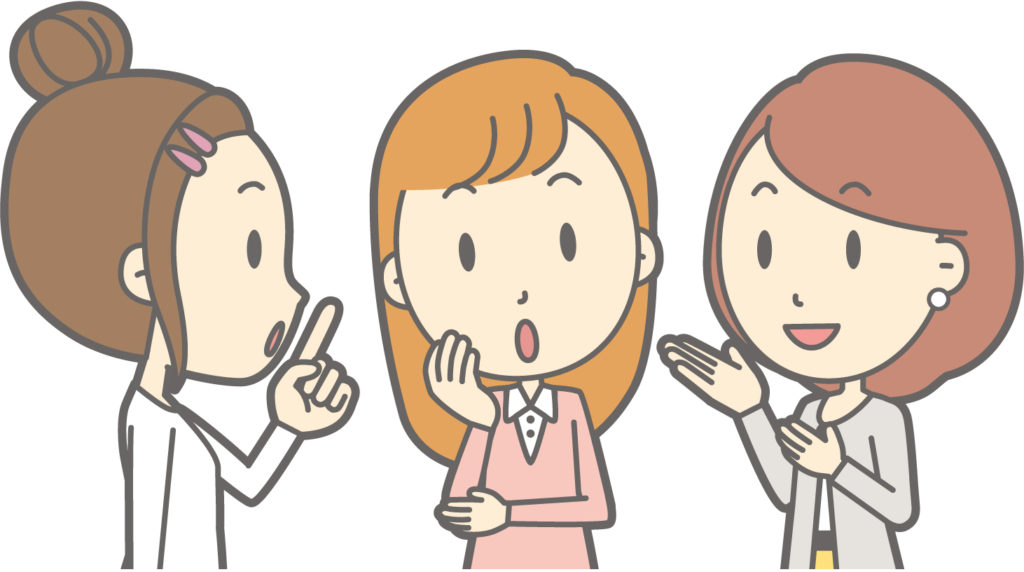
無理に「お互いにとって」と考えず、あくまで自分を軸にして考えてみましょう。
そもそもママ友を作るには?
ママ友との付き合い方を前提にしましたが、まずママ友を作りやすくなる「自分のあり方」をお伝えします。
・PTAの役員や地域の仕事はきちんとこなす
・にこやかに挨拶する
・自分の意見を柔らかく主張する
・相手の意見に同調しすぎない
ママ友が出来やすい人や、ママ友付き合いが無理なく長続きする人は、以上の事を実践している方が多いでしょう。
「情報交換が出来るママ友」という位置づけにする
ママ友の間では様々な情報交換が可能です。例を挙げると、ネットでは得られない地域の情報や施設・病院の口コミ、イベントやセミナーなどが挙げられます。
つまり、実際の体験談は何よりも参考になりえるということです。
特に療育に関する保育園・学校・施設の情報1つで、助かったという方がたくさんいます。
以下のツイートでは、療育ママさんたちの情報網のおかげで、一人では超えられない壁があることがわかります。
ママ友は「感情面を解消してくれる相手」ではなく「情報交換相手」と思うことをおすすめします。
反対に、自分が情報を提供するのも良いでしょう。
相手の状況を把握する
一人ひとり、子どもの発達障害の程度が違い、お母さんの考え方も違います。
自分の話もしながら、相手の状況を把握できると良いでしょう。例えば以下のような家族構成についてです。
- 相手の子どもの状況
- お母さんの考え
- 療育に積極的か、ほどほどか
大まかですが、これらの事を最初に話しておくと、後々「合わないな・・」と落胆することが少なくなります。
相手に精神的な余裕があるかを配慮する
自分が心細い時、頼りになるのが似た状況にいる療育ママ友です。
しかし、相談したり愚痴を吐き出す時は、相手の状況に配慮することをおすすめします。
友達は「いつの間にか仲良くなっていた」くらいが良い
友達を「作ろうと頑張る」と、あまり気が合わないのに無理して相手に合わせてしまうことが多々あります。
最初は「情報交換相手」の位置づけだった人でも、いつの間にか雑談や色々な話をするようになっていたら、「友達」と呼べるでしょう。
こちらの動画では、早期療育施設に通ううちに先輩の療育ママにたくさんの事を教えてもらったと語られています。
療育を通して友達が出来、深く話をする関係になることは、子育てをする上でかけがえのない存在になります。
先輩ママであり、支援する側に回っている人
発達障害をもつ子どもが高校生・大学生・社会人になり、今度は支援側に転じる方も少なくありません。
仕事としては未経験でも「発達障害の子育て」という実体験があるからこそ出来ることがたくさんあります。
不安を抱えている人に寄り添い、知識もある方が身近にいると心強いですね。
お住いの地域のNPO法人や、「親の会」を開催している方もおられます。
こちらの記事の後半に「親の会」の情報を載せていますので、ご参考程度にご覧ください。
ほどほどの距離を保つテクニック

ここからは具体的にほどほどの距離を保つ方法をお伝えします。
どちらかというと「自分を守る方法」です。
LINEでのやりとり
便利な連絡ツールですが、文字のやり取りは誤解を生みやすくなるものでもあります。
例えば以下のツイートでは療育ママさんとのLINEのやり取りについて語っています。
療育ママさんとのつながりは大切ですが、自分の意思も大切にした方が付き合いやすい例です。
直接会って話すとそんなに気にならないことでも、文字にすると相手の表情や真意が分からず、戸惑うことがあります。
LINEなどの文字のやりとりこそ「情報交換」「約束の連絡」くらいに留めておき、言いにくい話などは会って話すことが無難でしょう。
連絡頻度を抑える
特にLINEは「会話のようにテンポよくやりとりするもの」という考えから、「すぐに返さないと」と思う人がいます。
人それぞれのタイミングがあったり、時間の使い方が違います。
緊急なこと以外は、すぐに返信する必要はありません。
仕事や家事や子育てをする上に人とのやりとりを優先させていたら、自分の時間は到底作れません。
グループLINEには入らない・通知オフ
グループLINEは苦手という方は、案外多いものです。
グループLINEが苦手な方は、グループに入ることを断って、個別に連絡してもらえるようにお願い出来れば一番良いですが、そうもいかない時がありますよね。
そんな時はグループLINEに入っても「通知オフ」の機能を使うことをおすすめします。
通知が来るたびに見ていると、それこそ自分の時間がどんどん減っていきます。
誘いを断りたい時
誘ってもらったママ友会やランチ会などに行ってみたけど、あまり楽しめなかった。
それにもかかわらず、次に誘われた時も断れずに行ってしまい、ストレスになっていることはありませんか?
「断る時に、それなりの理由が無いといけない」と思い、断れずにいるという悩みをよく聞きます。
本来、断る時に理由を言う必要はありません。
「行きたいんだけど、予定があるんだ、ごめんね」
この程度の言い方で問題ありません。表情は「申し訳ない」と「ニコニコ」の半々くらいが良いでしょう。
療育ママとの良い関係を作るためにしない方が良いこと

「されると困る」ことがたくさんありますが、反対に「しない様に気をつけること」をお伝えします。
自分の意見を押し付けない
特に療育中にうまくいったことがあると、人に話したくなりますよね。
自分が良い気分の時こそ、療育ママ友への声かけは配慮が必要です。
同じ事を言うのでも、言い方を工夫してみると、感じが変わります。
自分の気持ちを伝えるだけにする
×「これ良かったから、絶対にやった方が良いよ」
〇「うちはこれを試してみて、うまくいったから嬉しい」
このように、「おすすめする」のではなく、あくまで「自分の気持ち」を伝えるだけにすると、相手は嫌な気持ちになりません。
「アイメッセージ」で伝える
「あなたが」「あなたは」と相手を主語にしがちですが、「アイメッセージ」と呼ばれる「私」を主語にして気持ちを伝えるとコミュニケーションがスムーズになる方法があります。
こちらの記事をぜひ参考にしてみて下さい。
主語を「私」にして伝えるのです。主語を私にすることで、相手のテリトリーを守りつつ、柔らかい表現が可能となります。
引用 アイメッセージとは?意味と使い方、ユーメッセージとの違い
たくさん話しすぎない
もし、普段から自分の話をしすぎてしまうと自覚している方は、話しすぎないように気を付けた方が、療育ママ友とも良好な関係を保てるでしょう。
「ツァイガルニク効果」というものがあります。
ドラマや漫画などを見てる時
・「良いところで終わるから続きが見たくなる」
という経験はありませんか?
会話でも、話しすぎないことで
・「もっと知りたい」「また会いたい」
と興味を持ってもらえます
ツァイガルニク効果を利用して話しすぎなければ、好感を持ってもらい、良好な関係を続けられるでしょう。
もちろん悩みや不安があれば、じっくり聞いてくれる人に素直に頼って下さい。
まとめ
今回は「療育ママ友との良好な関係の保つ方法」をお伝えしました。
大変なことが多く、まだまだ情報が多くない発達障害の子育てには、療育ママ友の存在はとても大きなものです。
いつかあなたが、先輩ママに教えてもらった役立つ情報を、同じように不安に思っている方に伝える時が来るかもしれません。
子育てで大変な中、ママ友の関係が負担にならない様に、距離感に気を付けながら関わることが、巡り巡って自分や子どものためになります。
人間関係は難しいこともありますが、一緒に頑張っていただければ幸いです。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。